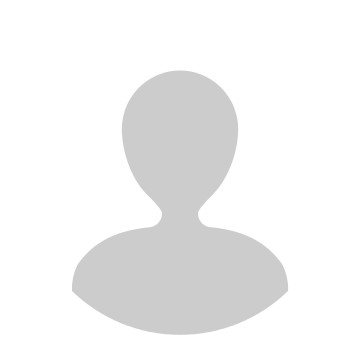|
гҖҖпјЈпјӨгҒЁгҒӢпј¬пј°гӮ’еҶҚз”ҹгҒ—гҒҰйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҸжҷӮгҒ«гҖҒе°‘гҒ—гҒ§гӮӮиүҜгҒ„йҹігҒ§иҒҙгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҖҒиүІгҖ…гҒЁгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиЈ…зҪ®гӮ’гҒқгӮҚгҒҲгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒҫгҒӮгҒҫгҒӮиҮӘеҲҶгҒ®ж„ҸеӣігҒҷгӮӢйҹігҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒдәәгҒ«иҒһгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжң¬дәәгҒ»гҒ©гҒ®ж„ҹжҝҖгҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮйҖҶгҒ«дәәгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒҹгҒ„гҒҰгҒ„гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®йҹігҒ®ж–№гҒҢеҘҪгҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮпјҲе№ёгҒӣгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒз§ҒгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒиҒһгҒӢгҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢйҹігҒ®д»Ій–“гҒ«жҒөгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢпјүгҒқгӮҢгҒ»гҒ©еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢйҹігҒҜдәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҝгҒӘйҒ•гҒҶгҒ®гҒ гҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒиӘ°гӮӮгҒҢзӣ®жҢҮгҒҷиүҜгҒ„йҹігҒЁгҒҜгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶйҹігӮ’гҒ„гҒҶгҒ®гҒӢгҖӮпјЈпјӨгҒЁгҒӢпј¬пј°гҒҢе®ҹйҡӣгҒ®жҘҪеҷЁгҒ§жј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢйҹігҒ«иҝ‘гҒҘгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«з•°и«–гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰпј®пјЁпј«дәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғӘгғӢгӮ№гғҲгҒ®ж №жҙҘжҳӯзҫ©гҒ•гӮ“гҒҢгҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢз§ҒгҒҜпјЈпјӨгӮ„гғ¬гӮігғјгғүгӮ’иҒҙгҒҸжҷӮжј”еҘҸ家гҒ®ж„ҸеӣігҒҢгӮҲгҒҸеҲҶгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«дјҡе ҙгҒ®е®ўеёӯгҒ§иҒһгҒ“гҒҲгӮӢйҹігӮ’иҒҙгҒҸдәӢгӮ’дёҖз•ӘеӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гҒҷгҒҢжј”еҘҸ家гҒ®ејҫгҒҚж–№гӮ’иҒһгҒҚеҸ–гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҶжҷӮгҒҜжј”еҘҸ家гҒЁеҗҢгҒҳгӮ№гғҶгғјгӮёгҒ®дёҠгҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒ§иҒҙгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮпјҲдҪҶгҒ—гҒқгҒ®е ҙеҗҲгӮӮжј”еҘҸ家гҒӢгӮүе°‘гҒ—и·қйӣўгӮ’гҒҠгҒ„гҒҹж„ҹгҒҳгҒ§иҒҙгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжј”еҘҸгӮ’иҮіиҝ‘и·қйӣўгҒ§иҒҙгҒҸгҒ®гҒҜиҝ«еҠӣгҒҜгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢжӮӘйҒҺгҒҺгҒҰдёҖз•ӘеӨ§еҲҮгҒӘе…ЁдҪ“гҒ®ж§ӢжҲҗгҒҢиҒһгҒҚеҸ–гӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«йҹігӮ’йҒ гҒҸгҒ«йЈӣгҒ°гҒҷзӮәгҒ®жј”еҘҸйӣ‘йҹігҒҢеј·йҒҺгҒҺгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮпјүгҖҚ
гҒ“гҒ“гҒ§ж №жҙҘгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ®пјіеёӯгҒ§иҒһгҒҸйҹігҒЁгҖҒжј”еҘҸ家гҒ®иҝ‘гҒҸгҒ§иҒһгҒҸйҹігҒ®2йҖҡгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ„гҒҡгӮҢгҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒжҘҪеҷЁгҒ®йҹіиүІгӮ’иүҜгҒҸиҒһгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гғҷгғігғҒгғһгғјгӮҜгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«иҸ…йҮҺжІ–еҪҰгҒ•гӮ“гҒҢгҖҒгғ¬гӮігғјгғүжј”еҘҸ家論гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жҸҗе”ұгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҗҢгҒҳгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ®жӣІгҒ§гӮӮгҖҒжҢҮжҸ®иҖ…гҒ®ж•°гҒ гҒ‘гҒ®жј”еҘҸж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ©гӮҢгӮӮгҒқгҒ®жӣІгҒ®и§ЈйҮҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ§иҒһгҒ“гҒҲгӮӢйҹігҒ®и§ЈйҮҲгӮӮгҖҒ10дәә10иүІгҒ®и§ЈйҮҲгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚдәәгҒ®ж•°гҒ гҒ‘иҒһгҒ“гҒҲж–№гҒҢйҒ•гҒҶгҒҜгҒҡгҒ гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘдәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гӮ“гҒӘйўЁгҒ«жӣёгҒҸгҒЁгҖҒзөҗеұҖгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒ§гӮӮжң¬дәәгҒҢиүҜгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӘгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҢжң¬дәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдёҖз•ӘиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮдәәгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®дәәгҒҜиҝ‘гҒ„йҹігҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгӮ“гҒ гҖҒгҒ“гҒ®дәәгҒҜпјіеёӯгҒ®йҹігҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгӮ“гҒ гҖҒгҒ“гҒ®дәәгҒҜйҹҝгҒҚгҒ®иүҜгҒ„гғӣгғјгғ«гҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгӮ“гҒ гҖҒгҒ“гҒ®дәәгҒҜгӮҜгғӘгӮўгҒӘйҹігҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгӮ“гҒ гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶж§ҳгҒ«зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒ10дәә10иүІгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰжёҲгҒҫгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„йҹігҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜжҘҪеҷЁгҒ®йҹігҒҢгҖҒжҘҪеҷЁгҒ®йҹігҒЁгҒ—гҒҰиҒһгҒ“гҒҲгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«йӢӯгҒ„йҹігӮ’еҮәгҒҷжҘҪеҷЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжҘҪеҷЁгҒЁгҒ„гҒҶд»ҘдёҠгҒҜгҒқгҒ®йҹігҒҜгҖҒдәәгҒ«еҝғең°гӮҲгҒ„гҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢз•°ж§ҳгҒ«йҹігҒҢзЎ¬гҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҹізЁӢгҒҢиҒһгҒҚеҸ–гӮҢгҒӘгҒ„гҒ»гҒ©гҒјгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰдёҚеҝ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶйҹігӮ’иҒҙгҒӢгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮгҒ«зҡҶгҒ•гӮ“гҒҜгҒ©гҒҶеҜҫеҝңгҒ—гҒҫгҒҷгҒӢгҖӮ
гҖҖжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жӯЈзӣҙгҒ«гҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒиҒһгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢдәәй–“й–ўдҝӮгҒҢжңүгӮҢгҒ°е•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҖҢе°ҸгҒ•гҒӘиҰӘеҲҮгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘиҝ·жғ‘гҖҚзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒ«гӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒ гҒҫгҒ гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҜеҘҘгҒҢж·ұгҒҸгҖҒдәәгҒӢгӮүеӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҹігҒ®ж–№еҗ‘гӮ’иЁҖи‘үгҒ§иЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҖҒд»Ій–“гҒ®зҺҮзӣҙгҒӘж„ҸиҰӢгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжұәгҒ—гҒҰжҖ’гӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еҝғгҒҢгҒ‘гҒҰгҖӮ

д»ҠжңқгҒҜгҖҒжҳЁж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йӣЁгҒҜгҒұгӮүгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ©гӮ“гӮҲгӮҠгҒЁжӣҮгҒЈгҒҹгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®еҶ¬гӮ’йҖЈжғігҒ•гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеӨ©ж°—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳЁж—ҘгҒҜеІЎеҙҺгҒ«дёӯеҸӨгҒ®пј¬пј°гӮ’иІ·гҒ„гҒ«иЎҢгҒҚгҖҒ40жһҡгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ1000жһҡд»ҘдёҠгҒҜгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢпј¬пј°гӮ’1жһҡ1жһҡгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҖҒгҒ»гҒ—гҒ„гҒӘгҒЁжҖқгҒҶгӮӮгҒ®гҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮӢгҒЁгҖҒзӣӨгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҖҒгӮ„гҒӨгӮҢгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒӮгҒЈгҒЁгҒ„гҒҶй–“гҒ«еҚҠж—ҘгҒҢйҒҺгҒҺгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮз§ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢгғ¬гӮігғјгғүгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮҠгҖҒдәҲе®ҡгӮҲгӮҠгӮӮжІўеұұиІ·гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгӮёгғЈгӮәгҒ®пј¬пј°гӮӮ3жһҡгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒд»–гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгӮҜгғ©гғғгӮ·гӮҜгҒ®пј¬пј°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҒ“гҒ®жүӢгҒ®еә—гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜзҸҚгҒ—гҒҸгҖҒе°‘гҒ—гҒҠгҒҫгҒ‘гҒҫгҒ§гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮжҘҪгҒ—гҒ„жҷӮй–“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгӮ’д»ҠжңқгҒӢгӮүиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒҜгҒ•гӮҸгӮҠгҒ®йғЁеҲҶгҒ гҒ‘гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒжј”еҘҸеҶ…е®№гҒЁгҒӢгҖҒгғҺгӮӨгӮәгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒЁгҒӢгҖҒйҢІйҹігҒ®иүҜгҒ—жӮӘгҒ—гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҖҒеҫҢгҒӢгӮүгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁиҒҙгҒҚгҒӘгҒҠгҒҷгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒ„гӮӢгҖӮеҲқеҜҫйқўгҒ®дәәгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒгӮҸгҒҸгӮҸгҒҸгҖҒгғүгӮӯгғүгӮӯгҒҷгӮӢзһ¬й–“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪ•гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ®гғӘгӮ№гғҲгӮ’гҒ“гҒ“гҒ«иЁҳгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҒҜ3жһҡгҒ®гӮёгғЈгӮә
гғ»Glad To Be Unhappy / Paul Desmond (VICTOR)
гғ»Come With Me / Tania Maria (Concord)
гғ»Largo / The Swingle Singers(Fontana)
ж—Ҙжң¬иӘһгҒ§гҖҢжҒӢжғ…гҖҚгҒЁйЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгғқгғјгғ«гғ»гғҮгӮ№гғўгғігғүгҒ®LPгҒҜгҖҒгҒәгғ©гғ»гӮёгғЈгӮұгҒ§зңәгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮзҫҺгҒ—гҒҸгҖҒйҹігӮӮиүҜгҒ„гҖӮж¬ЎгҒҜз§ҒгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгӮҰгӮЁгӮ№гғҲгғҹгғігӮ№гӮҝгғјгҒ®пј¬пј°
гғ»гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғіпјҡпјіпјұ1з•ӘгҖҒ2з•ӘпјҸгғҗгғӘгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈ
гғ»гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғіпјҡпјіпјұ15з•ӘпјҸгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮігғігғ„гӮ§гғ«гғҲгғҸгӮҰгӮ№еӣӣйҮҚеҘҸеӣЈ
гғҗгғӘгғӘгӮӮгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮігғігғ„гӮ§гғ«гғҲгғҸгӮҰгӮ№гӮӮпјЈпјӨгҒ§гҒҜдҪ•жһҡгҒӢжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠпј¬пј°гҒ§иҒҙгҒҸжј”еҘҸгҒҜгҖҒйҹігҒ®й®®еәҰгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгҒӨгӮ„гҒЁгҒ„гҒ„гҖҒең§еҖ’зҡ„гҒ«гҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮзү№гҒ«гғҗгғӘгғӘгҒ«гӮҲгӮӢеҲқжңҹгҒ®гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғіпјіпјұгҒҜжң¬еҪ“гҒ«иӢҘгҖ…гҒ—гҒҸгҖҒж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢгҖӮж¬ЎгҒҜгғҗгғғгғҸгҒ®гғӯзҹӯиӘҝгғҹгӮөжӣІ
гғ»гӮ«гғјгғ«гғ»гғҹгғҘгғігғ’гғігӮ¬гғјжҢҮжҸ®пјҸгӮ·гғҘгғҲгӮҰгғ„гғҲгӮ¬гғ«гғҲе®ӨеҶ…з®ЎејҰжҘҪеӣЈпјҲгғӯгғігғүгғіпјү
гғ»гӮ«гғјгғ«гғ»гғӘгғ’гӮҝгғјжҢҮжҸ®пјҸгғҹгғҘгғігғҳгғігғ»гғҗгғғгғҸз®ЎејҰжҘҪеӣЈпјҲгӮўгғ«гғ’гғјгғ•пјү
дёЎиҖ…гҒҜеҜҫз…§зҡ„гҒӘжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҹгғҘгғігғ’гғігӮ¬гғјгҒ®жҡ–гҒӢгҒ•гҖҒгғӘгғ’гӮҝгғјгҒ®еҺігҒ—гҒ•гҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгғӘгғ’гӮҝгғјгҒ®гӮўгғ«гғ’гғјгғ•зӣӨгҒ«гҒҜгҖҒгҒӘгҒңгҒӢгӮ°гғ¬гӮҙгғӘгӮӘиҒ–жӯҢгҖҢгӮҸгҒҢдё»гӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲеҫЎйҷҚиӘ•гҒ®з¬¬1гғҹгӮөгҖҚгҖҢиҒ–йңҠйҷҚиҮЁзҘӯгҒ®гғҹгӮөгҖҚгғ‘гғ¬гӮ№гғҲгғӘгғҠгҖҢжұқгҒҜгғҡгғҶгғӯгҒӘгӮҠгҖҚгҖҢгғһгғӘгӮўиў«жҳҮеӨ©гҒ®гғҹгӮөгҖҚгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгғүгӮӨгғ„зӣҙијёе…ҘзӣӨгҒҢгӮ»гғғгғҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮж¬ЎгҒҜеҸӨгҒ„гғ¬гӮігғјгғү
гғ»гғҗгғғгғҸпјҡзө„жӣІз¬¬2гғӯзҹӯиӘҝгҖҒ第3гғӢй•·иӘҝпјҸгғҹгғҘгғігғ’гғігӮ¬гғјжҢҮжҸ®пјҲгғӯгғігғүгғіпјү1955е№ҙ
гғ»гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲпјҡгӮҜгғ©гғӘгғҚгғғгғҲеҚ”еҘҸжӣІпјҸгӮҰгғјгғ—гғ©гғүгӮҘжҢҮжҸ®пјҲANGEL жқұиҠқйӣ»ж°—пјү
гғ»гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғіпјҡгғӯгғһгғігӮ№1з•ӘгҖҒ2з•ӘпјҸгӮӨгӮҙгғјгғ«гғ»гӮӘгӮӨгӮ№гғҲгғ©гғ•пјҲж—Ҙжң¬гӮ°гғ©гғўгғ•гӮ©гғіпјү
гғ»гғ©гғ•гғһгғӢгғҺгғ•пјҡгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІ2з•ӘпјҸгғ«гғјгғ“гғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғіпјҲRCAпјү1956е№ҙ
гҒ“гҒ®й ғгҒ®LPгҒҜйҮҚйҮҸзӣӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж¬ЎгҒҜгғ“гӮҜгӮҝгғјгҒ®гғӘгғ“гғігӮ°гғ»гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®3жһҡ
гғ»гғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјпјҡгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғіеҚ”еҘҸжӣІпјҸгғҸгӮӨгғ•гӮ§гғғгғ„
гғ»гғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјпјҡгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІ1з•ӘпјҸгӮҜгғ©гӮӨгғҗгғјгғіпјҲPпјүгӮӯгғӘгғ«гғ»гӮігғігғүгғ©гӮ·гғіжҢҮжҸ®
гғ»гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲпјҡдәӨйҹҝжӣІз¬¬40з•ӘпјҸгӮ«гғ©гғӨгғіжҢҮжҸ®пјҸгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«
иӢҘгҒҚж—ҘгҒ®гӮ«гғ©гғӨгғігҒҜгҖҒжҷ©е№ҙгҒ®еӨ–йқўзҡ„гҒӘзҫҺйҹігҒ®иҝҪжұӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪңзӮәгҒҜж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҡгҖҒжң¬еҪ“гҒ«иӢҘгҖ…гҒ—гҒҸгҖҒгҒҝгҒҡгҒҝгҒҡгҒ—гҒ„гҖӮгҒҫгҒ еҚҠеҲҶгӮӮзҙ№д»ӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮӮгҒҶжҷӮй–“гҒ гҖӮз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҒгҒҫгҒҹгҒ„гҒӨгҒӢгҖӮ

д»Ҡж—ҘгҖҒ11жңҲ3ж—ҘгҒҜиұҠз”°еёӮгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ®й–ӢйӨЁ9е‘Ёе№ҙгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҗгғјгӮ№гғҮгғјгғ»гӮігғігӮөгғјгғҲгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮиұҠз”°еёӮгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒ—гҒҹгҖҒж„ӣзҹҘзңҢеҮәиә«гҒ®зӢ¬еҘҸиҖ…гҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“еҮәжј”гҒ—гҒҰгҖҒ22жӣІгҒ®е°Ҹе“ҒгӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒҢжј”еҘҸгҒ—гҒҹгҖӮдјҙеҘҸгӮ’еӢӨгӮҒгӮӢгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒҜгҖҒе°Ҹзү§еёӮгҒ«жң¬жӢ ең°гӮ’зҪ®гҒҸдёӯйғЁгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҖҒжҢҮжҸ®гҒҜжқҫе°ҫи‘үеӯҗпјҲеҗҚеҸӨеұӢеёӮеҮәиә«пјүгҒ•гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ
еҚ°иұЎгҒҢеј·гҒӢгҒЈгҒҹзӢ¬еҘҸиҖ…гӮ’й ҶдёҚеҗҢгҒ§зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҲгғғгғ—гҒҜгғ•гғ«гғјгғҲгҒ®й«ҳжңЁз¶ҫеӯҗпјҲиұҠз”°еёӮеҮәиә«пјүгҒ•гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮеҪјеҘігҒҢд»Ҡж—Ҙжј”еҘҸгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгғүгғғгғ—гғ©гғјдҪңжӣІгҒ®гҖҢгӮўгғігғҖгғігғҶгҒЁгғӯгғігғүгҖҚгӮҲгӮҠгғӯгғігғүгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҪјеҘігҒ®жҒ©её«иҘҝжқ‘жҷәжұҹгҒ•гӮ“гҒЁгҒ®з«¶жј”гҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгғңгғ«гғҢдҪңжӣІгҖҢгӮ«гғ«гғЎгғіе№»жғіжӣІгҖҚгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гӮ’гғҗгғғгӮҜгҒ«жј”еҘҸгҖӮеҪјеҘігҒ®гғ•гғ«гғјгғҲгҒҜгҖҒзўәеӣәгҒҹгӮӢгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ®ж·ұгҒ„йҹіиүІгҒЁйҹіжҘҪжҖ§гҒ«гҒҜж„ҹеӢ•гҒ®дёҖиЁҖгҖӮ
гҒқгҒ®ж¬ЎгҒҜеӨ§и°·еә·еӯҗпјҲеҗҚеҸӨеұӢеҮәиә«пјүгҒ•гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮеӨ§и°·гҒ•гӮ“гҒҜгҖҒгғўгғігғҶгӮЈдҪңжӣІгҒ®гғҒгғЈгғјгғ«гғҖгғјгӮ·гғҘгӮ’жј”еҘҸгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ®еҫҢйғЁгӮҲгӮҠзҷ»е ҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз§ҒгҒҜдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжңҖеүҚеҲ—гҒ®еёӯгҒ«гҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғ—гғӯгҒ®йҹігҒҜгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгҒЁзҙҚеҫ—гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮйҹійӣўгӮҢгҒ®иүҜгҒ„гҒ—гҒӢгӮӮзӢ¬зү№гҒ®гғқгғ«гӮҝгғЎгғігғҲгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘйҹҝгҒҚгҒ®зҫҺйҹігҒ§жј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮNHKгҒ®гғ©гӮёгӮӘз•Әзө„гҖҢгӮҜгӮӨгӮәз–‘е•ҸгҒ®йӨЁгҖҚгҒ®гғҶгғјгғһжӣІгҖҒгӮЁгғ«гӮ¬гғјдҪңжӣІгҒ®ж„ӣгҒ®гҒӮгҒ„гҒ•гҒӨгӮ’жј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒеӨ§и°·еә·еӯҗгҒ•гӮ“гҒӘгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®ж¬ЎгҒҜж°ёз”°зңҹеёҢпјҲиұҠз”°еёӮеҮәиә«пјүгҒ•гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮж°ёз”°гҒ•гӮ“гҒҜгҖҒжҜҚгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒе…Ҳз”ҹгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖҒгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғӢгӮ№гғҲгҒ®ж°ёз”°зңҹзҗҶеӯҗгҒ•гӮ“гҒЁгҖҒгғҗгғғгғҸгҒ®дәҢгҒӨгҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҚ”еҘҸжӣІгғӢзҹӯиӘҝгӮҲгӮҠ第1жҘҪз« гӮ’жј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжӣІгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢз§ҒгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘжӣІгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҪјеҘігҒ®иӢҘгҖ…гҒ—гҒҸгҒҰгҖҒеҲҮгӮҢгҒ®гӮҲгҒ„гҖҒгғӘгӮәгғ ж„ҹгҒЁгҖҒгӮЁгғғгӮёгҒ®з«ӢгҒЈгҒҹйҹіиүІгҒҜеӨ§еӨүйӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҖҒгҒҫгҒ•гҒ«зҸҫд»ЈгҒ®гғҗгғғгғҸгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҖҒеұұжң¬зңҹз”ұзҫҺпјҲгӮҪгғ—гғ©гғҺпјүгҒ•гӮ“гҖҒдҪҗйҮҺжҲҗе®ҸпјҲгғҶгғҺгғјгғ«пјүгҒ•гӮ“гҖҒжңҚйғЁеӯқд№ҹпјҲгғҲгғ©гғігғҡгғғгғҲпјүгҒ•гӮ“гҖҒеәғзҖ¬жӮҰеӯҗпјҲгғ”гӮўгғҺпјүгҒ•гӮ“гҖҒеҫіеІЎгӮҒгҒҗгҒҝпјҲгӮӘгғ«гӮ¬гғіпјүгҒ•гӮ“гҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гғЎгғігғҗгғјгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
жңҖеҫҢгҒ«зү№зӯҶгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгҒ®зөӮгӮҸгӮҠиҝ‘гҒҸгҒ§гҖҒдёӯйғЁгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҹгӮ·гғҷгғӘгӮҰгӮ№гҒ®гғ•гӮЈгғігғ©гғігғҮгӮЈгӮўгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жӣІгӮ’з”ҹжј”еҘҸгҒ§иҒһгҒҸгҒ®гҒҜеҲқгӮҒгҒҰгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жӣІгҒҢжҠ‘ең§гҒ•гӮҢгҒҹгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®дәәгҖ…гӮ’еӢҮж°—д»ҳгҒ‘гҖҒ第2гҒ®еӣҪ家гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҹҘиӯҳгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гӮ№гӮұгғјгғ«ж„ҹжәўгӮҢгӮӢжј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®дәӢгӮ’еј·гҒҸе®ҹж„ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӨ§еӨүж„ҹеӢ•зҡ„гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ



д»Ҡе№ҙгҒ®6жңҲгҒ«гҖҒзҹҘз«ӢгҒ«гҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ§гҖҢгғ©гӮӨгғ–гғ»гғҸгӮҰгӮ№гҒ®еӨңгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғҶгғјгғһгҒ§гҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮ’жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҹгӮүгҒЁдјҒз”»гҒ—гҖҒLPгӮігғігӮөгғјгғҲгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒқгҒ®жҷӮгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дҪңгҒЈгҒҹз§ҒгҒ®и§ЈиӘ¬ж–ҮгҒ§гҒҷгҖӮ
йҒёе®ҡгҒ—гҒҹ8жһҡгҒ®гӮёгғЈгӮәгғ»гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒ®LPгҒҜгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰеҘҮгӮ’гҒҰгӮүгҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғ©гӮӨгғ–гҒ®еҗҚзӣӨгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҖйғЁгӮ’йҷӨгҒҚгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒ§гҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«жә–еӮҷгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
(1) Art Blakey - Au Club St. Germain, Vol. 2 (RCA (F) 430044)
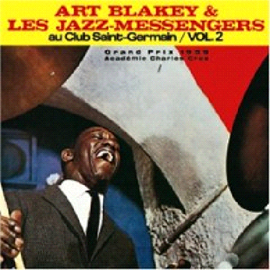
Lee Morgan (tp) Benny Golson (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (d)
"Club St. Germain", Paris, France, December 21, 1958
1. Moanin' With Hazel 13:56
гҖҢгӮөгғігӮёгӮ§гғ«гғһгғігҒ®гӮёгғЈгӮәгғЎгғғгӮ»гғігӮёгғЈгғјгӮәгҖҚгӮҲгӮҠгҖҢгғўгғјгғӢгғігғ»гӮҰгӮЈгӮәгғ»гғҳгӮӨгӮјгғ«гҖҚгҒӢгӮүгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮёгғЈгӮәгҒ®гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒ§гҒҜи¶…жңүеҗҚгҒӘзӣӨгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒгғ‘гғӘгҒ®гӮҜгғ©гғ–гғ»гӮөгғігӮёгӮ§гғ«гғһгғігҒ§гҒ®е®ҹжіҒйҢІйҹігҒ§гҒҷгҖӮ
гғЎгғігғҗгғјгҒ®дёҖдәәгҒ§гҖҒгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ®гғңгғ“гғјгғ»гғҶгӮЈгғўгғігӮәгҒҢдҪңжӣІгҒ—гҒҹгғўгғјгғӢгғігҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒ§гҒ®зҘҲгӮҠгҒ®гҒӨгҒ¶гӮ„гҒҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮҙгӮ№гғҡгғ«гӮҪгғігӮ°гҒ§гӮҲгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖҒгӮ·гғЈгӮҰгғҲе”ұжі•гҒЁгҒӢеҗҲгҒ„гҒ®жүӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒ“гҒ®жӣІгҒӢгӮүгҒҜиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮёгғЈгӮәгғЎгғғгӮ»гғігӮёгғЈгғјгӮәгҒҢж—Ҙжң¬гҒ«еҲқжқҘж—ҘгҒ—гҒҰгғ•гӮЎгғігӮӯгғјгғ»гғ–гғјгғ гӮ’е·»гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢ61е№ҙгҒ®1жңҲгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®2е№ҙеүҚгҒ®гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®дёӯгҒ§гҒ®еҪ“жҷӮгҒ®гғ‘гғӘгҒЈеӯҗгҒ®зҶұзӢӮгӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®гғўгғјгғӢгғігҒ®зҶұзӢӮжҢҜгӮҠгҒҢгҒ—гҒ®гҒ°гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гғўгғјгғӢгғігҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ«гӮҰгӮЈгӮәгғ»гғҳгӮӨгӮјгғ«гҒЁе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒе®ўгҒ®дёҖдәәгҒ§гҖҒжӯҢжүӢгҒ§гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ§гҒӮгӮӢгғҳгӮӨгӮјгғ«гғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒҢжј”еҘҸгҒ«ж„ҹжҘөгҒҫгҒЈгҒҰ Oh Lord, have mercyпјҒ гҒЁеҸ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҒҸгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гғҰгғӢгӮҫгғігҒ§гҒ®гғҶгғјгғһгҒ®еҫҢгғӘгғјгғ»гғўгғјгӮ¬гғігҒ®гғҲгғ©гғігғҡгғғгғҲгҖҒгғҷгғӢвҖ•гғ»гӮҙгғ«гӮҪгғігҒ®гғҶгғҠгғјгҖҒгғңгғ“гғјгғ»гғҶгӮЈгғўгғігӮәгҒ®гғ”гӮўгғҺгҒЁгӮўгғүгғӘгғ–гҒҢз¶ҡгҒҚгҖҒгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҒ«гғҳгӮӨгӮјгғ«гҒ®еЈ°гҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮжүӢжӢҚеӯҗгҒЁгҒӢжҺӣгҒ‘еЈ°гҒҢиүІгҖ…гҒЁе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгӮҜгғ©гғ–гҒ§гҒ®гғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҹйӣ°еӣІж°—гҒЁгҒӢгҖҒжј”еҘҸгҒЁдёҖдҪ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиҲҲеҘ®гҒҢдјқгӮҸгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
(2) The Cannonball Adderley Sextet In New York (Riverside RLP 404)
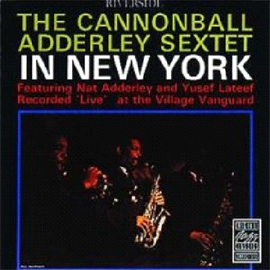
Nat Adderley (cor) Cannonball Adderley (as) Yusef Lateef (ts, fl, ob) Joe Zawinul (p) Sam Jones (b) Louis Hayes (d)
"Village Vanguard", NYC, January 12 & 14, 1962
1. Introduction 1:56
2. Gemini 11:36
гӮӯгғЈгғҺгғігғңгғјгғ«гҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгғ–гғ«гғјгғҺгғјгғҲгҒ®гҖҢгӮөгғ гӮ·гғігғ»гӮЁгғ«гӮ№гҖҚгҒЁгҒӢгҖҢгӮӨгғігғ»гӮ·гӮ«гӮҙгҖҚгҖҢгӮӨгғігғ»гӮөгғігғ•гғ©гғігӮ·гӮ№гӮігҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒҢжө®гҒӢгӮ“гҒ§гҒҸгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҢгӮӨгғігғ»гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгҖҚгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
ејҹгғҠгғғгғҲгғ»гӮўгғҖгғ¬гӮӨгҒЁгҒ®гӮҜгӮӨгғігғҶгғғгғҲгҒӢгӮүгҖҒгғҰгғјгӮ»гғ•гғ»гғ©гғҶгӮЈгғјгғ•гӮ’еҠ гҒҲгҒҹпј“з®Ўз·ЁжҲҗгҒ«жӢЎеӨ§гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®гғ•гӮЎгғігӮӯгғјгҒӘжј”еҘҸгҒ«йҮҚеҺҡгҒ•гҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йҷҪж°—гҒ§жҳҺгӮӢгҒ„е…„гҖҒгӮӯгғЈгғҺгғігғңгғјгғ«гғ»гӮўгғҖгғ¬гӮӨгҒ®гӮўгғ«гғҲгҖҒгӮ·гғЈгӮӨгҒӘејҹгҖҒгғҠгғғгғҲгғ»гӮўгғҖгғ¬гӮӨгҒ®гӮігғ«гғҚгғғгғҲгҖҒжқұжҙӢзҡ„гҒӘйҹіиүІгҒ®гғҰгғјгӮ»гғ•гғ»гғ©гғҶгӮЈгғјгғ•гҒ®гғ•гғ«гғјгғҲгҒЁгғҶгғҠгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹпј“з®Ўз·ЁжҲҗгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒҢеҖӢжҖ§зҡ„гҒӘгӮўгғүгғӘгғ–гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒҜеҫҢгҒ«гӮҰгӮЁгӮ¶гғјгғ¬гғқгғјгғҲгӮ’зөҗжҲҗгҒҷгӮӢгӮёгғ§гғјгғ»гӮ¶гғ“гғҢгғ«гҒҢеҠ гӮҸгҒЈгҒҰгӮўгғјгӮ·гғјгҒӘйҹіиүІгӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒҜгӮӯгғЈгғҺгғігғңгғјгғ«гҒҢгҒ“гҒ®е№ҙгҒ«гҖҒеҲқжқҘж—ҘгҒ—гҒҹжҷӮгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒ§гҖҒз§ҒгӮӮеҗҚеҸӨеұӢгҒ§гҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгҒ§еҪјгӮүгҒ®жј”еҘҸгҒ«жҺҘгҒ—гҖҒеӨ§еӨүиҲҲеҘ®гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’жҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
(3) Stan Getz And J.J. Johnson At The Opera House (mono) (Verve MGV 8265)

J.J. Johnson (tb -1/4) Stan Getz (ts) Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b) Connie Kay (d)
"Opera House", Chicago, IL, October 19, 1957
3. Crazy Rhythm 7:34
4. Yesterdays 3:38
5. It Never Entered My Mind 3:45
гҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҖҒгӮӘгӮ№гӮ«гғјгғ»гғ”гғјгӮҝгғјгӮҪгғігҒ®гғ¬гӮ®гғҘгғ©гғјгғ»гғҲгғӘгӮӘпјҲгғ”гғјгӮҝгғјгӮҪгғіпј°гҖҒгғ¬гӮӨгғ»гғ–гғ©гӮҰгғіпјўгҖҒгғҸгғјгғ–гғ»гӮЁгғӘгӮ№пј§пјүгҒ«гғүгғ©гғ гҒ®гӮігғӢгғјгғ»гӮұгӮӨгҒҢеҠ гӮҸгҒЈгҒҰгҖҒгғҗгғғгӮҜгӮ’гҒӨгҒЁгӮҒгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гғҶгғҠгғјгҒ®з¬¬пј‘дәәиҖ…гӮ№гӮҝгғігғ»гӮІгғғгғ„гҒЁгғҲгғӯгғігғңгғјгғігҒ®з¬¬пј‘дәәиҖ…J.J.гӮёгғ§гғігӮҪгғігҒҢ競演гҒҷгӮӢгҒЁиЁҖгҒҶеӨ§еӨүиұӘиҸҜгҒӘйЎ”гҒ¶гӮҢгҒ§гҖҒжңҖеҲқгҒ§жңҖеҫҢгҒ®жј”еҘҸдјҡгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒӢгӮүпј“жӣІиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖеҲқгҒ®гӮҜгғ¬гғјгӮёгғјгғ»гғӘгӮәгғ гҒҜдёЎиҖ…гҒ®гғӣгғғгғҲгҒӘ競演гҒ§гҒҷгҖӮжңҖеҲқгҒ«J.J.гҒҢгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҹгӮүгҒӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғҲгғӯгғігғңгғјгғігҒҢеҗ№гҒ‘гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгӮ’жҠ«йңІгҒ—гҖҒз¶ҡгҒ„гҒҰгӮҜгғјгғ«гҒӘгӮІгғғгғ„гҒҢгҒ“гӮҢгӮӮеӨ§еӨүгғӣгғғгғҲгҒ«гӮўгғүгғӘгғ–гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж¬ЎгҒ®гӮӨгӮЁгӮ№гӮҝгғҮгӮӨгӮәгҒ§гҒҜJ.J.гҒ®гғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгӮ’гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮӨгғғгғҲгғ»гғҚгғҗгғјгғ»гӮЁгғігӮҝгғјгғүгғ»гғһгӮӨгғ»гғһгӮӨгғігғүгҒ§гҒҜгӮІгғғгғ„гҒ®гғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгӮ’гҒҳгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁгҒҠжҘҪгҒ—гҒҝдёӢгҒ•гҒ„гҖӮпј“жӣІз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҠгҒӢгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
(4) Zoot Sims Quartet-Live at Ronnie Scott's '61
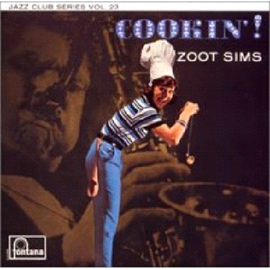
Zoot Sims (ts) Ronnie Scott (ts -1) Stan Tracey (p) Kenny Napper (b) Jackie Dougan (d)
"Ronnie Scott's Club", London, England, November 13-15, 1961
5. Autumn Leaves 7:24
гғҶгғҠгғјгҒ®гғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮзҡҶгҒ•гӮ“гҒ«иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁйҒёжӣІгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮәгҒ®гғӯгғӢгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮҲгӮҠжһҜи‘үгҒ®пј‘жӣІгҒ§гҒҷгҖӮгӮәгғјгғҲгҒ®гғҶгғҠгғјгҒ§гғҹгғҮгӮЈгӮўгғ гӮ„гӮўгғғгғ—гғҶгғігғқгҒ®жӣІгӮ’иҒһгҒҸгҒЁжҘҪгҒ—гҒҸгҖҒгӮ№гғӯгғјгҒӘжӣІгӮ’иҒһгҒҸгҒЁе„ӘгҒ—гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜеҲҮгҒӘгҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒӢгҖӮеҪјгҒ®гҒІгҒЁгҒ®иүҜгҒ„гҖҒе„ӘгҒ—гҒ„з”ҹгҒҚж§ҳгҒҢйҹіиүІгӮ„гғ•гғ¬гғјгӮәгҒ«гҒ«гҒҳгҒҝеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ§гҒҜгғҰгғӢгӮӘгғігҒ®еҠӣгҒҢеј·гҒҸгҒҰгҖҒеӨ–еӣҪгҒ®гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒҜгӮҜгғ©гғ–гҒ§жј”еҘҸгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жңҖеҲқгҒ«е®ҹзҸҫгҒ•гҒӣгҒҹгҒ®гҒҢгғӯгғӢгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒ§гҒ®гӮәгғјгғҲгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жһҜи‘үгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒеҸӨд»ҠжқұиҘҝгҒ®гӮёгғЈгӮәгғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒҢеҗҚжј”еҘҸгӮ’з№°гӮҠеәғгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮәгғјгғҲгҒ®жһҜи‘үгҒҜз§ҒгҒ®жңҖгӮӮеҘҪгҒҚгҒӘжӣІгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜLPгҒҢз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гғ•гғ¬гғғгӮ·гғҘгғ»гӮөгӮҰгғігғүгҒ®CDгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
(5) Chris Connor - Chris in Person (ATLANTIC SD-8040)
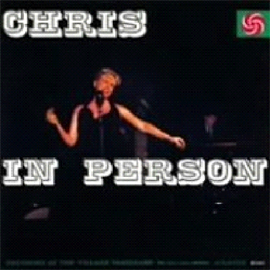
Chris Connor(Vocal) Bill Rubenstein (p) Kenny Burrell (g) Eddie de Haas (b) Lex Humphries (d)
"Village Vanguard", NYC,
1. Introduction
2. Strike Up The Band 2:07
3. Misty 3:10
4. Senor Blues 3:17
5. Lover Come Back To Me 2:38
6. Angel Eyes 3:46
7. Hallelujah I Love Him So 2:56
еҘіжҖ§гӮёгғЈгӮәгғңгғјгӮ«гғ«гӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒй»’дәәгҒ§гҒҜгғ“гғӘгғјгғ»гғӣгғӘгғҮгӮЈгӮ’еҲҘж јгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮЁгғ©гғ»гғ•гғғгғ„гӮёгӮ§гғ©гғ«гғүгҖҒгӮөгғ©гғ»гғңгғјгғігҖҒгӮ«гғјгғЎгғігғ»гғһгғғгӮҜгғ¬гӮӨгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзҷҪдәәгҒ§гҒҜгӮўгғӢгӮҝгғ»гӮӘгғҮгӮЈгҖҒгӮёгғҘгғјгғігғ»гӮҜгғӘгӮ№гғҶгӮЈгҖҒгҒқгҒ—гҒҰд»ҠеӣһеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгӮҜгғӘгӮ№гғ»гӮігғҠгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҗҚеүҚгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҜгғӘгӮ№гғ»гӮігғҠгғјгҒ®йӯ…еҠӣгҒҜгҖҒеЈ°йҮҸиұҠгҒӢгҒӘгғҸгӮ№гӮӯгғјгғңгӮӨгӮ№гҒ§гҖҒи»ҪгӮ„гҒӢгҒ«гҖҒзІӢгҒ«гӮ№гӮӨгғігӮ°гҒ—гҖҒйғҪдјҡдәәгҒ®зҹҘзҡ„гҒӘгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹеҘіжҖ§гӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гӮҜгғӘгӮ№гҒ®гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒҜгҒӮгҒҫгӮҠеӨҡгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгҒ®гғ“гғ¬гғғгӮёгғ»гғҗгғігӮ¬гғјгғүгҒ®гғ©гӮӨгғ–гҒ§гҒҜгҖҒгӮЁгғӯгғјгғ«гғ»гӮ¬гғјгғҠгҒ®дҪңжӣІгҒ—гҒҹгғҹгӮ№гғҶгӮЈгҒЁгҒӢгғӣгғ¬гӮ№гғ»гӮ·гғ«гғҗгғјгҒ®гӮ»гғӢгғ§гғјгғ«гғ»гғ–гғ«гғјгӮ№гҒқгҒ—гҒҰгғ¬гӮӨгғ»гғҒгғЈгғјгғ«гӮ№гҒ®гғҸгғ¬гғ«гғӨгғ»гӮўгӮӨгғ»гғ©гғ–гғ»гғ’гғ гғ»гӮҪгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹй»’гҒЈгҒҪгҒ„гӮӮгҒ®гӮӮеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгӮҜгғјгғ«гҒ«зІӢгҒ«гӮ№гӮӨгғігӮ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜиҒһгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
(6) Wynton Kelly/Wes Montgomery - Smokin' At The Half Note (Verve V/V6 8633)

Wynton Kelly (p) Wes Montgomery (g) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (d)
"Half Note", NYC, June 24, 1965
1. No Blues 12:49
гҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮӮгҖҒеҗҚзӣӨгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮгӮҰгӮӨгғігғҲгғігғ»гӮұгғӘгғјгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гғҲгғӘгӮӘгҒ«гӮ®гӮҝгғјгҒ®гӮҰгӮЁгӮ№гғ»гғўгғігӮҙгғЎгғӘгғјгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«зҷҪзҶұгҒ®жј”еҘҸгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮҰгӮЁгӮ№гғ»гғўгғігӮҙгғЎгғӘгғјгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гӮ®гӮҝгғјгҒ§пј‘гӮӘгӮҜгӮҝгғјгғ–йӣўгӮҢгҒҹйҹігӮ’еҗҢжҷӮгҒ«гғҰгғӢгӮҫгғігҒ§жј”еҘҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮӘгӮҜгӮҝгғјгғ–еҘҸжі•гҒ®гғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгӮ’еӨҡз”ЁгҒ—гҒҹдәәгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гӮӮгӮҰгӮЁгӮ№гҒ®гӮўгғүгғӘгғ–гҒҢйқҷгҒӢгҒ«е§ӢгҒҫгӮҠгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҒЁзҷҪзҶұгӮ’еёҜгҒігҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгӮӘгӮҜгӮҝгғјгғ–еҘҸжі•гҒҢеҶҙгҒҲгҒҫгҒҸгӮҠгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®гҒҷгҒ”гҒ•гҒ«гӮҰгӮӨгғігғҲгғігғ»гӮұгғӘгғјгҒҢиҒһгҒҚгҒ»гӮҢгҒҰгҖҒгғҗгғғгӮҜгӮ’еҸ–гӮӢгҒ®гӮ’жҷӮгҖ…жӯўгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гӮҰгӮӨгғігғҲгғігғ»гӮұгғӘгғјгӮӮгӮҰгӮЁгӮ№гҒ«и§ҰзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒҸгӮ№гӮӨгғігӮ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгғҒгӮ§гғігғҗгғјгӮ№гҒ®гғҷгғјгӮ№гӮҪгғӯгӮӮиІ гҒ‘гҒҡгҒ«зҶұгӮ’еёҜгҒігҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«зҷҪзҶұгҒ®гғ©гӮӨгғ–зӣӨгҒ§гҒҷгҖӮ
(7) Bill Evans - Waltz For Debby (Riverside RLP 399)
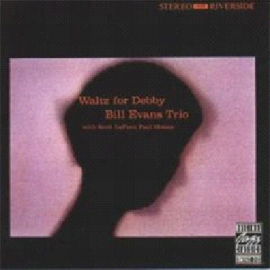
Bill Evans (p) Scott LaFaro (b) Paul Motian (d)
"Village Vanguard", NYC, matinee 1, June 25, 1961
1. My Foolish Heart 4:56
2. Waltz For Debby 6:54
гғ“гғ«гғ»гӮЁгғҗгғігӮ№гҒҢгғҷгғјгӮ·гӮ№гғҲгҒ®гӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгӮ’иҝҺгҒҲгҒҰгғ”гӮўгғҺгғ»гғҲгғӘгӮӘгӮ’зөҗжҲҗгҒ—гҖҒгғқгғјгғҲгғ¬гӮӨгғҲгғ»гӮӨгғігғ»гӮёгғЈгӮәгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢпј‘пјҷпј•пјҷе№ҙгҒ®жҡ®гӮҢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮү1.5е№ҙзөҢгҒЈгҒҰгҖҒгғ“гғ¬гғғгӮёгғ»гғҗгғігӮ¬гғјгғүгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮ’гӮөгғігғҮгӮӨгғ»гӮўгғғгғҲгғ»гӮ¶гғ»гғ“гғ¬гғғгӮёгғ»гғҗгғігӮ¬гғјгғүгҒЁгғҜгғ«гғ„гғ»гғ•гӮ©гғјгғ»гғҮгғ“гӮЈгҒЁгҒ„гҒҶ2жһҡгҒ®LPгҒЁгҒ—гҒҰзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢ1961е№ҙгҒ®6жңҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®11ж—ҘеҫҢгҒ«гӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгҒҜдәӨйҖҡдәӢж•…гҒ§дәЎгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гғҲгғӘгӮӘгҒ®зү№еҫҙгҒҜгӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгҒ®гғҷгғјгӮ№еҘҸжі•гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҫ“жқҘгҒ®гғҷгғјгӮ№гҒҢгҖҒгӮігғјгғүгӮ’дёҖйҹігҖҒдёҖйҹігҒ®еҚҳйҹігҒ§дёҖе®ҡгҒ®гғӘгӮәгғ гӮ’еҲ»гҒҝгҒӘгҒҢгӮүжј”еҘҸгҒҷгӮӢгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғ»гғҷгғјгӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒ®гӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгҒ®гғҷгғјгӮ№гҒҜгҒҫгӮӢгҒ§гғӣгғјгғіеҘҸиҖ…гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ”гӮўгғҺгҒЁдјҡи©ұгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгғігӮҝгғјгғ—гғ¬гӮӨгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҳҜйқһгғҷгғјгӮ№гҒ®йҹігҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
1жӣІзӣ®гҒ®гғһгӮӨгғ»гғ•гғјгғӘгғғгӮ·гғҘгғ»гғҸгғјгғҲгҒ§гҒҜгғ“гғ«гғ»гӮЁгғҗгғігӮ№гҒҢгҒҰгҒ„гҒӯгҒ„гҒ«йҹігӮ’йҒёгӮ“гҒ§гҖҒгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁгҒ—гҒӢгӮӮйқһеёёгҒ«гғҶгғігӮ·гғ§гғігҒ®й«ҳгҒ„гғ”гӮўгғҺгӮ’жј”еҘҸгҒ—е§ӢгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹгӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгҒҢгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгғҷгғјгӮ№гҒ§гҖҒгғ”гӮўгғҺгҒ«иӘһгӮҠгҒӢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзӣёж§ҢгӮ’жү“гҒӨгӮҲгҒҶгҒ«жј”еҘҸгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзӣҠгҖ…гӮЁгғҗгғігӮ№гҒ®гғ”гӮўгғҺгҒҢеҶ…еҗ‘зҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰиЎҢгҒҚгҖҒз·Ҡејөж„ҹгҒ®й«ҳгҒ„гғӘгғӘгӮ«гғ«гҒӘгғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжӣІгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҰе°‘гҒ—гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгҒ®ең°дёӢйү„гҒ®йӣ»и»ҠгҒ®йҹігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮжіЁж„ҸгҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
ж¬ЎгҒ®гғҜгғ«гғ„гғ»гғ•гӮ©гғјгғ»гғҮгғ“гӮЈгҒ§гҒҜгҖҒдёҖи»ўгҒ—гҒҰгғҷгғјгӮ№гҒҢгғ”гӮўгғҺд»ҘдёҠгҒ«йӣ„ејҒгҒ«гғ”гӮўгғҺгҒЁеҜҫи©ұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«гғҷгғјгӮ№гҒҢйӣ„ејҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжұәгҒ—гҒҰгӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғ»гғҷгғјгӮ№гҒ«гҒҜгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®з·Ҡејөж„ҹгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгғҷгғјгӮ№гҒЁгғ”гӮўгғҺгҒ®гӮӨгғігӮҝгғјгғ—гғ¬гӮӨгҒ«гӮӮзқҖзӣ®гҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
(8) Eric Dolphy - Last Date (Fontana (H) 681 008-ZL)
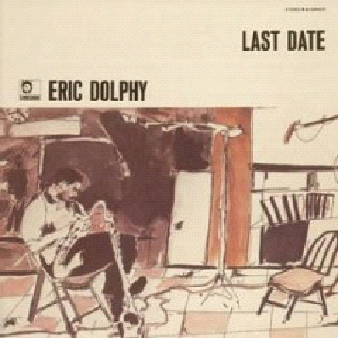
Eric Dolphy (as, bcl, fl) Misja Mengelberg (p) Jacques Schols (b) Han Bennink (d)
Hilversum, Holland, June 2, 1964
5. You Don't Know What Love Is 11:20
жңҖеҫҢгҒ«гӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®Last DateгҒЁиЁҖгҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮҲгӮҠYou Don't Know What Love IsгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®йӯ…еҠӣгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’иӘһгӮӢгҒ«гҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„дәәгҒҜгҖҒе®ҹгҒҜз§ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒ“гҒ“гӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҜж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮеҗҚгҒ®зҹҘгӮҢгҒҹгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®з ”究иҖ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҗҶи§ЈиҖ…гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮігғ¬гӮҜгӮ·гғ§гғігҒҜдё–з•ҢгҒ§гӮӮжңүж•°гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгҒІгҒЁгҒ®еүҚгҒ§гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгӮ’иӘһгӮӢгҒ®гҒҜгҒ„гҒӢгҒҢгҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе°‘гҒ—и©ұгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮёгғЈгӮәгҒ®гҒҝгҒ§гҒӘгҒҸгҖҒиҠёиЎ“дёҖиҲ¬гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дҪңе“ҒгҒ«жҺҘгҒ—гҒҹжҷӮгҒ«еүІгӮҠгҒЁжҠөжҠ—гҒӘгҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҖҒжңҖеҲқгҒҜйҒ•е’Ңж„ҹгӮ’иҰҡгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иүҜгҒ•гҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒЁгҒқгҒ®йӯ…еҠӣгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒӢгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒҜеҫҢиҖ…гҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜеҪјгҒ®гӮўгғүгғӘгғ–иЎЁзҸҫгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйқ©ж–°жҖ§гҖҒжғіеғҸгҒ®иҮӘз”ұгҒ•гҖҒж„ҸиЎЁжҖ§гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЁҖи‘үгҒ§иЎЁгҒ•гӮҢгӮӢеүөйҖ жҖ§гҒ®еӨ©жүҚзҡ„гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪјгҒҜгӮўгғ«гғҲгӮөгғғгӮҜгӮ№гҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гғҗгӮ№гӮҜгғ©гғӘгғҚгғғгғҲгҒЁгҒӢгғ•гғ«гғјгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰжј”еҘҸгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒӘгҒӢгҒ§гӮӮеҪјгҒ®гғ•гғ«гғјгғҲгҒ®жј”еҘҸгҒҜеӨ§еӨүгғӘгғӘгӮ«гғ«гҒ§гҖҒгҒҫгӮӢгҒ§е°ҸйіҘгҒЁеҜҫи©ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе„ӘгҒ—гҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҒҹгҒ гҒІгҒҹгҒҷгӮүгҒ«гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®гғ•гғ«гғјгғҲгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒ«иҖігӮ’еӮҫгҒ‘гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгғ•гғ«гғјгғҲгҒЁгҒ„гҒҶжҘҪеҷЁгҒ§гӮёгғЈгӮәгӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гҒҹжј”еҘҸгҒ§гҒҜгҖҒиЎЁзҸҫеҶ…е®№гҒЁгҒ„гҒ„гҖҒйҹіиүІгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’гҒ—гҒ®гҒҗгӮҲгҒҶгҒӘжј”еҘҸгҒҜз„ЎгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д»Ҡж—ҘгҖҒд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«жң¬еұӢгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгӮүгҖҒзұіеҺҹдёҮзҗҶгҒ®гҖҢж„ӣгҒ®жі•еүҮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒҢзӣ®гҒ«з•ҷгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮзұіеҺҹдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒҜ2006е№ҙ5жңҲгҒ«гҒҢгӮ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҖӮеғ•гҒҢеҪјеҘігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜ2003е№ҙгҒ®1жңҲ11ж—ҘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ«гғЎгғўгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҢгҒјгҒҸгҒҜгҖҒдҪң家гҒ®зұіеҺҹдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶдәәгӮ’гҖҒд»Ҡж—ҘгғҶгғ¬гғ“гӮ’иҰӢгҒҰеҲқгӮҒгҒҰзҹҘгҒЈгҒҹгҖӮдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒ®зҲ¶иҰӘгҒҜж—Ҙжң¬е…ұз”Је…ҡиЎҶиӯ°йҷўиӯ°е“ЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹжҳ¶ж°ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҢеӣҪйҡӣе…ұз”Јдё»зҫ©йҒӢеӢ•гҒ®ж©ҹй–ўзҙҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгҖҢе№іе’ҢгҒЁзӨҫдјҡдё»зҫ©гҒ®и«ёе•ҸйЎҢгҖҚгҒ®з·ЁйӣҶеұҖпјҲгғ—гғ©гғҸпјүгҒ«жҙҫйҒЈгҒ•гӮҢдёҖ家гҒҢгҒқгҒ®ең°гҒ«дҪҸгҒҝгҖҒдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒҜгҒқгҒ“гҒ®гғ—гғ©гғҸгғ»гӮҪгғ“гӮЁгғҲеӯҰж ЎгҒ«е°ҸеӯҰж Ўпј”е№ҙгҒ®гҒЁгҒҚгҒ«и»ўе…ҘгҒ—пј‘пјҷпј•пјҷпҪһпј‘пјҷпј–пј”гҒ®й–“еӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢж—Ҙжң¬гҒ®еӨ§еӯҰгҒ§гғӯгӮ·гӮўж–ҮеӯҰгӮ’е°Ӯж”»гҒ—гҖҒгғӯгӮ·гӮўиӘһгҒ®йҖҡиЁіиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгӮҙгғ«гғҗгғҒгғ§гғ•гҖҒгӮЁгғӘгғ„гӮЈгғігҒӘгҒ©гҒ®йҖҡиЁігӮ’дҪ“йЁ“гҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҹдҪ“йЁ“гӮ’гӮӮгҒЁгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®жң¬гӮ’жӣёгҒҸгҖӮдё»гҒӘгӮӮгҒ®гҒ«гҖҒгҖҢдёҚе®ҹгҒӘзҫҺеҘігҒӢиІһж·‘гҒӘйҶңеҘі(гғ–гӮ№)гҒӢгҖҚж–°жҪ®ж–Үеә«гҖҢеҳҳгҒӨгҒҚгӮўгғјгғӢгғЈгҒ®зңҹгҒЈиөӨгҒӘзңҹе®ҹгҖҚж–ҮиҠёгӮ·гғӘгғјгӮәгҖҢгғӯгӮ·гӮўгҒҜд»Ҡж—ҘгӮӮиҚ’гӮҢжЁЎж§ҳ гҖҚи¬ӣи«ҮзӨҫж–Үеә«гҖҢйӯ”еҘігҒ®пј‘гғҖгғјгӮ№вҖ•жӯЈзҫ©гҒЁеёёиӯҳгҒ«еҶ·гӮ„ж°ҙгӮ’жөҙгҒігҒӣгӮӢпј‘пј“з« гҖҚж–°жҪ®ж–Үеә«гҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гғҶгғ¬гғ“гҒ§гҒҜгҖҒеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒҠжҜҚгҒ•гӮ“гҒ®гӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгӮ’дёүгҒӨи©ұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдёҖгҒӨгҒҜгҖҒе°ҸеӯҰж ЎгҒ«е…ҘеӯҰгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®и©ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз”·гҒҜй»’гҒ®гғ©гғігғүгӮ»гғ«гҖҒеҘігҒҜиөӨгҒ®гғ©гғігғүгӮ»гғ«гҒЁз”»дёҖзҡ„гҒ§гҒҜеҖӢжҖ§гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёҖдәәгҒ гҒ‘иҢ¶иүІгҒ®гғ©гғігғүгӮ»гғ«гӮ’иғҢиІ гҒЈгҒҰе…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдәҢгҒӨзӣ®гҒҜгҖҒ家гҒ§иұҶгҒҫгҒҚгӮ’гҒ•гҒӣгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮзҰҸгҒҜеҶ…гҖҒй¬јгҒҜеӨ–гҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮдёүгҒӨзӣ®гҒҜгҖҒ家гӮ’ж–°зҜүгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ«еЈҒдёӯгҒ«иҗҪжӣёгҒҚгӮ’иЁұгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгӮ’иҰӢгҒҰеҸӢдәәгҒҢеӯҗдҫӣгҒ®иәҫгҒҢгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«еәғгҒ„зҷҪгҒ„еЈҒгӮ’иҰӢгҒҰиҗҪжӣёгҒҚгӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгҒӘгҒ„еӯҗдҫӣгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢдёҚиҮӘ然гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҒгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жң¬дәәгӮӮгғ—гғ©гғҸгғ»гӮҪгғ“гӮЁгғҲеӯҰж ЎгҒ®жҖқгҒ„еҮәгӮ’иӘһгӮӢдёӯгҒ§ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘи©ұгҒҢеҚ°иұЎзҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӯҰж ЎгҒҜдё–з•Ңпј•пјҗгӮ«еӣҪгҒӢгӮүгҒ®еӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдјҡи©ұгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҒҠдә’гҒ„гҒ«иҮӘеҲҶгӮ’дё»ејөгҒ—гҖҒгҒӘгӮӢгҒ№гҒҸзӣёжүӢгҒ®ејұзӮ№гӮ’зӘҒгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ«жҲ»гҒЈгҒҰеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«и©ұгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҸҚеҝңгҒҢиҝ”гҒЈгҒҰгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮпј‘е№ҙгҒҸгӮүгҒ„гҒ—гҒҰгҒҜгҒЈгҒЁж°—гҒҢгҒӨгҒ„гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬дәәгҒЈгҒҰгҒӘгӮ“гҒЁзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҖӮиҮӘеҲҶгҒҢи©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒи©ұгҒ—гҒҹеҫҢгҒ§зӣёжүӢгҒҢгҒ©гҒҶж„ҹгҒҳгӮӢгҒӢгҒҫгҒ§гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгҖӮ
гҒ“гӮ“гҒӘеҪјеҘігҒ®и©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҜгҒ•гҒЈгҒқгҒҸжң¬еұӢгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҖҢеҳҳгҒӨгҒҚгӮўгғјгғӢгғЈгҒ®зңҹгҒЈиөӨгҒӘзңҹе®ҹгҖҚгҒЁгҖҢгғӯгӮ·гӮўгҒҜд»Ҡж—ҘгӮӮиҚ’гӮҢжЁЎж§ҳ гҖҚгӮ’иІ·гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰиӘӯгӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҖӮж–Үз« гӮӮгҒҶгҒҫгҒҸгҖҒи©ұгӮӮж–°й®®гҒ§еӨ§еӨүйқўзҷҪгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжң¬гӮ’иӘӯгҒҝгҒӘгҒҢгӮүгҒјгҒҸгҒҜеҲҘгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬дәәгҒӘгӮүиӘ°гҒ§гӮӮгҖҢе’ҢгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰе°ҠгҒ—гҒЁгҒӘгҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжң¬жқҘгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгҖҒж„ҸиҰӢгҒ®йҒ•гҒҶиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҒҠдә’гҒ„гҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«иӯ°и«–гҒ—гҒҰдёҖиҮҙзӮ№гӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҒӘгҒ•гҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮгҒқгҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжЁ©еЁҒгҒ®гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«еҫ“гҒҶгҖҒеҸҚеҜҫж„ҸиҰӢгҒҜиҒһгҒӢгҒӘгҒ„гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶйўЁгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙжң¬дәәгҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгӮӢгҖӮиҮӘеҲҶгҒ®иҖғгҒҲгӮ’дё»ејөгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒзӣёжүӢгҒ®ж„ҸиҰӢгҒ«иҖігӮ’иІёгҒҷгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢжңӘгҒ гҒ«иӢҰжүӢгҒӘж—Ҙжң¬дәәгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮгғҲгғЁгӮҝиҮӘеӢ•и»ҠгҒЁпјӘпјІжқұжө·гҖҒдёӯйғЁйӣ»еҠӣгҒ®пј“зӨҫгҒ§дёӯеӯҰгғ»й«ҳж ЎгҒ®дёҖиІ«гҒ—гҒҹеӯҰж ЎгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢгҒЁе ұйҒ“гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒзҹҘиӯҳгӮ’гҒ©гӮҢгҒ гҒ‘и©°гӮҒгҒҹгҒӢгҒ§и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘеҲҶгҒЁд»–дәәгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгӮӢгҖҒиҮӘз«ӢгҒ—гҒҹдәәж јеҪўжҲҗгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҹж•ҷиӮІгҒ«жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҒЈгҒЁзұіеҺҹдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒ®дҪңе“ҒгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҚ
гҒЁиЁҖгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘзү©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдҪ•гҒӢж”Ҝйӣўж»…иЈӮгҒӘзөҗи«–гӮ’е°ҺгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒ•гҒҰгҒҠгҒҚгҖҒзұіеҺҹдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒ®иӨҮзңјзҡ„иҰ–зӮ№гҒ§гҖҒжҸҸгҒҚеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгӮӨгғӯгғігғҠеҮәжқҘдәӢгҒҜжң¬еҪ“гҒ«ж–°й®®гҒ§гҖҒеғ•гҒҜгҒҷгҒЈгҒӢгӮҠеҪјеҘігҒ®гғ•гӮЎгғігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгӮҸгҒҡгҒӢ3е№ҙеҫҢгҒ«дәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰеӨ§еӨүж®ӢеҝөгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒд»Ҡе№ҙж–°гҒҹгҒ«гҖҒжңҖеҲқгҒ§жңҖеҫҢгҒ®и¬ӣжј”йҢІйӣҶгҒҢеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӢҝи«–иіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ

иҠұгҒ®йҰҷгӮӢжңЁгӮ’пј“гҒӨжҢҷгҒ’гӮӢгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒжҳҘгҒ®жІҲдёҒиҠұгҖҒеҲқеӨҸгҒ®гҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҖҒз§ӢгҒ®йҮ‘жңЁзҠҖгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮеҲқеӨҸгҒ®гҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒҜгҖҒзү№еҲҘгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жў…йӣЁгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰй•·йӣЁгҒҢз¶ҡгҒҚгҖҒеӨңгҖҒиӘӯжӣёгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒӨгҒ—гҒӢйӣЁйҹігҒҢжӯўгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮж°—еҲҶи»ўжҸӣгҒ«жҡ—й—ҮгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеәӯгҒ«еҮәгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒйўЁгҒ®гҒӘгҒ„гғ гғігғ гғігҒЁгҒ—гҒҹз©әж°—гҒ®дёӯгҒ«гҖҒгҒ»гҒ®гҒӢгҒӘйҰҷгӮҠгҒҢеҢӮгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®иҠұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҢгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®иҠұгӮ’ж„ҸиӯҳгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶзҠ¶жіҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒжңҖеҲқгҒ«гҒ“гҒ®дәӢгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҹжҷӮгҒ«гҖҒиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹжң¬гҒҢгғ¬гӮӨгғўгғігғүпҪҘгӮ«гғјгғҙгӮЎгғјгҒ®и©©йӣҶгҖҒй»’з”°зөөзҫҺеӯҗиЁігҖҢж°ҙгҒ®еҮәдјҡгҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҖҚи«–еүөзӨҫгҖҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҢйӣЁгҖҚгғ»д»Ҡжңқзӣ®гҒҢгҒ•гӮҒгҒҹжҷӮгҖҒз„ЎжҖ§гҒ«гҒ“гҒ®гҒҫгҒҫдёҖж—ҘдёӯгғҷгғғгғүгҒ®дёӯгҒ«гҒ„гҒҰгғ»жң¬гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгғ»гҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒқгҒ®иЎқеӢ•гҒЁй—ҳгҒЈгҒҹгҖӮгғ»гҒқгӮҢгҒӢгӮүзӘ“гҒ®еӨ–гҒ®йӣЁгӮ’иҰӢгҒҹгҖӮгғ»гҒқгҒ—гҒҰгҖҒйҷҚеҸӮгҒ—гҒҹгҖӮгғ»гҒ“гҒ®йӣЁгҒ®жңқгҒ«гҒҷгҒЈгҒӢгӮҠиә«гӮ’д»»гҒӣгӮҲгҒҶгҖӮгғ»гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҒ“гҒ®дәәз”ҹгӮ’гҒҫгҒҹгӮӮгҒҶдёҖеәҰз”ҹгҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгғ»гҒҫгҒҹеҗҢгҒҳиЁұгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„йҒҺгҒЎгӮ’зҠҜгҒҷгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгғ»гҒҶгӮ“гҖҒзўәзҺҮгҒҜеҚҠеҲҶгҒ гҖӮгҒҶгӮ“гҖӮ
гҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®зҷҪгҒ„иҠұгҒҢгҖҒгғ¬гӮӨгғўгғігғүгғ»гӮ«гғјгғҙгӮЎгғјгҒ®и©©гҒ«йҰҷгӮҠгӮ’ж·»гҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгӮӮгҖҒгғ¬гӮӨгғўгғігғүгғ»гӮ«гғјгғҙгӮЎгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮ„гҒ•гҒ—гҒ„ж–ҮдҪ“гҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®ж„ҹжғ…гӮ’и©©гҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒјгҒҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®йҰҷгӮҠгҒҜжҠ’жғ…и©©гҒ®еҢӮгҒ„гҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҜгҖҒгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®жңЁгӮ’еәӯгҒ«гҒ„гҒЈгҒұгҒ„жӨҚгҒҲгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ«гҒҜгҖҒдёҖйҮҚгҒ®иҠұгҖҒе…«йҮҚгҒ®иҠұгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒқгӮҢгҒ®еӨ§ијӘгҒЁгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮиҠұгҒ®иү¶гӮ„гҒӢгҒӘгҒ®гҒҜе…«йҮҚгҒ®еӨ§ијӘгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҰҷгӮҠгҒҢеј·гҒҸе®ҹгӮ’зөҗгҒ¶гҒ®гҒҜдёҖйҮҚгҒ®иҠұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҢҝгҒ—жңЁгҒ§еў—гӮ„гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒз”әгҒ®дёӯгӮ’гҒӮгҒЎгҒ“гҒЎжӯ©гҒҚгҖҒжҢҝгҒ—жңЁгҒ«йҒ©гҒ—гҒҹжһқгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒҫгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮгҒӮгӮҢгҒӢгӮүпј—е№ҙзөҢгҒЈгҒҹд»ҠгҖҒеәӯгҒ«пј•жң¬гҒ®гҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®жңЁгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҖҒзҷҪгҒ„иҠұгӮ’еҢӮгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҠұгӮ’ж‘ҳгӮ“гҒ§ж°ҙгҒ«жө®гҒӢгҒ№гҖҒйғЁеұӢгҒ§гӮӮеҢӮгҒ„гӮ’жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒ®и©©гӮӮгҒӮгӮҢгҒӢгӮүе°‘гҒ—гҒҜеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҢгҒӮгӮҒгҖҚгғ»жў…йӣЁгҒ«е…ҘгӮҠгғ»жҜҺж—ҘйӣЁгҒҢйҷҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғ»гӮҸгҒҹгҒ—гҒ®еҝғгӮӮгғ»ж¶ҷгҒ§жҝЎгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғ»гҖҖ йӣЁгҒ«жҝЎгӮҢгҒҹгғ»зҙ«йҷҪиҠұгҒ§гҒҜгғ»йӣЁиӣҷгҒҢгғ»йіҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгғ»гҖҖзҗҶз”ұгӮӮгҒӘгҒҸгғ»ж¶ҷгӮ’жөҒгҒ—гғ»иғёгӮ’гҒ—гӮҒгҒӨгҒ‘гӮӢгғ»гӮҸгҒҹгҒ—гҒ®еҝғгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»пјҲз”ҹйҮҺгҖҖжҒӯпјү
й»’дәәеҘіжҖ§гҒ®гғ“гғӘгғјгғ»гғӣгғӘгғҮгӮӨгҒҜпј‘пјҷпј”пјҗе№ҙгҒӢгӮүпј•пјҗе№ҙд»ЈгҒ«зҸҫгӮҢгҒҹеӨ©жүҚгӮёгғЈгӮәпҪҘгӮ·гғігӮ¬гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјеҘігҒҢгӮ№гғҶгғјгӮёгҒ§жӯҢгҒҶжҷӮгҒ«гҒ„гҒӨгӮӮй«ӘгҒ«жҢҝгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®иҠұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ¬гғҮгӮЈгғ»гғҮгӮӨгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҒқгҒ®дәәз”ҹгҒҜиҫӣй…ёгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҪјеҘігҒ®жӯҢгҒҜгҖҒгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®иҠұгҒ®йҰҷгӮҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒ®еҝғгҒ«жҹ“гҒҝе…ҘгҒЈгҒҰйҹҝгҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иӘӯжӣёгҒ§з–ІгӮҢгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒгҒјгҒҸгӮӮгӮёгғЈгӮәгҒ®LPгӮ„пјЈпјӨгӮ’иҒһгҒҸгҖӮеӨ§жҠөгҒҜйҹігҒ®иүҜгҒ„йҢІйҹігҒ®гғ”гӮўгғҺгғҲгғӘгӮӘгҒҢдёӯеҝғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҷгғјгӮ№гҒ®гҒҶгҒӯгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдҪҺйҹігҒ®дёӯгҒ§гҖҒгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгғ”гӮўгғҺгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ§гӮӮжҷӮгҒ«гҒҜз„ЎжҖ§гҒ«гғ“гғӘгғјгҒ®гӮёгғЈгӮәгғңгғјгӮ«гғ«гҒҢиҒһгҒҚгҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒҶгҒЈгҒҹгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғҗгғ©гғјгғүгҒ«иә«гӮ’еҜ„гҒӣгҒҰгҖҒгҒҸгҒЎгҒӘгҒ—гҒ®й«ӘйЈҫгӮҠгҒ®дјјеҗҲгҒҶгҖҒеҘіжҖ§гӮ’жҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖӮ

гҖҢгҒ•гӮҲгҒӘгӮүгғҗгғјгғүгғ©гғігғүгҖҚ
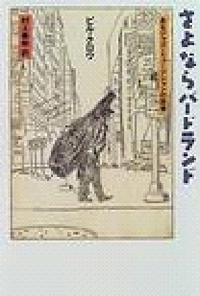
гӮёгғЈгӮәгғ»гғһгғігҒ®иҮӘдјқгӮ’жӣёгҒ„гҒҹжң¬гҒ§гҒҜгҖҒгғһгӮӨгғ«гӮ№гғ»гғҮгӮӨгғ“гӮ№гҒЁгҒӢгӮўгғјгғҲгғ»гғҡгғғгғ‘гғјгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢжң¬ж јзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғ“гғ«гғ»гӮҜгғӯгӮҰгҒ®жӣёгҒ„гҒҹгҖҢгҒ•гӮҲгҒӘгӮүгғҗгғјгғүгғ©гғігғүгҖҚгҒҜеғ•гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзү№еҲҘгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҷгғјгӮ·гӮ№гғҲгҒ®гғ“гғ«гғ»гӮҜгғӯгӮҰгҒ®пј•пјҗе№ҙд»ЈгҒӢгӮүпј–пјҗе№ҙд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®иҮӘдјқзҡ„дәӨйҒҠйҢІгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жң¬гҒ«гҒҜгӮёгғЈгӮәгӮ’жј”еҘҸгҒҷгӮӢе–ңгҒігҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢжәўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ«гҒҜгғ‘гғјгӮ«гғјгҖҒгӮЁгғӘгғігғҲгғігҖҒгғһгӮӨгғ«гӮ№гҖҒгӮІгғғгғ„гҖҒгғһгғӘгӮ¬гғігҖҒгӮәгғјгғҲзӯүгҒ®гғ—гғ¬гӮӨгғӨгғјгҒ®гӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгҒӢгӮүиҫӣеҸЈгҒ®жү№и©•гҒҫгҒ§гҒҢгҖҒеҪјгҒ®дҪ“йЁ“гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«иӘһгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰеӨ§еӨүгҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„гҖӮгҒӘгҒӢгҒ§гӮӮгӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮәгҒ®пј»жҘҪеҷЁдёҖгҒӨгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®дё–гҒҜжҘөжҘҪгҒ гҒЈгҒҹгҖӮпјҪгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒжӯ»гҒ®пј’ж—ҘеүҚгҒҫгҒ§гғҶгғҠгғјгӮ’ж”ҫгҒ•гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдёҖз”ҹгҒ«гҒҜиғёжү“гҒҹгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮиЁіиҖ…гҒҜжқ‘дёҠжҳҘжЁ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®жң¬гҒЁеҮәдјҡгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜпјҷпј–е№ҙгҒ®пј‘пјҗжңҲгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ«еғ•гҒҜзө¶дёҚиӘҝгҒ®жҷӮгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жң¬гҒ®дё–з•ҢгҒ«жөёгҒЈгҒҰгҒҡгҒ„гҒ¶гӮ“гҒЁж•‘гӮҸгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’пјҷпјҗпјҗеҶҶгҒ§гӮӮе®үгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгҒҜж–°жҪ®ж–Үеә«гҒ§пјҳпј•пј—еҶҶгҒ§иІ·гҒҲгӮӢгҖӮеҪјгҒҜгҒ“гҒ®жң¬гҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гҖҒгӮёгғЈгӮәгғ»гӮўгғҚгӮҜгғүгғјгғ„гҒЁгҒ„гҒҶжң¬гӮӮжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮжқ‘дёҠжҳҘжЁ№гҒҢзҝ»иЁігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҢжҳјеҜқгҒ®гҒҷгҒҷгӮҒгҖҚ
гҒ“гҒ®жң¬гҒҜгҖҒжқұдә¬еҢ»з§‘жӯҜ科еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҒ®дә•дёҠжҳҢж¬ЎйғҺе…Ҳз”ҹгҒ®жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгҖҒгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒҜе„ӘгҒ—гҒ„гҒҢдёӯиә«гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢж·ұгҒ„дёҖеҶҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…Ҳз”ҹгҒҜгҖҒзқЎзң 科еӯҰгӮ’е°Ӯж”»гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®й ҳеҹҹгҒӘгӮүгғ©гӮӨгғҗгғ«гҒ®гҒ„гҒӘгҒ„жңӘзҹҘгҒ®еҺҹйҮҺгӮ’жҺўжӨңгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ гҖҒгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҲҶйҮҺгҒ®гӮ№гғҡгӮ·гғЈгғӘгӮ№гғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»зң гӮҠгҒ«гҒҜгғ¬гғ зқЎзң гҒЁгҖҒгғҺгғігғ¬гғ зқЎзң гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғ¬гғ зқЎзң гҒҜи„ігӮ’жҙ»жҖ§еҢ–гҒ•гҒӣгҖҒгғҺгғігғ¬гғ зқЎзң гҒҜи„ігӮ’дј‘йӨҠгҒ•гҒӣгӮӢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»гғ¬гғ зқЎзң гҒҢпј“пјҗеҲҶеүҚеҫҢгҖҒгғҺгғігғ¬гғ зқЎзң гҒҢпј–пјҗеҲҶеүҚеҫҢгҒ®пјҷпјҗеҲҶгҒҢзқЎзң гҒ®дёҖгҒӨгҒ®гӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гғ»гғ¬гғ зқЎзң гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§зӣ®гӮ’иҰҡгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒзӣ®иҰҡгӮҒгҒҢиүҜгҒ„гҖӮ
гғ»гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰжҳјеҜқгҒҜпј‘пј•еҲҶзЁӢеәҰгҒӢгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜпјҷпјҗеҲҶд»ҘдёҠгҒҢиүҜгҒ„гҖӮдёӯйҖ”еҚҠз«ҜгҒ§гҒҜзӣ®иҰҡгӮҒгҒҢжӮӘгҒҸгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰйҖҶеҠ№жһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®гҒ»гҒӢзқЎзң дёҚи¶ігҒҜзҙҜз©ҚгҒҷгӮӢгҒҢеҜқгҒ гӮҒгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒӢгҖҒгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒҜзқЎзң жҷӮй–“гӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒЁгҒӢгҖҒзң гӮҠгҒҜйўЁйӮӘгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ«дҫөгҒ•гӮҢгҒҹдҪ“гӮ’жІ»зҷӮгҒ«йӣҶдёӯгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒе·ҰеҸігҒ®и„ігӮ’дәӨдә’гҒ«зң гӮүгҒӣгӮӢгӮӨгғ«гӮ«гӮ„жёЎгӮҠйіҘгҒҢгҒ„гӮӢгҖӮзӯүзқЎзң гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®зҹҘиӯҳгҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„и©°гҒҫгҒЈгҒҹжң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒЁгҒӢгҒҸгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒ®еӨҡгҒ„гҖҒдјҡзӨҫз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғ©гғӘгғјгғһгғіи«ёж°ҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹзҹҘиӯҳгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒз–ІеҠҙгӮ’еӣһеҫ©гҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒ«еҪ№гҒ«з«ӢгҒӨгҒЁжҖқгҒҶгҖӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘеҶ…е®№гӮ’гҖҒж–°жӣёжң¬гҒ«гҒ—гҒҹгҖҢзқЎзң гҒ®жҠҖиЎ“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒҢгғҜгғӢгҒ®NEWж–°жӣёгҒ§еҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е…ҲжңҲгҒ®28ж—ҘгҒ«иҰӘжҲҡгҒ®жі•дәӢгҒ«гҒ„гҒЈгҒҹжҷӮгҖҒеұ…еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹеҫ“е…„ејҹгҒҢгҖҒз§ҒгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘеҘҪгҒҚгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ家гҒ«еҸӨгҒ„йӣ»и“„гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйӮӘйӯ”гҒ гҒӢгӮүеҮҰеҲҶгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮӮгҒ—иүҜгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҖҒжҢҒгҒЈгҒҰиЎҢгҒҸгҒӢгҒ„гҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶи©ұгҒҜж»…еӨҡгҒ«ж–ӯгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ”гҒҝгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮиІ°гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮпјҲгҒқгӮҢгҒ§еҫҢгҒ§иӢҰеҠҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢпјүж•°ж—ҘеҫҢгҖҒ家гҒ®дҝ®зҗҶгӮ’й јгӮ“гҒ гҒӨгҒ„гҒ§гҒ«гҖҒеҫ“е…„ејҹгҒҢйӣ»и“„гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҒ„гҒӨгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®йӣ»и“„гҒӢгҒҜгҖҒгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гғ“гӮҜгӮҝгғјиЈҪгҒ®гҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸ30~40е№ҙгҒҸгӮүгҒ„еүҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮд»•ж§ҳгҒҜгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒAMж”ҫйҖҒгҒ®еҸ—дҝЎж©ҹгҒҢ2еҸ°д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒNHKгҒ®з¬¬1гҒЁз¬¬2ж”ҫйҖҒгҒ§гӮ№гғҶгғ¬гӮӘж”ҫйҖҒгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеҗҚж®ӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгғ‘гғҜгғјйғЁгҒҜзңҹз©әз®Ў6BMпјҳгӮ’4жң¬з”ЁгҒ„гҒҹгғ—гғғгӮ·гғҘгғ»гғ—гғ«гғ»гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮўгғігғ—гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдҪҝз”ЁеҸҜиғҪгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒзңҹз©әз®ЎгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮеҹғгҒҫгҒҝгӮҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰеҲҶи§ЈгҒ—гҒҰгҖҒеүҘгҒҢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹиЈңеј·жқҝгӮ’жҺҘзқҖгҒ—гҒӘгҒҠгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгғӘгғ•гӮЎгӮӨгғігҒ—гҒҹгҖӮ
гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜ2WayгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгӮўгғ«гғӢгӮізЈҒзҹігҒҢдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®йҹігҒҜгҖҒеӨ§еӨүзҙ зӣҙгҒ§гҖҒгҒҷгҒҢгҒҷгҒҢгҒ—гҒҸгҖҒйҹҝгҒҚгҒ®иүҜгҒ„йҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲз®ұгӮ’йіҙгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ пјүзңҹз©әз®ЎгӮўгғігғ—гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒLPгҒ§гғҗгғӯгғғгӮҜйҹіжҘҪгҒЁгҒӢе®ӨеҶ…жҘҪгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁжңҖй«ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еүҚзҪ®гҒҚгҒҢй•·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁігҒ§гҖҒгҒҫгҒҹдёӯеҸӨгҒ®LPгӮ’иІ·гҒ„гҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§е…ҘжүӢгҒ—гҒҹLPгҒ®дёӯгҒ«гҖҒйҹіжҘҪгҒЁгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒз§ҒгҒ®жғіеғҸеҠӣгӮ’гҒӢгҒҚгҒҹгҒҰгҒҹLPгҒҢ4жһҡгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гғ»гғҳгғігғҮгғ«пјҡеҗҲеҘҸеҚ”еҘҸжӣІйӣҶпјҸгӮ«гғјгғ«гғ»гӮ·гғҘгғјгғӘгғ’гғҲгҖҒгғҗгӮӨгӮЁгғ«гғіж”ҫпјҲгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«пјү
гғ»гғҳгғігғҮгғ«пјҡж°ҙдёҠгҒ®йҹіжҘҪпјҸгғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғ–гғјгғ¬гғјгӮәгҖҒгғҸгғјгӮ°гғ»гғ•гӮЈгғ«пјҲгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«пјү
гҒ“гҒ®2жһҡгҒҢжҳӯе’Ң45е№ҙ4жңҲгҒ«WгҒ•гӮ“гӮҲгӮҠTSгҒ•гӮ“гҖҒTYгҒ•гӮ“еҫЎеӨ«еҰ»гҒ®зөҗе©ҡзҘқгҒ„гҒ«иҙҲгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»гғҸгғігӮ¬гғӘгғјз”°ең’е№»жғіжӣІпјҸгғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғ©гғігғ‘гғ«пјҲгғ•гӮЈгғӘгғғгғ—гӮ№пјү
гҒ“гӮҢгҒҜеҗҢгҒҳе№ҙгҒ®8жңҲгҒ«гҖҒTSгҒ•гӮ“гҒҢеҘҘгҒ•гӮ“гҒ®TYгҒ•гӮ“гҒ®24жӯігҒ®иӘ•з”ҹж—ҘгҒ«гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»гғҙгӮЈгғҗгғ«гғҮгӮЈпјҡгғ•гғ«гғјгғҲеҚ”еҘҸжӣІгҖҢжө·гҒ®еөҗгҖҚпјҸгӮӨгғ»гғ гӮёгғҒеҗҲеҘҸеӣЈпјҲгғ•гӮЈгғӘгғғгғ—гӮ№пјү
гҒ“гӮҢгҒҜ46е№ҙгҒ®8жңҲгҒ«гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠTSгҒ•гӮ“гҒҢеҘҘгҒ•гӮ“гҒ®TYгҒ•гӮ“гҒ®25жӯігҒ®иӘ•з”ҹж—ҘгҒ«гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгҒ“гҒ®е№ҙгҒ«гҒҠеӯҗж§ҳгӮӮз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢпјү
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“з§ҒгҒҜгҖҒWгҒ•гӮ“гӮӮTSгҒ•гӮ“гӮӮTYгҒ•гӮ“гӮӮзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁи©®зҙўгҒҷгӮӢгҒӨгӮӮгӮҠгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҘҘгҒ•гӮ“гҒ®TYгҒ•гӮ“гҒҢз§ҒгҒЁеҗҢгҒҳе№ҙеӣһгӮҠгҒӘгҒ®гҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§иҮӘеҲҶгҒ гҒЈгҒҹгӮүгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖҒгҒӘгҒ©гҒЁжғіеғҸгҒ—гҒӘгҒҢгӮүе°‘гҒ—иҖғгҒҲгҒҹгҖӮWгҒ•гӮ“гҒҜгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гғ»гӮҪгӮөгӮЁгғҶгӮЈгҒ®дјҡе“ЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®WгҒ•гӮ“гҒҜзөҗе©ҡзҘқгҒ„гҒ«гғҳгғігғҮгғ«гӮ’иҙҲгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгҒ гҒЈгҒҹгӮүгӮҸгҒҹгҒ—гӮӮгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®е№ҙд»ЈгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІгҒ«гҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҘҘгҒ•гӮ“гҒҜгғ•гғ«гғјгғҲгҒ®йҹіиүІгҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгӮ“гҒ гҖӮзӣӨйқўгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒ4жһҡгҒЁгӮӮгӮҲгҒҸиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з—ӣгӮ“гҒ§гҒ„гҒӘгҒ„гҖҒеӨ§еҲҮгҒ«дҝқз®ЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№гҒ«гӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ®LPгҒҜгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒ®з—ӣгӮ“гҒ гҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒз¶әйә—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиӘ•з”ҹж—ҘгҒ”гҒЁгҒ«LPгғ¬гӮігғјгғүгӮ’гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒҷгӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгҖҒеҪ“жҷӮгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ§еӨүгҒҠгҒ—гӮғгӮҢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«жқҘгҒҰLPгӮ’еҘҘгҒ•гӮ“гҒҜжүӢж”ҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮиүІгҖ…гҒЁжғіеғҸгӮ’гҒӢгҒҚз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ
гғҳгғігғҮгғ«гҒ®ж°ҙдёҠгҒ®йҹіжҘҪгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮҲгӮҠе…ёйӣ…гҒ«жөҒгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғҗгғғгғҸгҒҜз„ЎдјҙеҘҸгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғіжӣІгӮ’6жӣІжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮз„ЎдјҙеҘҸгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігӮҪгғҠгӮҝ3жӣІгҒЁз„ЎдјҙеҘҸгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігғ‘гғ«гғҶгӮЈгғјгӮҝ3жӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮжңүеҗҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒ第5жҘҪз« гҒ«гӮ·гғЈгӮігғігғҢгӮ’еҗ«гӮҖгғ‘гғ«гғҶгӮЈгғјгӮҝ第2з•ӘгғӢзҹӯиӘҝгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гӮ·гғЈгӮігғігғҢгҒҜгҖҢиҚҳйҮҚгҒӘдё»йЎҢгҒҢжҸҗзӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢ30еӣһеӨүеҘҸгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгӮ·гғЈгӮігғігғҢгҒЁгҒҜеӨүеҘҸгӮ’зҜүгҒҚдёҠгҒ’гӮӢеҸӨгҒ„иҲһжӣІеҪўејҸгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨүеҘҸгҒӢгӮүеӨүеҘҸгҒёгҒЁж°—еҲҶзҡ„гҒ«з·ҠејөгҒ®й«ҳжҪ®гҒ—гҒҰгӮҶгҒҸеҠӣеј·гҒ•гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚпјҲеҗҚжӣІгҒ®жЎҲеҶ…пјҲдёӯпјүгҖҒйҹіжҘҪгҒ®еҸӢзӨҫгҖҒSпј“пјҷе№ҙпјүгҒЁгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒјгҒҸгҒҢгҖҒгғҗгғғгғҸгҒ®з„ЎдјҙеҘҸгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғіжӣІгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮж„ҹеӢ•гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҒ»гӮ“гҒ®ж•°е№ҙеүҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҫ“жқҘгҒ®CDдёӯеҝғгҒӢгӮүгҖҒйҹігҒ®иүҜгҒ•гӮ’еҶҚиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰLPгғ¬гӮігғјгғүгӮ’гӮӮгҒҶдёҖеәҰйӣҶгӮҒгҒ гҒ—гҒҹй ғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҜгғ©гғғгӮ·гӮҜгҒ®LPгҒӘгӮүдҪ•гҒ§гӮӮгӮҲгҒ„гҒЁгҖҒеҸӢдәәгҒ«й јгӮ“гҒ§30жһҡгҖҒ50жһҡгҒЁзәҸгӮҒиІ·гҒ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮгҒ«гҖҒиӢҘгҒ„еҘіжҖ§гҒҢиЎЁзҙҷгҒ«жҳ гҒЈгҒҹгғҸгғігӮ°гғ«ж–Үеӯ—гҒ§и§ЈиӘ¬гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹгҖҒйҹ“еӣҪиЈҪгҒ®LPгҒҢ1жһҡгҒҜгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢиӢұеӣҪDECCAйҢІйҹігҖҒгғҒгғ§гғігғ»гӮӯгғ§гғігғ•гӮЎжј”еҘҸгҒ®гҖҢз„ЎдјҙеҘҸгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ‘гғ«гғҶгӮЈгғјгӮҝ第2з•Әгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第3з•ӘгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжңҖеҲқгҒ«гҒ“гҒ®LPгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒеҪјеҘігҒ®гҒҝгҒҡгҒҝгҒҡгҒ—гҒ„жғ…ж„ҹгҒӮгҒөгӮҢгҒҹгҖҒзҫҺйҹігҒ§еҘҸгҒ§гӮӢгҖҒиӢҘгҒ„жғ…зҶұгҒ«жәўгӮҢгҒҹжј”еҘҸгҒ«жҖқгӮҸгҒҡеј•гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒе…ЁжӣІгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰ3еӣһгӮӮиҒһгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹзЁӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҒ¶з„¶жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгҒ“гҒ®LPгҒҜгҖҒд»ҠгҒ§гҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒ®гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒӘLPгҒ®1жһҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е…Ҳж—ҘSUNVALLEY AUDIOгҒ®еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҖҒгҒқгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒ„гҒҰгӮўгӮӯгӮ·гӮӘгғ гҒҢйіҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҒЁгҖҒйҒҺеӨ§гҒӘжҜ”е–©гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҖҒгғ“гӮҜгӮҝгғјгҒ®гғ¬гғҲгғӯгғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸеҜӣгҒ„гҒ зҙ зӣҙгҒӘиүҜгҒ„йҹігӮ’иҒһгҒӢгҒӣгӮӢгҖӮгғҙгӮ©гғјгӮ«гғ«гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ејҰжҘҪеҷЁгҒ®йҹігҒҜгҒЁгҒҰгӮӮиү¶гӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»Ҡж—ҘгӮӮжңқгҒӢгӮүгҖҒгғҗгғғгғҸгҒ®з„ЎдјҙеҘҸгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғіжӣІгӮ’иҒһгҒ“гҒҶгҒЁгҖҒжүӢжҢҒгҒЎгҒ®CDгҖҒLPгӮ’гҒІгҒЈгҒұгӮҠеҮәгҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
еҮәгҒҰгҒҚгҒҹйҹіжәҗгҒҜгҖҒLPгҒ§гҒҜгҖҒгғҒгғ§гғігғ»гӮӯгғ§гғігғ•гӮЎпјҲ1974е№ҙпјүгҖҒгғЁгғјгӮјгғ•гғ»гӮ·гӮІгғғгғҶгӮЈпјҲ1973е№ҙпјүгҖҒгғЁгғјгӮјгғ•гғ»гӮ№гғјгӮҜпјҲ1971е№ҙпјүгҖҒгғҳгғігғӘгӮҜгғ»гӮ·гӮ§гғӘгғігӮ°пјҲ1967е№ҙпјүгҒ®4жһҡгҖӮCDгҒ§гҒҜгҖҒгғҠгӮҝгғігғ»гғҹгғ«гӮ·гғҶгӮЈгғіпјҲ1956е№ҙгҖҒ1975е№ҙгҖҒ1986е№ҙпјүгҖҒгӮ®гғүгғігғ»гӮҜгғ¬гғЎгғјгғ«пјҲ1975е№ҙгҖҒ1980е№ҙпјүгҖҒгғ•гӮ§гғӘгғғгӮҜгӮ№гғ»гӮўгғјгғЁпјҲ1974е№ҙпјүгҖҒгғ’гғ©гғӘгғјгғ»гғҸгғјгғіпјҲ1997е№ҙпјүгҒ®7жһҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮӨгӮӘгғӘгғіеҘҸиҖ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҒ„гҒӨгҒӢгҒҜжј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„еҗҚжӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®жј”еҘҸгӮӮеӨ§еӨүгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгӮӯгғ§гғігғ•гӮЎгҒЁгӮ·гӮІгғғгғҶгӮЈгҒ®дёЎжҘөз«ҜгҒ®жј”еҘҸгҒЁгҖҒдёӯеәёгҒ®75е№ҙгғҹгғ«гӮ·гғҶгӮЈгғігҒ®жј”еҘҸгҒӢгҖӮгӮҜгғ¬гғЎгғјгғ«гҒ®еҮӣгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҙ°йғЁгҒҫгҒ§иҰӢйҖҡгҒ—гҒ®иүҜгҒ„жј”еҘҸгӮӮеҘҪгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҒ—гҖҒгӮ·гӮ§гғӘгғігӮ°гҒ®жё…жҫ„гҒӘжј”еҘҸгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒ—гғ»гғ»гғ»гҒ“гҒ®жӣІгҒҜгҖҒгӮӯгғ§гғігғ•гӮЎгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’зү№еҲҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҡҶиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒ жҖӘзү©гғҸгӮӨгғ•гӮ§гғғгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгғ‘гғјгғ«гғһгғігӮӮгҒҫгҒ гҒ гҖӮгҒ“гҒ®д»¶гҒ§гӮӮгҒҫгҒ гҒҫгҒ жҘҪгҒ—гӮҒгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҲгғЁгӮҝиҮӘеӢ•и»ҠгҒ®еұұжң¬еүҜзӨҫй•·пјҲ1999е№ҙеҪ“жҷӮпјүгҒҢгғӣгӮӨгғғгғҲгғһгғігҒ®гҖҢгғ–гғӯгғјгғүгӮҰгӮ§гғјгҒ®жҷҜиҰігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи©©гӮ’дёӯж—Ҙж–°иҒһгҒ®гҖҢзҙҷгҒӨгҒ¶гҒҰгҖҚгҒ«зҙ№д»ӢгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖиҘҝж–№гҒ®жө·гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰжӯӨж–№гҒёж—Ҙжң¬гҒӢгӮүжёЎзұігҒ—гҒҹгҖҒ
гҖҖи¬ҷиӯІгҒ«гҒ—гҒҰиүІжө…й»’гҒҸдёЎеҲҖгӮ’гҒ•гҒ—гҒҹдҪҝзҜҖйҒ”гҒҜгҖҒ
гҖҖз„ЎеёҪгҒ«гҒ—гҒҰиҮҶгҒӣгҒҡгҖҒз„Ўи“ӢгҒ®еӣӣијӘйҰ¬и»ҠгҒ«еҸҚгӮҠгҒӢгҒҲгӮҠгҖҒ
гҖҖд»Ҡж—ҘгғһгғігғҸгғғгӮҝгғігӮ’з·ҙгҒЈгҒҰиЎҢгҒҸгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»
гҖҖзҷҫдёҮгҒ®гғһгғігғҸгғғгӮҝгғідәәгҒҢгҒқгҒ®иҲ—йҒ“гҒ«йЈӣгҒіеҮәгҒ—гҒҹгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»
гҖҖгҒ“гҒ®жҷҜиҰігҒ®еҲ—гҒ«дәӨгҒҳгӮҠгҒҰз§ҒгӮӮгҒҫгҒҹжҸҡиЁҖгҒҷгӮӢгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»
гҖҖеҪјзӯүгҒҜиӮҜе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҪјзӯүгҒҜжҲҗе°ұгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҖпјҲгғӣгӮӨгғғгғҲгғһгғіи©©йӣҶгҖҖејҘз”ҹжӣёжҲҝгҖҖзҷҪйіҘзңҒеҗҫиЁіпјү
гҒ“гӮҢгҒҜ幕жң«гҒ®йҒЈзұідҪҝзҜҖеӣЈгҒҢзҶұзғҲгҒӘжӯ“иҝҺгӮ’гҖҒгҒӢгҒ®ең°гҒ§еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’жӯҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮ’жҖқгҒҶгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘж„ҹеӢ•гӮ’иҰҡгҒҲгӮӢгҒЁиӘһгҒЈгҒҰгҒҝгҒҲгӮӢгҖӮ
гҒ•гӮҠж°—гҒӘгҒ„дёҖж–ҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғӣгӮӨгғғгғҲгғһгғігҒ®и©©гҒ®дёӯгӮҲгӮҠгҒ“гӮҢгӮ’жҺўгҒ—еҮәгҒ—гҖҒйҒЈзұідҪҝзҜҖеӣЈгӮ’жҖқгҒ„гӮ„гӮҠгҖҒд»ҠгҒ®ж—Ҙзұій–ўдҝӮгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгӮ’жҖқгҒ„гҖҒгҒқгҒ—гҒҰж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢжғіеғҸеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҖӮгҒқгҒ“гҒ«ж·ұгҒ„зҹҘиӯҳгҒЁгҖҒиұҠгҒӢгҒӘдәәз”ҹзөҢйЁ“гӮ’ж„ҹгҒҳеҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
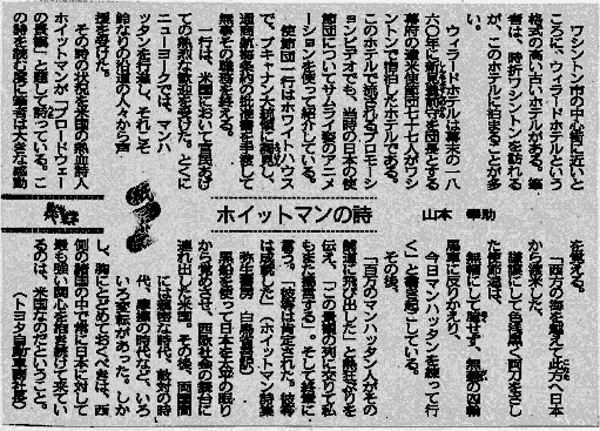


з§ҒгҒ®еӢӨгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹдјҡзӨҫгҒ«гҖҒи»ҠгҒ®гӮ«гғ©гғјгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгғҲгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгҒ®гҒһгҒҝгҒ•гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶгғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒҢгҒ„гҒҹгҖӮеҪјеҘігҒҜеҪ“жҷӮгҖҒиүІгҒ®жөҒиЎҢгҒ«дёҖз•ӘеҪұйҹҝеҠӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғігҒ®еӢ•еҗ‘гӮ’дё№еҝөгҒ«иӘҝгҒ№гҖҒи»ҠгҒ®гӮ«гғ©гғјиЁӯе®ҡгҒ«еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒ„гҒӨгҒӢи»ҠгҒӢгӮүгӮ«гғ©гғјгҒ®жөҒиЎҢгӮ’зҷәдҝЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеӨўгҒ гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘеҪјеҘігҒЁеғ•гҒҢжҷӮгҖ…и©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгғ“гғғгӮ°гғ»гғҗгғігғүгҒ®гӮёгғЈгӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеғ•гҒҜеӨ©жүҚгӮ®гӮҝгғӘгӮ№гғҲгҖҒгғ•гғ¬гғҮгӮЈгғ»гӮ°гғӘгғјгғігҒ®ејҫгӮҖгғӘгӮәгғ гҒ«д№—гҒЈгҒҰеҝ«иӘҝгҒ«гӮ№гӮӨгғігӮ°гҒҷгӮӢгӮ«гӮҰгғігғҲгғ»гғҷгӮӨгӮ·гғјгҒ®гғҗгғігғүгҒҢжңҖй«ҳгҒ«жҘҪгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҪјеҘігҒ®гҒҠж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒҜз§Ӣеҗүж•Ҹеӯҗпјқгғ«гғјгғ»гӮҝгғҗгӮӯгғігғ»гғ“гғғгӮ°гғ»гғҗгғігғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеғ•гҒҜгҒқгҒ®жҷӮз§Ӣеҗүж•ҸеӯҗгҒ®гғ”гӮўгғҺгғҲгғӘгӮӘгҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгғ“гғғгӮ°гғ»гғҗгғігғүгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ•гҒЈгҒқгҒҸгҖҢгғӯгғјгғүгғ»гӮҝгӮӨгғ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжқҘж—ҘгӮ№гғҶгғјгӮёгҒ®йҢІйҹізӣӨгӮ’иІ·гҒЈгҒҰиҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҮ„гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дёӯгҒ«еӯӨи»ҚгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®гҒ«гҒҠгҒ„гҒҢгҒ·гӮ“гҒ·гӮ“гҒҷгӮӢз§Ӣеҗүж•ҸеӯҗгҒ®жӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ«гғјгғ»гӮҝгғҗгӮӯгғігҒ®гғ•гғ«гғјгғҲгҒҢе°әе…«гҒ®йҹіиүІгӮ’еҘҸгҒ§гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®гғ“гғјгғҲгҒ«гҒ®гҒЈгҒҰжңҖй«ҳгҒ«зӣӣгӮҠдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒҢгӮёгғЈгӮәгҒ§иЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
еҪјеҘігҒҢдҪңжӣІгҒ—гҒҹеӯӨи»ҚгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгҖҒгҒ“гҒ®е№ҙгҒ«дё–й–“гҒ®и©ұйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹе°ҸйҮҺз”°еҜӣйғҺе°‘е°үгҒ®гҒ“гҒЁгҒЁгҖҒеҪјеҘіиҮӘиә«гҒҢзұіеӣҪгҒ§еӯӨи»ҚеҘ®й—ҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігӮ’иҫјгӮҒгҒҰгҒӨгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҖҒжң¬дәәгҒҢиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒ«еӯӨи»Қд»ҘеӨ–гҒ«еўЁзөөгҒЁгҒӢгғҹгғҠгғһгӮҝгҖҒеЎ©йҠҖжқҸгҖҒгғӯгғігӮ°гғ»гӮӨгӮЁгғӯгғјгғ»гғӯгғјгғүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҪјеҘіиҮӘиә«гҒ®жүӢгҒ«гӮҲгӮӢж—Ҙжң¬гҒ®гҒ«гҒҠгҒ„гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹжӣІгҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“зҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
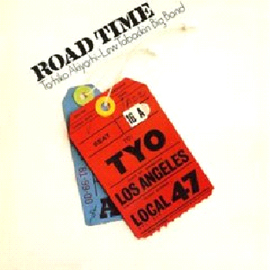
гҒ“гҒ®еӢ•ж©ҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжң¬дәәгҒҢгҖҢгӮёгғЈгӮәгҒЁз”ҹгҒҚгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒ®дёӯгҒ§ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјӯпјӘпјұгҒ®гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҖҒгӮёгғ§гғігғ»гғ«гӮӨгӮ№гҒҢгӮігғігӮігғ«гғүгҖҒгғҗгғігғүгғјгғ гҖҒгғ•гӮ©гғігғҶгғғгӮөгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдёҖйҖЈгҒ®жӣІгҒ«гғҗгғғгғҸгҒ®гғ•гғјгӮ¬гҒ®жҠҖжі•гҒЁгҒӢгҖҒејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸгҒ®жҠҖжі•гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҪјгҒҜгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«жҶ§гӮҢгҒҰгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶжӣІгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒӘгӮүгҒ°з§ҒгӮӮеҗҢгҒҳзҷәжғігҒ§ж—Ҙжң¬гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮҲгҒҶгҒЁгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҪјеҘігҒ®жӣІгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгӮёгғ§гғігғ»гғ«гӮӨгӮ№гҒҜгҖҢж—Ҙжң¬гҒҜеҪјеҘігҒ«д»»гҒӣгӮҲгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎеҪјгҒҜгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«жҶ§гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮёгғЈгӮәгӮ’дё–з•ҢгҒ®йҹіжҘҪгҒ«гҒ—гҒҹгҒҸгҒҰжӣІгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҫҢгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒҜжқұ欧гҒ®еҢӮгҒ„гҒ®гҒҷгӮӢжӣІгӮӮеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒ§еӣҪйҡӣеҢ–пјҲгӮ°гғӯгғјгғҗгғӘгӮјгғјгӮ·гғ§гғіпјүгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„еҹәжә–гҒ«иҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«еҸ—гҒ‘жӯўгӮҒгӮӢдәәгҒҢеӨ§еӨҡж•°гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮиӢұиӘһгҒ§гҒӮгӮӢгӮ°гғӯгғјгғҗгғӘгӮјгғјгӮ·гғ§гғігӮ’гҖҒзұігғ»иӢұдәәгҒҜгҒ©гҒҶжҚ•гӮүгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҹәжә–гҒҢжңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’дё–з•ҢгҒ®жЁҷжә–гҒЁгҒ—гҒҰжҷ®еҸҠгҒ•гҒӣгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҢеӣҪйҡӣеҹәжә–гҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜдҪ•гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®еҹәжә–гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮж—Ҙжң¬дәәгҒҢжҸҸгҒҸеӣҪйҡӣеҢ–гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҖ…гҒ®и»ҚдәӢзҡ„гҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒ«гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеј·гҒ„еӣҪгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’еӯҰгҒігҖҒеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢиЎҢеӢ•гғ‘гӮҝгғјгғігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰдёӯеӣҪгҒҢеј·гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹжҷӮгҒҜдёӯеӣҪгҒ«еӯҰгҒігҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒҢгҒҷгҒҷгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹжҷӮгҒҜгӮӘгғ©гғігғҖгҒ«еӯҰгҒігҖҒд»ҠгҒҜгӮўгғЎгғӘгӮ«дёҖиҫәеҖ’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲзұіеҺҹдёҮзҗҶгҒ•гӮ“гҒ®гҖҢж„ӣгҒ®жі•еүҮгҖҚгҒ®дёӯгҒ®еӣҪйҡӣеҢ–гҒЁгӮ°гғӯгғјгғҗгғӘгӮјгғјгӮ·гғ§гғігҒ®гҒӮгҒ„гҒ гҖҒгӮҲгӮҠеј•з”Ёпјү
гҒ§гӮӮж—Ҙжң¬гҒ§гӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гӮ№гӮҝгғігғҖгғјгғүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№гҒ§гҒҜгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гӮўгғігӮ°гғӯгӮөгӮҜгӮҪгғігҒ®иіҮжң¬дё»зҫ©гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеёӮе ҙгҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒ«гҒҷгҒ№гҒҰгӮ’гӮҶгҒ гҒӯгӮӢж–№жі•гҒҜгҖҒжұәгҒ—гҒҰдё–з•ҢгҒ®жЁҷжә–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзӨҫдјҡзҡ„е…¬жӯЈгҒ•гӮ’ж¬ гҒ„гҒҹзұіиӢұеһӢиіҮжң¬дё»зҫ©гҒ«гҒҷгҒҺгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠдёҖгҒӨгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгғ•гғ©гғігӮ№гҒ§гҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶ…еұұзҜҖгҒ•гӮ“гҒҢйҖұеҲҠгӮЁгӮігғҺгғҹгӮ№гғҲгҒ®жңҲжӣңж—ҘгҒ®жүӢзҙҷгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮҲгӮҠеј•з”Ёпјү
еј•з”ЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒҰз”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒҢгҖҒдёҠиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒдё–з•ҢгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®ж°‘ж—ҸгӮ„еӣҪгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒҺгӮҠгҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒҢзҗҶи§ЈгҒ—гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒж–ҮеҢ–гҒ«и§ҰгӮҢгҖҒжӯҙеҸІгӮ’зҹҘгӮҠгҖҒдҫЎеҖӨиҰігӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖиҝ‘гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®дјҒжҘӯгҒ®ж–№гҒҢгҖҒд»•дәӢгҒ§жө·еӨ–гҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®ж©ҹдјҡгӮ’жҚүгҒҲгҒҰжҳҜйқһгҖҒз©ҚжҘөзҡ„гҒ«гҒқгҒ®еӣҪгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еӢүеј·гҒ—гҖҒж–ҮеҢ–гҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
зҗҶи§ЈгҒ—гҒӮгҒҶгҒ“гҒЁгҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гҒҜгҖҒеӣҪгҒЁеӣҪгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдјҒжҘӯгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ—гҖҒдәәгҒЁдәәгҒ®й–“гҒ«гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮдҫЎеҖӨиҰігҒ®йҒ•гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢзӣёжүӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒқгҒ®е·®гҒҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘еҹӢгҒҫгҒЈгҒҰзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°иҮӘеҲҶгҒ®гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„еҪўгҒ§гҒ—гҒӢеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ“гҒ«гҒҷгӮҢйҒ•гҒ„гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еҹӢгӮҒгӮӢгҒ®гҒҜеҜҫи©ұгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи»ӢиҪўгҒ«гҖҒгҒ©гҒ®зЁӢеәҰеҶ·йқҷгҒ•гӮ’еӨұгӮҸгҒҡгҒ«еҜҫеҮҰгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒҢеӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
гҒ“гҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒЁеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒгҒқгҒ®ж №жӢ гҒ®зўәгҒӢгӮүгҒ—гҒ•гҒҜгҖҒгҒҜгҒӘгҒҜгҒ жҖӘгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҖӮгӮҲгҒҸиҖғгҒҲгҒҰгҖҒиӘ е®ҹгҒ§гҖҒеҢ…е®№еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢдәәй–“гҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘдәәгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

еғ•гҒҜдјҡзӨҫгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒ—гҒҰгҖҢгӮЁгӮігғҺгғҹгӮ№гғҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйӣ‘иӘҢгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«иӘӯгҒҝе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮе®ҹеӢҷзҡ„гҒӘзөҢжёҲиӘҢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒи©•и«–гҒЁгҒӢгҖҒеҜҫи«ҮгҒЁгҒӢгҖҒи«–ж–ҮгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒҸгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢзЎ¬гҒ„жң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§ж¬ гҒӢгҒ•гҒҡгҒ«зӣ®гӮ’йҖҡгҒҷгӮӮгҒ®гҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒжӣёи©•ж¬„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жӣёи©•ж¬„гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒеӨҸдј‘гҒҝгҒ«иӘӯгӮҖжң¬гҒ®зү№йӣҶгҒЁгҒӢгҒҢе®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒиӘӯжӣёгҒ®гӮёгғЈгғігғ«гҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҹйғЁеҲҶгӮӮеӨҡгҒҸгҒӮгӮӢгҖӮж—©е·қж–Үеә«гҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢжҺўеҒөгғҹгӮ№гғҶгғӘгғјгҒӘгҒ©гҒҢгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүи»ҚдәӢеҶ’йҷәе°ҸиӘ¬гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҒжө·еӨ–гҒ®зҝ»иЁізү©гҒҢең§еҖ’зҡ„гҒ«йқўзҷҪгҒ„гҖӮ
гҒқгҒ®дёӯгҒ§йқўзҷҪгҒ„иҮӘдјқе°ҸиӘ¬гҒ«еҮәдјҡгҒЈгҒҹгҖӮгғҺгғјгғҷгғ«зү©зҗҶеӯҰиіһгӮ’еҸ—иіһгҒ—гҒҹгғӘгғҒгғЈгғјгғүгғ»гғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ®жӣёгҒ„гҒҹпҪўгҒ”еҶ—и«ҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҒгғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ•гӮ“пҪЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҪјгҒ®йЈҫгӮҠж°—гҒ®гҒӘгҒ„дәәжҹ„гҒЁгҖҒз ”з©¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжғ…зҶұгҒЁгҖҒгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҒЁеҶ’йҷәжҒӢж„ӣгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдёӯгҖ…гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еІ©жіўгҒӢгӮүеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢгҒ”еҶ—и«ҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҒгғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ•гӮ“в… пҪЈгҖҒгҖҢгҒ”еҶ—и«ҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҒгғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ•гӮ“в…ЎпҪЈгҖҒгҖҢеӣ°гӮҠгҒҫгҒҷгғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ•гӮ“гҖҚгҖҒгҖҢгғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ•гӮ“жңҖеҫҢгҒ®еҶ’йҷәгҖҚгҒ®4еҶҠгҒҜиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮпјҲд»ҠгҒҜеІ©жіўзҸҫд»Јж–Үеә«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјү

еҗҚеҸӨеұӢеӨ§еӯҰгҒ®йЈҜеі¶е®—дёҖе…ғеӯҰй•·гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹеӯҰзӘ“йӣ‘иЁҳгҒЁиЁҖгҒҶжң¬гӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜ第2ејҫгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ第1ејҫгӮӮгҒҷгҒ§гҒ«е…ҘжүӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮЁгғғгӮ»гӮӨйӣҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҒ“гӮҢгӮ’иӘӯгӮҖгҒЁйЈҜеі¶е…Ҳз”ҹгҒ®е№…гҒ®еәғгҒ„еӯҰе•ҸзҹҘиӯҳгҒ«й©ҡгҒӢгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®дёӯгҒ«гӮӮгҖҢгӮҸгҒӢгӮүгҒҡгӮ„гҒ®гғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒ•гӮ“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–ҮгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғ•гӮЎгӮӨгғігғһгғігҒҢиӘ°гҒӢгҒ®и«–ж–ҮгӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҖҢзӨҫдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҖӢгҖ…гҒ®дәәй–“гҒҜгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иҰ–иҰҡзҡ„гҖҒиЎЁиұЎзҡ„зөҢи·ҜгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰжғ…е ұгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖҚгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гӮҲгҒҸгӮҲгҒҸзҝ»иЁігҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁдҪ•гҒ®дәӢгҒҜз„ЎгҒ„гҖҢдәәгҒҜгӮӮгҒ®гӮ’иӘӯгӮҖгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гӮ“гҒӘиӘҝеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒеӯҰдјҡгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгӮӮеҲӨгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜеҲӨгӮүгҒӘгҒ„гҒЁиіӘе•ҸгӮ’йҖЈзҷәгҒҷгӮӢгҖӮгҒҷгӮӢгҒЁдјҡе ҙгҒ®йҖҹиЁҳиҖ…гҒ«е…Ҳз”ҹгҒҜеӨ§еӯҰгҒ®ж•ҷжҺҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒЁиіӘе•ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒӘгҒңгҒӘгӮүиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гӮӮеҲӨгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮйқўзҷҪгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ