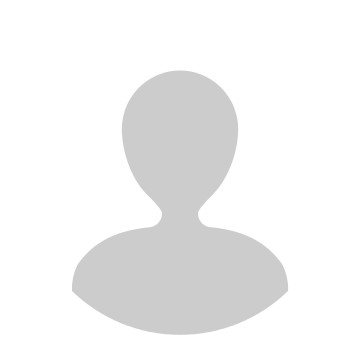|
гҒҠжҳјгҒ«гғҶгғ¬гғ“гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒж°ҙи°·иұҠдё»жј”гҒ®зӣёжЈ’гҒЁгҒ„гҒҶгғүгғ©гғһгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮж®әдәәдәӢ件гӮ’гҒҝгҒ”гҒЁгҒӘжҺЁзҗҶгҒ§ж¬ЎгҖ…гҒЁи§ЈжұәгҒҷгӮӢеҲ‘дәӢгҒ®зү©иӘһгҒ§гҖҒд»ҠгғҶгғ¬гғ“гҒ®дәәж°—з•Әзө„гҒ®дёҖгҒӨгҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»Ҡж—ҘгҒ®и©ұгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒҢж®әгҒ•гӮҢгҖҒзҠҜдәәгҒҢгғ”гӮўгғҺгҒ®иӘҝеҫӢеё«гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒӢгҒ«жҺЁзҗҶгҒ—гҒҰзӘҒгҒҚжӯўгӮҒгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҲ‘дәӢгҒҜгғ”гӮўгғҺгҒҢејҫгҒ‘гҖҒгҒ—гҒӢгӮӮиӘҝеҫӢеё«гҒ§гӮӮж°—гҒҘгҒӢгҒӘгҒ„йҹігҒ®еҫ®еҰҷгҒӘеӨүеҢ–гӮ’ж„ҹгҒҳеҸ–гӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢдәӢ件解жұәгҒ®жүӢгҒҢгҒӢгӮҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгӮҶгҒҸгҖӮе°‘гҖ…и©ұгҒ—гҒҢеҮәжқҘгҒҷгҒҺгҒ§дҝЎгҒҳгҒҢгҒҹгҒ„гҖӮгҒқгӮ“гҒӘеҲ‘дәӢгҒ„гӮӢгҒӢгӮҲгҖҒгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮд»®е®ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҖжөҒгҒ®гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°еҪ“然気гҒҘгҒҸгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒҢгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫеҲ‘дәӢгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҒ“гҒ®и©ұгҒҜжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҖӮгӮӮгҒ—гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҒ¶з„¶гҒҢйҮҚгҒӯгӮҢгҒ°дәӢ件гӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе№ёйҒӢгӮ’жӢӣгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
е№ёйҒӢгӮ’жӢӣгҒҸгғҒгғЈгғігӮ№гҒҜ4гҒӨгҒ®гӮҝгӮӨгғ—гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮпјҲгҒ“гҒ®и©ұгҒҜдә¬йғҪеӨ§еӯҰйңҠй•·йЎһз ”з©¶жүҖгҒ®жүҖй•·гҖҒд№…дҝқ田競е…Ҳз”ҹгҒ®и¬ӣжј”гҒ§иҒһгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢпјү
пј‘пјүжЈҡгғңгӮҝ
иҮӘеҲҶгҒҜдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҒжЈҡгҒӢгӮүгғңгӮҝйӨ…гҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎжҖқгҒ„гҒҢгҒ‘гҒӘгҒ„е№ёйҒӢгҒ«жҒөгҒҫгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғҒгғЈгғігӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пј’пјүгӮӨгғҢжЈ’
зҠ¬гӮӮжӯ©гҒ‘гҒ°жЈ’гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§з©ҚжҘөзҡ„гҒ«е№ёйҒӢгӮ’жӢӣгҒҸгғҒгғЈгғігӮ№гҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮгҒӮгҒҫгӮҠж·ұгҒҸиҖғгҒҲгҒҰиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸз©ҚжҘөзҡ„гҒ«иЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгғҒгғЈгғігӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пј“пјүгӮ¬гғ«гғҗгғӢ
гӮ¬гғ«гғҗгғӢйӣ»жұ гҒ®гҒӮгҒ®гӮ¬гғ«гғҗгғӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜзӯӢиӮүгҒҢеӢ•гҒҸгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж—Ҙй ғгҒӢгӮүеј·гҒ„й–ўеҝғгӮ’жҠұгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒҚжұ гҒ®йү„жҹөгҒ«гҒЁгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹиӣҷгҒ®и¶ігҒҢгҖҒйӣ·гҒ®йӣ»ж°—гҒ§еҸҚе°„зҡ„гҒ«еӢ•гҒҸгҒ®гӮ’иҰӢгҒҰгҖҒзӯӢиӮүгҒҜйӣ»жөҒгҒҢжөҒгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӢ•гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒеёёж—Ҙй ғгҒӢгӮүгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«е•ҸйЎҢж„ҸиӯҳгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰж·ұгҒҸз ”з©¶гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж…ӢеәҰгҒ§иҮЁгӮҖгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиЁӘгӮҢгҒҹгғҒгғЈгғігӮ№гҒ§е№ёйҒӢгӮ’жүӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғҹгғігӮ°гҒҢгғҡгғӢгӮ·гғӘгғігӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҒ®гӮӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгғҒгғЈгғігӮ№гӮ’гӮӮгҒ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пј”пјүгӮ»гғ¬гғігғҮгӮЈгғғгғ—
дёҖгҒӨгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹиғҪеҠӣгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®дәәгҒ®е…Ёдәәж јгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ®й«ҳгҒ„иҰӢиӯҳгҒҢе№ёйҒӢгӮ’зү©гҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гӮўгғ«гӮҝгғ»гғҹгғ©гҒ®жҙһзӘҹгҒ®еҸӨд»ЈгҒ®еЈҒз”»гӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҖҒең°иіӘеӯҰиҖ…гҒ§гӮўгғһгғҒгғҘгӮўгҒ®иҖғеҸӨеӯҰиҖ…гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгғһгӮ№гӮ»гғӘгғҺгғ»гӮөгӮҰгғҲгӮҘгӮӘгғјгғ©гҒ®и©ұгҒҢдҫӢгҒ«жҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҖҢ1879е№ҙгҒ®гҒӮгӮӢгҒЁгҒҚеҪјгҒҜе№јгҒ„еЁҳгҒ®гғһгғӘгӮўгҒЁгғ”гӮҜгғӢгғғгӮҜгҒ«жқҘгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮйҒҠгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢеЁҳгҒҢиҰӢгҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠеҝғй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒҠзҲ¶гҒ•гӮ“пјҒзүӣгӮҲпјҒзүӣгӮҲпјҒгҒЁгҒ„гҒҶеЁҳгҒ®еЈ°гҒҢжҙһзӘҹгӮҲгӮҠиҒһгҒ“гҒҲгҖҒдёӯгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеЁҳгҒҢеӨ©дә•гҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹеЈҒз”»гӮ’жҢҮе·®гҒ—гҒҰгҖҢгӮўгғ«гӮҝгғ»гғҹгғ©гҖҚпјҲдёҠгӮ’иҰӢгҒҰпјүгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ«гҒҜйҮҺзүӣгҒ®зөөгҒҢжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®зөөгӮ’иҰӢгҒҰеҪјгҒҜгҒқгҒ“гҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйҮҺзүӣгҒҢгҖҒзҸҫеӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮӮгҒҶзө¶ж»…гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҖҒе°Ӯй–ҖгҒ®ең°иіӘиӘҝжҹ»гҒӘгҒ©гӮ’гҒҷгӮӢгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢж—§зҹіеҷЁжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢеҪ“еҲқгҒҜиӘ°гӮӮеҪјгҒ®и©ұгӮ’дҝЎгҒҳгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒиҮӘдҪңиҮӘжј”гҒ®дҪңгӮҠи©ұгҒЁз–‘гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚ
е°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж·ұгҒ„и¶Је‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҖҒеӯҗдҫӣгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҘҪеҘҮеҝғгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгӮ»гғ¬гғігғҮгӮЈгғғгғ—гҒӘгғҒгғЈгғігӮ№гӮ’зү©гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гҒ—гҒҡгӮҒгҖҒгҒӮгҒ®еҲ‘дәӢгҒҜгӮ»гғ¬гғігғҮгӮЈгғғгғ—гҒӘи„іеҠӣгҒ®жҢҒгҒЎдё»гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮиӘ°гӮӮгҒҢдҝЎгҒҳгҒҢгҒҹгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒ®гҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜгҖӮ


гҒјгҒҸгҒҜе№ҙгҒ«ж•°еӣһгҒҘгҒӨгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®жј”еҘҸдјҡгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёҚе№ёгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬5з•ӘгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮйҒҺеҺ»гҒ«2еӣһгҒҸгӮүгҒ„гғҒгғЈгғігӮ№гҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮйғҪеҗҲгҒҢгҒӨгҒӢгҒҡиҒһгҒҚйҖғгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“LPгӮ„CDгҒ§20жһҡгҒҸгӮүгҒ„гҒҜжҢҒгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиүІгҖ…гҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮз”ҹжј”еҘҸгҒҢиҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒ®жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®дё»гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гҒӮгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒгғ«гғјгғ“гғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігҒЁгғҗгғ¬гғігғңгӮӨгғ гҖҒгӮјгғ«гӮӯгғігҒЁгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғігҖҒгӮ°гғ«гғҖгҒЁгғӣгғ«гӮ№гғҲгғ»гӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігҖҒгғҗгғғгӮҜгғҸгӮҰгӮ№гҒЁгӮҜгғ¬гғЎгғігӮ№гғ»гӮҜгғ©гӮҰгӮ№гҖҒгғ„гӮЈгғһгғјгғһгғігҒЁгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғігҖҒгӮ®гғ¬гғӘгӮ№гҒЁгӮ»гғ«гҖҒгӮ°гғјгғ«гғүгҒЁгӮ№гғҲгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҖҒгӮұгғігғ—гҒЁгғ©гӮӨгғҲгғҠгғјгҖҒгғ•гӮЈгғғгӮ·гғЈгғјгҒЁгғ•гғ«гғҲгғҷгғігӮ°гғ©гғјгҖҒеҶ…з”°гҒЁгӮ¶гғігғҮгғ«гғӘгғігӮ°гҖҒгғҡгғ©гӮӨгғӨгҒЁгғҸгӮӨгғҶгғігӮҜгҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жј”еҘҸгҒҜгҒҝгҒӘеҘҪгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮзҡҮеёқгҒ®дёӯгҒ®зҡҮеёқгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгғ«гғјгғ“гғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігҒЁгғҗгғ¬гғігғңгӮӨгғ гҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜгҒқгҒ®еүҚгҒ«гӮӮгғ©гӮӨгғігӮ№гғүгғ«гғ•пјҸгғңгӮ№гғҲгғігғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгҒЁз«¶жј”гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®80жӯігӮ’йҒҺгҒҺгҒҰгҒӢгӮүгҒ®гғҗгғ¬гғігғңгӮӨгғ гҒЁгҒ®жј”еҘҸгҒҢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҖӮеҮәгҒ гҒ—гҒ®гӮ«гғҮгғігғ„гӮЎгҒӢгӮүгҒ—гҒҰй©ҡгҒҚгҒ®йҖЈз¶ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгғҶгғігғқгҒ§дёҖйҹідёҖйҹігӮ’иұҠгҒӢгҒ«йҹҝгҒӢгҒӣгҒҰгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮиұӘиҸҜзөўзҲӣгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘжј”еҘҸгҒҜиҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғ”гӮўгғҺгҒ®иҖҒеӨ§е®¶гҒҢжӮ 然гҒЁиҮӘеҲҶгҒ®гӮ„гӮҠж–№гҒ§жј”еҘҸгҒ—гҖҒгғҗгғ¬гғігғңгӮӨгғ гҒҢгҒқгӮҢгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гӮ’гғӘгғјгғүгҒ—гҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гҒҜгҖҒжәҢеүҢгҒЁгҒ—гҒҰгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘгӮ°гғ«гғҖгҒ®жј”еҘҸгӮӮеҘҪгҒҚгҒ гҒ—гҖҒгӮ°гғјгғ«гғүгҒ®жј”еҘҸгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е…ҲжңҲгҒ®19ж—ҘгҒ«иұҠз”°еёӮгҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ§гҖҒгӮөгғ©гғ»гғҒгғЈгғігҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігҖҒгғһгғӘгӮ№гғ»гғӨгғігӮҪгғігӮ№жҢҮжҸ®пјҸгғҗгӮӨгӮЁгғ«гғіж”ҫйҖҒдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгғЎгғігғҮгғ«гӮ№гӮҫгғјгғігҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғӘгғіеҚ”еҘҸжӣІгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҖӮдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжңҖеүҚеҲ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮөгғ©гғ»гғҒгғЈгғігҒҜжј”еҘҸгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§дјқиӘ¬гҒ®гӮёгғҚгғғгғҲгғ»гғҢгғҙгғјгҒ®й·№гҒ®зӣ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйӢӯгҒ„зӣ®гҒ§гғӨгғігӮҪгғігӮ№гҒ«еҗҲеӣігӮ’йҖҒгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒзӢ¬еҘҸиҖ…з”ЁгҒ®зӢӯгҒ„гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ®дёӯгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘи¶ійҹігӮ’з«ӢгҒҰгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеүҚгҒёиЎҢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҫҢгӮҚгҒ«дёӢгҒҢгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгғӘгӮәгғ гӮ’гҒЁгӮҠгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҒ•гҒӮдёҖз·’гҒ«еҗҲеҘҸгҒҷгӮӢгҒһгҒЁгҖҒгҒ°гҒӢгӮҠгҒ«гӮўгӮӨгғ»гӮігғігӮҝгӮҜгғҲгӮ’гҒ—гҒҹгӮҠгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гғүгғ©гғһгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзёҰжЁӘз„Ўе°ҪгҒ®жҙ»иәҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҘҸгҒ§гӮӢйҹігҒҜгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒӮгӮӢгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘжј”еҘҸгҒ§гҖҒе„Әйӣ…гҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ®гғЎгғігӮігғігҒЁгҒҜдёҖз·ҡгӮ’з”»гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҜеҚҒеҲҶжҘҪгҒ—гӮ“гҒ гҖӮгҒҹгҒ CDгҒ§гҒ“гҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒ„гҒҹгӮүгҒ©гҒҶжҖқгҒҶгҒӢгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ
гҒјгҒҸгҒҢгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®5з•ӘгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮігғігғҒгӮ§гғ«гғҲгҒ®з”ҹжј”еҘҸгҒ«жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғүгғ©гғһгӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒјгҒҸгҒҢеҘҪгӮ“гҒ§иҒһгҒҸжј”еҘҸгҒҜгҖҒзӢ¬еҘҸиҖ…гҒЁжҢҮжҸ®иҖ…гҒ®гҒӮгҒ„гҒ гҒ«з·Ҡејөй–ўдҝӮгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰжј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҒ¶з„¶гҒ®дёҖиҮҙгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢпјүжҘөз«ҜгҒӘдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒгӮ°гғјгғ«гғүгҒЁдёҖз·’гҒ«гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®пј’з•ӘгӮ’жј”еҘҸгҒ—гҒҹгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғігҒҜгҖҒжј”еҘҸеҫҢгҒ«иҒҙиЎҶгҒ«гҒ“гҒ®жј”еҘҸгҒҜз§ҒгҒ®ж„ҸеӣігҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒЁйҮҲжҳҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬5з•ӘгҒ®з”ҹжј”еҘҸгӮ’иҒһгҒҸжҘҪгҒ—гҒҝгҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ еҪ“еҲҶз¶ҡгҒҚгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ


гҒјгҒҸгҒҜгӮёгғЈгӮәгҒЁгҒӢгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӣёгҒӢгӮҢгҒҹжң¬гҒҜгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜйҹіжҘҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘһгӮүгӮҢгҒҹжң¬гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒеҗүз”°з§Җе’ҢгҒ•гӮ“гҒЁе®ҮйҮҺеҠҹиҠігҒ•гӮ“гҒ®жӣёгҒӢгӮҢгҒҹжң¬гӮ’еҘҪгӮ“гҒ§иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮиҫһжӣёгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪҝгҒ„ж–№гӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҝ—йіҘж „е…«йғҺз·Ёи‘—гҒ«гӮҲгӮӢгҖҢеӨ§дҪңжӣІе®¶гҒЁгҒқгҒ®гғ¬гӮігғјгғүгҖҚпјҲе…Ё3е·»пјүгҒЁйҹіжҘҪд№ӢеҸӢзӨҫгҒ®гҖҢеҗҚжӣІи§ЈиӘ¬е…ЁйӣҶгҖҚпјҲе…Ё24е·»пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еҗүз”°з§Җе’ҢгҒ•гӮ“гҒ®жң¬гҒ§гҒҜгҖҒжҳӯе’Ң56е№ҙгҒӢгӮү58е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰж–°жҪ®ж–Үеә«гӮҲгӮҠеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢпј¬пј°300йҒёгҖҚгҖҢдё–з•ҢгҒ®жҢҮжҸ®иҖ…гҖҚгҖҢдё–з•ҢгҒ®гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҖҚгҒ®3еҶҠгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢжңҖеҲқгҒ«иӘӯгӮ“гҒ жң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҜеҗүз”°з§Җе’ҢгҒ•гӮ“гҒ®жң¬гӮ’ж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°иіје…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮж–Үеә«жң¬гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸеҚҳиЎҢжң¬гӮӮгҖҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж–°жң¬гҒ§гҒҜе…ҘжүӢгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜеҸӨжң¬гҒ§иІ·гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҒҫгҒ 25еҶҠзЁӢеәҰгҒ—гҒӢжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮеҸӨжң¬гҒҜдё»гҒЁгҒ—гҒҰеҗҚеҸӨеұӢгҒ®гғ‘гғ«гӮігҒ®еүҚгҒ«гҒӮгӮӢдәәз”ҹжӣёжҲҝгҒЁгҒ„гҒҶеҸӨжң¬еұӢгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®еҸӨжң¬еұӢгҒҜиҰҸжЁЎгҒ®еүІгӮҠгҒ«гҖҒйҹіжҘҪгҒЁгҒӢзөөз”»гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиҠёиЎ“й–ўдҝӮгҒ®жң¬гҒҢеӨҡгҒҸзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°иҰ—гҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҢеҗүз”°з§Җе’ҢгҒ•гӮ“гҒ®жң¬гӮ’еҘҪгӮҖзҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒқгҒ®йҹіжҘҪи©•и«–гҒ®ж–№жі•гҒҢеҘҪгҒҚгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгӮӢдҪңжӣІе®¶гҒ®дҪңе“ҒгҒӘгӮҠжј”еҘҸгҒӘгӮҠгӮ’гҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶзҗҶз”ұгҒ§еҘҪгӮҖгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜеҘҪгҒҫгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁж…ӢеәҰгӮ’гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ•гҒӣгҖҒгҒӘгҒңгҒқгҒҶгҒӘгҒ®гҒӢгӮ’гҖҒгҒқгҒ®дҪңе“ҒгҒ®ж§ӢжҲҗгҒ®д»•ж–№гҖҒдҪңиҖ…гҒҜгҒӘгҒңгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгҒөгҒҶгҒ«дҪңжӣІгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒжҺЁзҗҶгҒ—гҒқгӮҢгӮ’иЁјжҳҺгҒ—гҒҰиҰӢгҒӣгӮӢгҖӮгҒқгҒ®ж–Үз« гҒ®ж§ӢжҲҗж–№жі•гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒдҪңиҖ…иҮӘиә«гҒ®еәғгҒҸж·ұгҒ„йҹіжҘҪгҒёгҒ®йҖ и©ЈгҒ«иЈҸжү“гҒЎгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒеҲӨж–ӯгҒ®иҰӢдәӢгҒ•гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгӮӮгҒӢгҒӨгҒҰгҒҜиҮӘеӢ•и»Ҡй–ӢзҷәгҒ«жҗәгӮҸгӮӢжҠҖиЎ“иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’дҫӢгҒ«и©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ競еҗҲгғЎгғјгӮ«гғјгҒҢж–°и»ҠгӮ’зҷәиЎЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®иӘҝжҹ»гӮ’гҒҷгӮӢгҖӮиЁӯиЁҲиҖ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®йү„жқҝгҒ«гӮҲгӮӢжқҝзө„гҒҝж§ӢйҖ гӮ’иҰӢгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒҜи»ҪйҮҸеҢ–гҒЁеј·еәҰгҒ®дёЎз«ӢгҒҢеӨ§еӨүгҒҶгҒҫгҒҸиЁӯиЁҲгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§гҒҜгҖҒйҳІйҢҶгҒ«гҒҜе„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢдҪңжҘӯгҒҢеӨ§еӨүгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§зҘһзөҢгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҗ„йғЁзҪІгҒ®йҖЈжҗәгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒӢгҖҒгӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒ®иЁӯиЁҲж–№жі•гӮ’з ”з©¶гҒ—гҒҹгҒӘгҒЁгҒӢгӮҸгҒӢгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜи…•гҒ®иүҜгҒ„иЁӯиЁҲиҖ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒӮгӮӢгҒ»гҒ©гҒқгҒҶгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ
гҒјгҒҸгҒҜйҹіжҘҪзҗҶи«–гҒ®е°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮӮжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ—гҖҒжҘҪиӯңгӮ’иҰӢгҒҰгғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгҒҢжө®гҒӢгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҗүз”°з§Җе’ҢгҒ•гӮ“гҒ®и©•и«–гҒӘгӮҠи§ЈиӘ¬гҒӘгӮҠгӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҖҒзўәгҒӢгҒӘе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒ«иЈҸжү“гҒЎгҒ•гӮҢгҒҹжҙһеҜҹеҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҖҒгҒқгҒ®зҷәжғігҒ®д»•ж–№гҒ«е…ұж„ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒз§ҒиҮӘиә«гҒ®зҹҘиӯҳгҒ®ж¬ еҰӮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„йғЁеҲҶгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гӮӮдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е®ҮйҮҺеҠҹиҠігҒ•гӮ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜеӨҡгҒҸгӮ’иҝ°гҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғҒгғ§гғігғ»гӮӯгғ§гғігғ»гғ•гӮЎгҒЁгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®йҹіжҘҪгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮ

гҒјгҒҸгҒҢ1999е№ҙгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж—ҘиЁҳйўЁгҒ®йӣ‘ж–ҮгӮ’жӣёгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒе°Ҹжһ—зҺІеӯҗгҒ•гӮ“гҒ®йҡҸзӯҶйӣҶгҖҢжө·иҫәгҒ®гҒқгӮҲйўЁгҖҚгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘж–ҮгҒҢжӣёгҒ‘гӮӢгҒЁгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“д»ҠгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгҒ®и¶іе…ғгҒ«гӮӮеҸҠгҒ°гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘ駄ж–ҮгҒ—гҒӢжӣёгҒ‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢ1999е№ҙгҒ®еҲқгӮҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮи‘—иҖ…гҒ«гҒҜз”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҜгҒ“гҒ®жң¬гӮ’гғ–гғғгӮҜгӮӘгғ•гҒ§100еҶҶгҒ§иіје…ҘгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯиә«гӮӮиҰӢгҒҡгҒ«гҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒҷз·‘иүІгҒ®еёғиЈҪгҒ®дёҠе“ҒгҒӘиЈ…дёҒгҒЁгҖҒгҒ•гӮҸгӮ„гҒӢгҒӘж°ҙиүІгҒ§еҚ°еҲ·гҒ•гӮҢгҒҹзҙҷгҒ®гӮ«гғҗгғјгҒЁгҖҒйЎҢеҗҚгҒ«гҒІгҒӢгӮҢгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе°Ҹжһ—зҺІеӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№гҒӢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒ«гҖӮ

жң¬гҒ®еёҜгҒ«гҒҜеҪјеҘігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢдёӯйғЁзөҢжёҲж–°иҒһгҒ®гҖҢй–‘дәәеё–гҖҚгғ¬гӮ®гғҘгғ©гғјгғЎгғігғҗгғјгҒ®е°Ҹжһ—зҺІеӯҗгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒиҘҝе°ҫеёӮеңЁдҪҸгҒ®з«Ҙи©ұдҪң家гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҪ“欄гҒ§гӮӮгҖҒжҷӮгҒ®жөҒгӮҢгҖҒеӣӣеӯЈжҠҳгҖ…гҒ®дҫҝгӮҠгҖҒиә«иҝ‘гҒӘеҮәжқҘдәӢгҒӘгҒ©гӮ’з¶ҙгҒЈгҒҹи»ҪеҰҷгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүеҝғгӮ’гҒҶгҒӨзӯҶйҒӢгҒігҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғ•гӮЎгғігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гҖҚгҒЁзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеёҜиЈҸгҒ«гҒҜеҪјеҘігҒ®йҡҸзӯҶгҒ®дёҖзҜҖгҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢгҖҢгҒҹгҒ„гҒҸгҒӨгҖҚгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒЁгҖҢгҒјгӮ“гӮ„гӮҠгҖҚгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜдјјгҒҰйқһгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгӮ“гӮ„гӮҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜеҝғгӮ’гӮҶгҒЈгҒҹгӮҠй–Ӣж”ҫгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘе·ұгӮ’иҮӘ然гҒЁеҗҢеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҝғгҒҜйҖҖеұҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮйіҘгҒ®еӣҖгӮҠгҖҒйӣІгҒ®жөҒгӮҢгҖҒиҚүжңЁгҒ®жҸәгӮҢгӮӢдёӯгӮ’йҖҚйҒҘгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒиҮӘ然гҒЁиӘһгӮҠгҖҒиҮӘеҲҶгҒЁиӘһгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдәәй–“гҒ«гҒҜгҒ“гҒ®жҷӮгҒ“гҒқгҒҢе®қгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢй–‘дәәеё–гҖҚгҒ®й–‘дәәгҒЁгҒҜгҖҒгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«жңүгӮҠйӣЈгҒҸиІҙйҮҚгҒӘжҷӮгӮ’гӮӮгҒӨдәәгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮзӨҫдјҡгҒ®е®қгҒЁгҒ§гӮӮеҳҜгҒ„гҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҒӢгҖҚгҒ“гҒ®ең°ж–№гҒ®дәәгӮүгҒ—гҒҸгҖҒиҘҝе°ҫгҖҒзў§еҚ—гҖҒе®үеҹҺгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹең°еҗҚгӮ„гҒ“гҒ®ең°ж–№еҮәиә«гҒ®дәәеҗҚгӮӮеӨҡгҒҸеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҢ1999е№ҙгҒӢгӮү2000е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжӣёгҒҚгҒЁгӮҒгҒҹйӣ‘иЁҳгҖҒB5гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ§пј‘пјҗпјҗгғҡгғјгӮёгҒ»гҒ©гҒ®еҶ…е®№гӮ’гҖҒдёҖеҶҠгҒ гҒ‘иҮӘеҲҶгҒ§иЈҪжң¬гҒ—гҖҢиҖігӮ’жҫ„гҒҫгҒӣгҒ°йҹіжҘҪгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨгғҲгғ«гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ®гӮӮгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒдёҖгҒӨгҒ®йӣ‘иЁҳгҒ®ж–Үз« гҒ®й•·гҒ•гӮ’гҖҒпј”пјҗпјҗеӯ—и©°гӮҒгҒ®еҺҹзЁҝз”Ёзҙҷпј“жһҡзЁӢеәҰгӮ’зӣ®е®үгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮӮгҖҒгҒҹгҒ¶гӮ“гҒ«гҒ“гҒ®йҡҸзӯҶйӣҶгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҪўејҸзҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгҒҜжүӢжң¬гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒҫгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒҢгҖҒйӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒҜж„ҹеҸ—жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢгҒјгӮ“гӮ„гӮҠгҖҚгҒ—гҒҰиҮӘ然гҒЁиӘһгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиҮӘеҲҶгҒЁиӘһгҒЈгҒҹгӮҠгҒҜгҖҒз°ЎеҚҳгҒ«гҒҜеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҖҢгҒјгӮ“гӮ„гӮҠгҖҚгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮжүҚиғҪгҒ«гҒҜеӨ©жҖ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҖҒиЁ“з·ҙгҒ§гҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҮәжқҘгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒӯгҒ гӮҠгҒҜгҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҒҰгҖҒиЁ“з·ҙгҒ§еҮәжқҘгӮӢзҜ„еӣІгҒ§ж„ҹеҸ—жҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҖҒгҒӘгӮӢгҒ№гҒҸжҜҺж—Ҙж–Үз« гӮ’жӣёгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дёүжІіең°ж–№гҒ®зҡҶгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒе°Ҹжһ—зҺІеӯҗгҒ•гӮ“гҒ®ең°е…ғгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒж–°жң¬гҒ§жүӢгҒ«е…ҘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ§гӮӮгҖҒеҸӨжң¬еұӢгӮ’жҺўгҒӣгҒ°гҒ“гҒ®жң¬гҒҜиҰӢгҒӨгҒӢгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒд»•дәӢгҒ§з–ІгӮҢгҒҹгҒЁгҒҚгҒӘгҒ©гҒ«гҖҒж°—еҲҶи»ўжҸӣгҒЁгҒ—гҒҰиӘӯгҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҚгҒЈгҒЁж„ҹеҸ—жҖ§гҒҢеў—гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҝҪиЁҳ
SUNVALLEY AUDIOгҒ®еӨ§ж©Ӣеә—дё»гҒ®гҒ”еҘҪж„ҸгҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒ®йӣ‘иЁҳгӮ’гҖҢгӮёгғЈгӮәгғ»гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®йӣ‘иЁҳеёігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ§жҺІијүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢж–Үз« гӮ’жӣёгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹзөҢз·ҜгҒҜд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮёгғЈгӮәгғ»гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ«еҝ…гҒҡгҒ—гӮӮгҒ“гҒ гӮҸгӮүгҒҡгҒ«йӣ‘иЁҳгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚҳгҒӘгӮӢйӣ‘иЁҳеёігҒЁгҒ—гҒҰиӘӯгӮ“гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҒјгҒҸгҒҜгҒ“гҒ®еӨҸгҒӢгӮүгҖҒ1йҖұй–“гҒ«пј“еӣһгҒҸгӮүгҒ„гҖҒзҹҘз«ӢеёӮгҒ«гҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҖҚпјҲTel:0566-81-9851пјүгҒ«йЎ”гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮй–Ӣеә—гҒҷгӮӢгҒЁ30еҲҶд»ҘеҶ…гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮд»Ҡе№ҙгҒ®еӨҸй ғгҒӢгӮүгҒқгҒҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨҸгҒҜеӨ•ж–№гҒ®4жҷӮй ғгҒӢгӮүгҖҒгҒҫгҒҹз•‘гҒ§дёҖд»•дәӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®еүҚгҖҒжҡ‘гҒ„зӣӣгӮҠгҒ«йЎ”гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®жҷӮй–“еёҜгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠе®ўгӮӮгҒ„гҒӘгҒҸпјҲгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒҢе…ЁзӣӣгҒ®й ғгҒҜгҖҒеӨ–гҒ§дёҰгӮ“гҒ§еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠе®ўгҒ•гӮ“гҒҢгҒ„гҒҰгҖҒй–Ӣеә—гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«жәҖеёӯгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢпјүгҖҒгҒҹгҒҫгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒҠе®ўгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜиҲҲе‘ігҒӮгӮӢдәәйҒ”гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮпјҲгғ¬гӮігғјгғүгӮ’гҒ“гҒ®еә—гҒ§иІ©еЈІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®дёӯеҸӨгғ¬гӮігғјгғүгӮ’еҸҺйӣҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰе®ҡжңҹзҡ„гҒ«йЎ”гӮ’еҮәгҒҷдәәгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘдё»е©ҰгҖҒе…Ҳз”ҹгҖҒдјҡзӨҫеҪ№е“ЎгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®иӢҘгҒ„й ғгҒӢгӮүгҒ®еҸӢдәәгҖҒгҒӘгҒ©гҒӘгҒ©пјү

гӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҚжқҘгӮӢгҒҠе®ўгҒ•гӮ“гҒҢгҒ„гӮӢжҷӮгҒҜгҖҒйқҷгҒӢгҒ«гғ¬гӮігғјгғүгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒеә—й ӯиІ©еЈІгҒ®LPгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәгҒ®йӣ‘иӘҢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ гӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒд»–гҒ®гҒҠе®ўгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„жҷӮгҒҜгғһгӮ№гӮҝгғјгҒЁи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ
дёҖз•ӘеӨҡгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒдёӯеҸӨLPгҒ®жғ…е ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ©гҒ“гҒ§гҒ©гӮ“гҒӘдёӯеҸӨLPгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжғ…е ұдәӨжҸӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®и¶Је‘ігҒҜгҖҒй§ҶгҒ‘еҮәгҒ—гҒ®гҒјгҒҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®ж–№гҒҜгҒҡгҒЈгҒЁзөҢйЁ“гҒҢиұҠеҜҢгҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҢжғ…е ұгӮ’иІ°гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒжңҖиҝ‘зү№гҒ«гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгҒҢеӨҡгҒҸйӣҶгҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гӮӮгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ·гғ§гғғгғ—гҒ§гҒ„гҒӢгҒ«е®үгҒҸиІ·гҒҶгҒӢгӮ’競гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҒқгӮҢгҒӢгӮүгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ«жқҘгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еә—гҒҜ1960е№ҙд»ЈгҒ«гӮҝгӮӨгғ гӮ№гғӘгғғгғ—гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгғҺгӮ№гӮҝгғ«гӮёгғјгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢеә—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеә—гӮ’ж”№иЈ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еҸӨгҒ„гҒҫгҒҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж©ҹжў°ејҸгҒ®жҹұжҷӮиЁҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮўгғігғҶгӮЈгғјгӮҜгӮ„гҖҒLPгӮ’дҝқз®ЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжүӢдҪңгӮҠгҒ®жЈҡгҖҒLPгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе»ғе“ҒгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹж®өгғңгғјгғ«з®ұгҒӘгҒ©гҖҒгҒҠйҮ‘гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҡгҒ«гғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢзҡҶжүӢдҪңгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®гӮ„гӮҠж–№гӮ’зңҹдјјгӮӢгҒЁе®үгҒҸеҮәжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гғҺгӮҰгғҸгӮҰгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®и©ұгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјиҮӘиә«гҒ®иұҠеҜҢгҒӘзөҢйЁ“гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгҒ“гҒ“гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒҠе®ўгҒ•гӮ“гҒ®иүІгҖ…гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘи¶Је‘ігҒ®и©ұгҖҒгҒӘгҒ©гҒӘгҒ©гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»
жҳЁж—ҘгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢеә—гҒ®еҘҘгӮҲгӮҠгҖҒгӮ„гҒЈгҒЁиҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒдёҖеҶҠгҒ®жң¬гӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒјгҒҸгҒ«иІёгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮгҖҢгҒҠгӮҢгҒҹгҒЎгҒ®гӮёгғЈгӮәзӢӮйқ’жҳҘиЁҳгҖҒгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶иӘ•з”ҹзү©иӘһгҖҚгҒ“гӮҢгҒҜе…ЁеӣҪжңүеҗҚгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ®гҒҠгӮ„гҒҳ33дәәгҒҢз¶ҙгҒЈгҒҹ笑гҒ„гҒЁгғҡгғјгӮҪгӮ№жәўгӮҢгӮӢйқ’жҳҘзү©иӘһгҖҒгҒЁеёҜгҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгҒ§гҒҜгӮёгғЈгӮәжң¬гҒ®еҹ·зӯҶиҖ…гҒ§гӮӮзҹҘгӮүгӮҢгӮӢгғЎгӮ°гҒ®еҜәеі¶йқ–еӣҪгҒ•гӮ“гҖҒгӮӨгғјгӮ°гғ«гҒ®еҫҢи—Өйӣ…жҙӢгҒ•гӮ“гҒӘгҒ©гҒҢеҗҚгӮ’йҖЈгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгӮӮеҹ·зӯҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ1991е№ҙгҒ®7жңҲгҒ®еҮәзүҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒҢ19пј•0е№ҙд»ЈгҖҒ60е№ҙд»ЈгҒ®гӮёгғЈгӮәгҒ®е…ЁзӣӣжҷӮд»ЈгҒ«гӮӘгғјгғ—гғігҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҹ·зӯҶжҷӮгҒ«гҒҜгғ–гғјгғ гӮӮйҒҺгҒҺгҒҰзөҢе–¶зҡ„гҒ«гӮӮиӢҰгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжҷӮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиә«гҒ«гҒӨгҒҫгҒ•гӮҢгӮӢи©ұгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®жӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’дёҖйғЁжҠңжӣёгҒҚгҒҷгӮӢгҖӮгҖҢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҢеӨүдәәгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«еӨүдәәгҒ®е®ўгҒҢйӣҶгҒҫгӮӢеә—гҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеҫҢиҖ…гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮ“гӮүеҸҚи«–гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—дёҖзЁ®з•°ж§ҳгҒӘгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢгҒ„гҒҰеә—еҶ…гҒ«е…ҘгӮҠгҒҘгӮүгҒ„гҖҒгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜеҝғеӨ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯгҒ§еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиҖ…гҒ®ж–№гҒҢгҖҒгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«жҖ–гҒ„гҒ—дёҚе®үгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»е®ҹйҡӣгҒ«гҒ“гӮ“гҒӘгҒҠе®ўж§ҳгҒҢзҸҫгӮҢгҒҹгҖӮгҖҢдҪ•гӮӮжіЁж–ҮгҒӣгҒҡгҒ«дәҢжҷӮй–“д»ҘдёҠгӮӮгҒ„гҒҹгҒҠе®ўж§ҳгҖҚгҖҢгӮігғјгғ’гғјд»ЈгӮ’еҖӨеҲҮгҒЈгҒҹгҒҠе®ўж§ҳгҖҚгҖҢжҜҺеӨ•гҒ®гғһгғ©гӮҪгғігӮігғјгӮ№гҒ«еә—еҶ…дёҖе‘ЁгӮ’еҠ гҒҲгҒҹгҒҠе®ўж§ҳгҖҚгҖҢеә—еҶ…гҒ§иҮӘеҲҶгҒ®гӮәгғңгғігҒ«зҒ«гӮ’гҒӨгҒ‘з„јиә«иҮӘж®әгӮ’еӣігӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒҠе®ўж§ҳгҖҚгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гҒјгҒҸгҒ®йӣ‘иЁҳеёігӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гӮӢж–№пјҲжҷ®йҖҡгҒ®зҡҶгҒ•гӮ“пјүгҖҒж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ«еҜ„гҒЈгҒҰгҒҝгҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖӮ

д»Ҡж—ҘгӮӮгҖҒжҳЁж—ҘгҒ«з¶ҡгҒ„гҒҰгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҖҚгҒ®и©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҢзҹҘз«ӢгҒ«гӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҖҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ1960е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒжқұдә¬ж–°е®ҝгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖҢгғқгғӢгғјгҖҚгҒЁгҒӢдә¬йғҪгҒ®гҖҢгӮ·гӮўгғігӮҜгғ¬гғјгғ«гҖҚгҒЁгҒӢгҖҒеҗҚеүҚгӮӮиҰҡгҒҲгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒиүІгҖ…гҒӘгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ«еҮәе…ҘгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҖҒгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒҢдҪ•гҒҹгӮӢгҒӢгҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮең°е…ғгҖҒзҹҘз«ӢгҒ«гҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ«иЎҢгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒзҗҶз”ұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҖҒзўәгҒӢи¬ӣи«ҮзӨҫгҒ®жң¬гҒ гҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒе…ЁеӣҪгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®гғ•гӮ§гӮӨгғҗгғӘгғғгғҲгғ»гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®зҙ№д»ӢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҖҢгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҖҚгҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгӮўгғ«гғҗгғјгғҲгғ»гӮўгӮӨгғ©гғјгҖҒгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҖҒгғӯгғјгғ©гғігғүгғ»гӮ«гғјгӮҜгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒгҒјгҒҸгҒҢгҒқгҒ®йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгӮўгғҗгғігӮ®гғЈгғ«гғүгҒЁгҒјгҒҸгҒҢжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгғЎгғігғҗгғјгҒ®еҗҚгҒҢйҖЈгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®гҒјгҒҸгҒҜгҖҒгӮўгғјгғҲгғ»гғҡгғғгғ‘гғјгӮ„гғ“гғ«гғ»гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒӘгҒ©гӮ’еҘҪгӮ“гҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒјгҒҸгҒ®иЎҢгҒҸгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгғһгӮ№гӮҝгғјгҒӢгӮүеҖҹгӮҠгҒҹгҖҢгҒҠгӮҢгҒҹгҒЎгҒ®гӮёгғЈгӮәзӢӮйқ’жҳҘиЁҳгҖҒгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶иӘ•з”ҹзү©иӘһгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢгӮёгғЈгӮәгӮ’еҸӢйҒ”гҒӢгӮүгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҗгғјгғҲгғ»гӮўгӮӨгғ©гғјгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгӮүгҖҒгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҒЁзҙҚеҫ—гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгӮӮд»ҠгҒ§гҒҜгҖҒгҒҠе®ўж§ҳ第1гҒ«иҖғгҒҲгҒҰгҖҒгғ¬гӮ№гӮҝгғјгғ»гғӨгғігӮ°гҒ®жј”еҘҸгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгӮҠгҖҒгғ“гғ«гғ»гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҖҒгғҒгғғгӮҜгғ»гӮігғӘгӮўгҒ®жј”еҘҸгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгӮҠгҒЁгҖҒиүІгҖ…гҒЁж°—гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
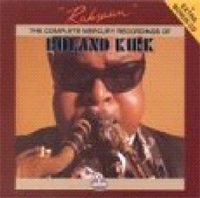
гҒқгӮ“гҒӘжҳЁд»ҠгҒ®гҖҢгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҖҒгҒјгҒҸгҒҢеә—гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢLPгғ¬гӮігғјгғүгӮ’гҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁиҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒUгҒ•гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶж–№гҒҢгҒҠиҰӢгҒҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«й јгҒҫгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶDVDгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ»гҒӢгҒ«гҒҠе®ўгӮӮгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®DVDгӮ’гғҶгғ¬гғ“гҒ§иҰіиіһгҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢдҪ•гҒЁгғӯгғјгғ©гғігғүгғ»гӮ«гғјгӮҜгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӯгғјгғ©гғігғүгғ»гӮ«гғјгӮҜгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒгғӘгғјгғүжҘҪеҷЁгӮ’3гҒӨгӮӮ4гҒӨгӮӮеҸЈгҒ«гҒҸгӮҸгҒҲгҒҰеҗҢжҷӮгҒ«йіҙгӮүгҒ—гҖҒе’Ҷе“®гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮ°гғӯгғҶгӮ№гӮҜгғ»гӮёгғЈгӮәгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгӮӮйҮЈгӮүгӮҢгҒҰгҖҒиҰӢгӮӢгҒЁгҒҜз„ЎгҒ—гҒ«иҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҚҳгҒӘгӮӢгғ©гӮӨгғ–гҒ®жҳ еғҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҪјгҒ®жј”еҘҸгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒзӢјгҒҢйҒ еҗ гҒҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮ·гғјгғігҒҢеҮәгҒҹгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӯҗдҫӣгҒҢгҒҠгӮӮгҒЎгӮғгҒ®гғ©гғғгғ‘гӮ’еҗ№гҒҚйіҙгӮүгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮ·гғјгғігҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒеҪјгҒ®жј”еҘҸгҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢеӨ§еӨүгӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еҪјгҒҢгҒ©гӮ“гҒӘгӮЁгғўгғјгӮ·гғ§гғігҒ§жҢҒгҒЈгҒҰгҖҒд»Ҡжј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒјгҒҸгҒ®еӢқжүӢгҒӘзҗҶи§ЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҪјгҒҢдҪ•гҒӢгӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеӨ§гҒҚгҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’еҶ…гҒ«з§ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гӮёгғЈгӮәгҒЁгҒ„гҒҶйҹіжҘҪгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰйҹігҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҷӮгҒ«гҒҜеӨ§еӨүзҫҺгҒ—гҒ„гғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгӮ’зҙЎгҒҺгҖҒжҷӮгҒ«гҒҜе’Ҷе“®гҒҷгӮӢгӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҖӮгҒқгӮ“гҒӘгҒөгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҒЁгҖҒеҪјгҒҢиЎЁзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиүҜгҒ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҒӢгӮүдёҚжҖқиӯ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҜд»ҠгҖҒгғӯгғјгғ©гғігғүгғ»гӮ«гғјгӮҜгҒ®гҖҢгғӯгғјгғ©гғігғүгғ»гӮ«гғјгӮҜгғ»гӮӨгғігғ»гғ‘гғӘгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®йӣ‘ж–ҮгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҢгӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚгӮ’иҒһгҒ„гҒҰдҪ•гӮ’йҖЈжғігҒҷгӮӢгҒӢгҖӮгӮ№гғҡгӮӨгғіиӘһгҒ§гҖҢзҷҪгҒ„家гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігҒ гҒқгҒҶгҒ гҒҢгҖҒгғўгғӯгғғгӮігҒ®йғҪеёӮеҗҚгҒӢгӮүжҳ з”»гӮ’жҖқгҒҶдәәгӮӮгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгғҰгғӘгҒ®иҠұгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иҠұгҒҜгҖҒжҲ‘гҒҢеҰ»гҒ®еҘҪгҒҚгҒӘиҠұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҠұгӮ’иІ·гҒҶгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜйҒҺгҒЈгҒҰз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢжҷӮеҰ»гҒ®гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгҒ§гӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гӮ’иІ·гҒ„жұӮгӮҒгҒҰд»ҘжқҘгҖҒжҲ‘гҒҢ家гҒ§гҒҜиҠұгӮ’иІ·гҒҶгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иүІгҒҜзҙ”зҷҪиүІгҒ®еӨ§ијӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҰҷгӮҠгӮӮеј·гҒҸгҖҒдёҖжң¬гҒӮгӮҢгҒ°йғЁеұӢдёӯгҒ«гҒҷгҒҢгҒҷгҒҢгҒ—гҒ•гҒҢжәҖгҒЎгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғҰгғӘгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®еұұгғҰгғӘзӯүгӮ’гӮӮгҒЎгҒ„гҒҰгӮӘгғ©гғігғҖгҒ§ж”№иүҜгҒ•гӮҢгҒҹе“ҒзЁ®гҒ§гӮӘгғӘгӮЁгғігӮҝгғ«гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүзі»гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮд»Ҡж—Ҙжң¬гҒ§дёҖз•Әдәәж°—гҒ®гҒӮгӮӢеҲҮиҠұгҒ®гғҰгғӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«дәҢз•Әзӣ®гҒҜгғһгғ«гӮігғқгғјгғӯгҒЁгҒ„гҒҶи–„гҒ„гғ”гғігӮҜгҒ®гғҰгғӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғҰгғӘгҒЁгҒ„гҒҶиҠұгҒҜж°ҙгҒ•гҒҲгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжӣҝгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®гҒӨгҒјгҒҝгҒҢй–ӢиҠұгҒҷгӮӢеј·гҒ„з”ҹе‘ҪеҠӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒІгҒЁгҒӨеҺ„д»ӢгҒӘгҒ®гҒҜиҠұзІүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒӨгҒҸгҒЁеҸ–гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮж“ҰгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж°ҙжҙ—гҒ„гҒ—гҒҰгӮӮгҒ гӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ¬гғ гғҶгғјгғ—гӮ’дҪҝгҒҶгҒ®гҒҢжҜ”ијғзҡ„иүҜгҒ„гҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гҒ®иҠұиЁҖи‘үгҒҜй«ҳиІҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“еҲҶгҒ“гҒ®иҠұгӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гҒ®иҠұгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гҒ®иҠұгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжё…жҘҡгҒ§иү¶гӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒ
жңқгҒ®е…үгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮ„гҒ•гҒ—гҒҸгҖҒгҒӮгҒӢгӮӢгҒ„гҖҒ
иӢҘи‘үгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиҗҢгҒҲеҮәгҒ§гҒҰгҒҝгҒҡгҒҝгҒҡгҒ—гҒ„гҖҒ
жіүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҫ„гӮ“гҒ зһігӮ’зҙ зӣҙгҒ«й–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгҒҫгҒІгӮӢгҒ®иЎ—гӮ’гӮҸгҒҹгҒ—гҒЁгҒ„гҒЈгҒ—гӮҮгҒ«гҒӮгӮҶгӮҖгҖҒ
еӨ•гӮӮгӮ„гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§е„ӘгҒ—гҒҸгӮҸгҒҹгҒ—гӮ’гҒӨгҒӨгӮ“гҒ§гҒҸгӮҢгӮӢгҖҒ
жҡ—гҒ„еҪұгҒ§гҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гҒ®иЎҢгҒҸйҒ“гӮ’з…§гӮүгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖҒ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гҒ®гҒ•гӮҸгӮ„гҒӢгҒӘйўЁгҖҒзҶұгҒ„жҒҜ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гҒ®йЎҳгҒ„гҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒ®жҖқгҒ„
гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҖҒйўЁгҒ®гҒөгҒҸгҒҹгҒігҒ«гҖҒ
гҒӮгҒӘгҒҹгӮ’жҖқгҒҶгҖҒгҒ©гҒ“гҒ«гҒ„гҒҰгӮӮгҖҒ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒҸгҒЎгҒҘгҒ‘гҒҷгӮӢгҖҒиү¶гӮ„гҒӢгҒӘйҰҷгӮҠгҒ®гҒҷгӮӢгҒҹгҒігҒ«гҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜиӢҘи‘үгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиҗҢгҒҲеҮәгҒ§гҒҰгҒҝгҒҡгҒҝгҒҡгҒ—гҒ„гҖҒ
жіүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҫ„гӮ“гҒ зһігӮ’зҙ зӣҙгҒ«й–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒ
гӮ«гӮөгғ–гғ©гғігӮ«гҒ®иҠұгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжё…жҘҡгҒ§иү¶гӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒ
жңқгҒ®е…үгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮ„гҒ•гҒ—гҒҸгҖҒгҒӮгҒӢгӮӢгҒ„гҖӮ


гғ»гӮәгғјгғҲгҒҢиЁҖи‘үгҒ«зӘ®гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒҫгҒҡгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮдёҖдәәгҒ®гғ•гӮЎгғігҒ«гҖҢгҒқгӮ“гҒӘгҒ«й…”гҒЈгҒұгӮүгҒЈгҒҰгӮҲгҒҸжј”еҘҸгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒӯгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгӮәгғјгғҲгҒҜгҒ“гҒҶзӯ”гҒҲгҒҹгҖӮгҖҢгҒқгӮҢгҒҜгҒӯгҖҒжҷ®ж®өгҒӢгӮүй…”гҒЈжү•гҒЈгҒҰз·ҙзҝ’гҒ—гҒҰгӮӢгҒӢгӮүгҒ•пјҒгҖҚ
гғ»гӮәгғјгғҲгҒҜгҒӮгӮӢж—ҘгҒ®еҚҲеҫҢгҖҒгғҖгғјгӮҜгғ»гӮ№гғјгғ„гӮ’зқҖгҒҰгӮёгғ гғ»гӮўгғігғүгғ»гӮўгғігғҮгӮЈгғјгӮәгғ»гғҗгғјгҒ«зҸҫгӮҢгҒҹгҖӮзҷҪгҒ„гӮ·гғЈгғ„гҒ«гғҚгӮҜгӮҝгӮӨгӮ’гҒ—гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮәгғјгғҲгҒҜжҳјй–“гҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒҜгӮігғјгғҮгғҘгғӯгӮӨгҒ®гӮәгғңгғігҒ«йҮҺзҗғгҒ®гӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж јеҘҪгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҖҢгӮҲгҒҶгӮәгғјгғҲгҖҚгҒЁиӘ°гҒӢгҒҢе°ӢгҒӯгҒҹгҖӮгҖҢгҒ“гӮ“гҒӘзңҹгҒЈжҳјй–“гҒӢгӮүгӮҒгҒӢгҒ—иҫјгӮ“гҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„гҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮ“гҒ гӮҲпјҹгҖҚгӮәгғјгғҲгҒҜгғҚгӮҜгӮҝгӮӨгӮ’гҒ—гӮҒзӣҙгҒ—гҖҒйҡҷй–“гҒ®гҒӮгҒ„гҒҹжӯҜгӮ’гҒ«гҒЈгҒЁиҰӢгҒӣгҒҰ笑гҒЈгҒҹгҖӮгҖҢдҝәгҒ«гӮӮгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҖӮзӣ®гҒҢиҰҡгӮҒгҒҹгӮүгҒ“гӮ“гҒӘж јеҘҪгҒ гҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҖҚ
дёҠгҒ®дәҢгҒӨгҒ®ж–ҮгҒҜгҖҒгғ“гғ«гғ»гӮҜгғӯгӮҰгҒҢжӣёгҒ„гҒҹгҖҢгӮёгғЈгӮәгғ»гӮўгғҚгӮҜгғүгғјгғ„гҖҚжқ‘дёҠжҳҘжЁ№иЁігҒ«ијүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҖёи©ұгҒ®дёҖйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮәгҒҜй…’гҒ•гҒҲйЈІгӮ“гҒ§гҒ„гӮҢгҒ°гҒ”ж©ҹе«ҢгҒ®гҖҒгҒҹгҒ„гҒёгӮ“гҒІгҒЁгҒ®иүҜгҒ„гӮёгғЈгӮәгғһгғігҒ§гҖҒдҪңжӣІгҒЁгҒӢгҖҒз·ЁжӣІгҖҒгғҗгғігғүгҒ®гғӘгғјгғҖгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдәӢгҒ«гҒҜй–ўеҝғгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгғҶгғҠгғјгғ»гӮөгғғгӮҜгӮ№1жң¬гҒ§гӮёгғЈгӮәгӮ’еҗ№гҒ„гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ®жј”еҘҸгҒҜгҖҒеҪјгҒ®дәәжҹ„гӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҰгҒҹгҒ„гҒёгӮ“жҡ–гҒӢгҒ„гҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гғҶгғҠгғјгӮ’еҗ№гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢз”ҹгҒҚгҒҢгҒ„гҒ®иҒ·дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮ“гҒӘеҪјгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгҖҒгҒјгҒҸгҒҜгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮәгғјгғҲгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҒ©гӮҢгӮӮгҒ“гӮҢгӮӮгҒҝгҒӘеҘҪгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢеҘҪгӮ“гҒ§иҒһгҒҸжӣІгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҪјгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮ
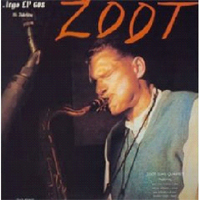
гғ»гӮҜгғғгӮӯгғі
1961е№ҙгҒ«гғӯгғігғүгғігҒ®гғӯгғӢгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгғ»гӮҜгғ©гғ–гҒ§гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒ®жһҜи‘үгҒ®жј”еҘҸгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒ®жңҖгӮӮеҘҪгҒҚгҒӘжһҜи‘үгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»гӮәгғјгғҲ
9:20гӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«пјӣгӮәгғјгғҲгҒ®еҝ«иӘҝгҒӘгғҶгғҠгғјгҒҢеҝғең°гӮҲгҒ„
гғңгғҳгғҹгғӨгғ»гӮўгғ•гӮҝгғјгғ»гғҖгғјгӮҜпјӣгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜзҸҚгҒ—гҒҸгӮўгғ«гғҲгғ»гӮөгғғгӮҜгӮ№гҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒҫгҒҹгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮ

гғ»гӮӨгғ•гғ»гӮўгӮӨгғ гғ»гғ©гғғгӮӯгғј
гӮӨгғ•гғ»гӮўгӮӨгғ гғ»гғ©гғғгӮӯгғјгҖҒгғҰгғјгӮўгғ»гғһгӮӨгғ»гӮЁгғҙгғӘгӮ·гғігӮ°гҒ“гҒ®пј’жӣІгҒ§гҒ®гӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгҒҜгҒ„гҒӨиҒһгҒ„гҒҰгӮӮеҝғгҒҢе’ҢгӮҖгҖӮ
гғ»гӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮәгғ»гӮўгғігғүгғ»гӮ¶гғ»гӮ¬гғјгӮ·гғҘгӮӨгғігғ»гғ–гғ©гӮ¶гғјгӮә
гӮөгғһгғјгӮҝгӮӨгғ пјӣгғҶгғҠгғјгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гӮёгғ§гғјгғ»гғ‘гӮ№гҒ®гӮ®гӮҝгғјгӮӮе…үгӮӢгҖӮ
гғ»гғҰгӮҝгғ»гғ’гғғгғ—гғ»гӮҰгӮЈгӮәгғ»гӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮә
гӮігғјгғҲгҒ«гҒҷгҒҝгӮҢпјӣгҒ„гҒӨиҒһгҒ„гҒҰгӮӮгҒ“гҒ®е“Җж„ҒгҒҜгҒҹгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гӮәгғјгғҲгғ»гӮ·гғ гӮәгҒ«гҒҜгҖҒгӮўгғ«гғҗгғ гҖҢгғҖгӮҰгғігғ»гғӣгғјгғ гҖҚгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ гҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„жӣІгҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
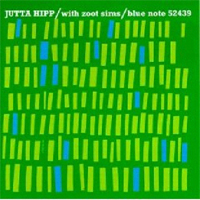


еүЈиұӘдҪң家гҒ®дә”е‘іеә·зҘҗгҒ•гӮ“гҒҢжӣёгҒ„гҒҹжң¬гҒ«гҖҒгҖҢдә”е‘іеә·зҘҗгҖҖйҹіжҘҪе·ЎзӨјгҖҚгҖҢдә”е‘іеә·зҘҗгҖҖгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘйҒҚжӯҙгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒҢж–°жҪ®ж–Үеә«гҒ§еҮәгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮйҹіжҘҪе·ЎзӨјгҒ®гҒ»гҒҶгҒҜгҒ®гҒЎгҒ«гҖҢгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒЁи“„йҹіж©ҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйЎҢеҗҚгҒ§и§’е·қжҳҘжЁ№дәӢеӢҷжүҖгӮҲгӮҠгғ©гғігғҶгӮЈгӮЁеҸўжӣёгҒЁгҒ—гҒҰеҶҚеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йҹіжҘҪе·ЎзӨјгҒ®дёӯгҒ§дә”е‘іеә·зҘҗгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒгҒҹгҒЈгҒҹпј‘жӣІгҒ гҒ‘йҹіжҘҪгӮ’йҒёгҒ¶гҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒ“гҒ®гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІз¬¬пј‘пј”з•Әе¬°гғҸзҹӯиӘҝпјҲдҪңе“Ғ131пјүгӮ’йҒёгҒ¶гҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮи«ҰиҰігҒ®жңҖгӮӮжҫ„гӮ“гҒ еўғең°гҒҢгҒ“гҒ®дҪңе“ҒгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҖӮгҒјгҒҸгҒҜгҒқгӮҢгҒҫгҒ§ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгӮ’гҖҒжҠҪиұЎзҡ„гҒЁгҒӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒ«йқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒӢиЁҖгҒЈгҒҰйҒҝгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҖҒиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒӢгӮү10е№ҙгҒҸгӮүгҒ„еүҚгҒ®и©ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒ®еҒ¶з„¶гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҜгҒҹгҒЈгҒҹдёҖжһҡејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҒ®LPгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖҒгҒқгӮҢгӮӮгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІз¬¬пј‘пј”з•Әе¬°гғҸзҹӯиӘҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮSUPRAPHONгӮҲгӮҠеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒгӮ№гғЎгӮҝгғҠеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ«гӮҲгӮӢ1970е№ҙйҢІйҹігҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒ«гҖҒжҷӮгҖ…еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҜиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒеӨңдёӯгҒ«гҖҒе‘ЁгӮҠгӮ’ж°—йҒЈгҒЈгҒҰйҹігӮ’гҒ„гҒӨгӮӮгӮҲгӮҠзөһгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҲҶйӣҶдёӯгҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҶ’й ӯгҒ®еҮәгҒ гҒ—гҒӢгӮүиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®зҘҲгӮҠгҒ®еЈ°гҒ гҖӮгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®йҹіжҘҪгҒҢеӨ©дҪҝгҒ®зҘҲгӮҠгҒ®йҹіжҘҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®йҹіжҘҪгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«дәәй–“гҒ®зҘҲгӮҠгҒ®йҹіжҘҪгҒ гҖӮи«ҰиҰігҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮҲгҒ„гҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҜгҖҒеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒе№ҫеӨҡгҒ®еӣ°йӣЈгӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҒҰгҖҒеңЁгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҝғеўғгҒ«еҲ°йҒ”гҒ—гҒҹдәәгҒ®гҖҒйқҷгҒӢгҒ§гҖҒеј·гҒҸгҖҒ敬иҷ”гҒӘзҘҲгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸжҫ„гӮ“гҒ гҖҒеҝғжҙ—гӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйҹіжҘҪгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҒҹгҒЈгҒҹпј”дёҒгҒ®ејҰжҘҪеҷЁгҒ§дҪ•гҒЁеәғгҒ„еӨ§гҒҚгҒӘдё–з•ҢгӮ’иЎЁзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒ“гҒ®ж„ҹеӢ•гҒҢгҒјгҒҸгӮ’ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҒ®гҒЁгӮҠгҒ“гҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ
гҒ“гҒҶгҒӘгӮӢгҒЁд»–гҒ®жј”еҘҸиҖ…гҒ®пј‘пј”з•ӘгҒҢиҒһгҒҚгҒҹгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгӮӮгҒҶLPгҒҜзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§CDгҒ§иүІгҖ…гҒЁжҺўгҒ—гҒҹгҖӮгӮўгғ«гғҗгғігғҷгғ«гӮҜеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғҗгғӘгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғҷгғ«гғӘгғіеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғ–гғғгӮ·гғҘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғӯгӮјгғјеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғ–гӮҝгғҡгӮ№гғҲеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғ¬гғҠгғјеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғЎгғҮгӮЈгғҒеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгӮ¬гғ«гғҚгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҖҒгғҸгғјгӮІгғіеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒӘгҒ©гҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨўдёӯгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘжј”еҘҸгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®иЎЁзҸҫгҒ®йҒ•гҒ„гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гӮ„гҖҒеҗ„еӣЈдҪ“гҒ®зү№еҫҙгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еҘҪгҒҝгӮӮзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®пј‘пј’з•Әд»ҘйҷҚгҒ®еҫҢжңҹеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҒ«зҡ„гӮ’зөһгҒЈгҒҰиҒһгҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҖӮеј·гҒҸеј•гҒӢгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгӮўгғҖгғјгӮёгғ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒҢжӣёгҒ„гҒҹгӮўгғҖгғјгӮёгғ§гҒҜжң¬еҪ“гҒ«зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҖӮ第12з•ӘгҒ§гҒҜ第2жҘҪз« гҒ«еӨүеҘҸжӣІгҒЁгҒ—гҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ第13з•ӘгҒ§гҒҜ第5жҘҪз« гҒҢжңүеҗҚгҒӘгӮ«гғҙгӮЎгғҶгӮЈгғјгғҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢз§ҒгҒҢжӣёгҒ„гҒҹдёҖз•Әж„ҹеӢ•зҡ„гҒӘжӣІгҖҚгҒЁгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғіиҮӘиә«гҒҢиЁҖгҒЈгҒҹгҖҒзҹӯгҒ„еҳҶгҒҚгҒ®гӮ«гғҙгӮЎгғҶгӮЈгғјгғҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ第14з•ӘгҒҜжӣІе…ЁдҪ“гҒҢгҖҒжңҖгӮӮзҘһз§ҳзҡ„гҒ§гҖҒжңҖгӮӮжё…жҫ„гҒ§гҖҒжңҖгӮӮйқһең°дёҠзҡ„гҒӘеӣӣйҮҚеҘҸгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮ第4жҘҪз« гҒҢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҖӮ第15з•ӘгҒ§гҒҜ第3жҘҪз« гҒҢгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢз—…зҷ’гҒҲгҒҹиҖ…гҒ®гҖҒзҘһгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҒ–гҒӘгӮӢж„ҹи¬қгҒ®гҒҶгҒҹгҖӮгғӘгғҮгӮЈгӮўж—Ӣжі•гҒ«гӮҲгӮӢгҖӮгҖҚгҒЁи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеәғгҒ„еҝғгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ第16з•ӘгҒ§гҒҜ第3жҘҪз« гҒҢгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж·ұгҒ„жӮІгҒ—гҒҝгҒ«еЈ°гӮӮгҒӘгҒҸж¶ҷгҒ—гҒҰгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе–ңгҒігҒЁгҒӢгҖҒж„ҹи¬қгҒЁгҒӢгҖҒеҳҶгҒҚгҒЁгҒӢгҖҒжӮІгҒ—гҒҝгҒЁгҒӢгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҒ“гҒ®гӮўгғҖгғјгӮёгғ§гҒ§иЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮӮгҒҶгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘеЈ°гӮ’еҮәгҒҷдәӢгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒжң¬еҪ“гҒ«йқҷгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ„гҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸиүІгҖ…гҒӘејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгӮ’еҘҪгӮ“гҒ§иҒһгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒдә”е‘іеә·зҘҗгҒ•гӮ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІз¬¬пј‘пј”з•Әе¬°гғҸзҹӯиӘҝпјҲдҪңе“Ғ131пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ


гҒјгҒҸгҒҢејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгӮ’иҒһгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜжҳЁж—Ҙиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғіпҪҘгӮўгғ«гғҗгғігғҷгғ«гӮҜпјіпјұгҖҒгӮ№гғЎгӮҝгғҠпјіпјұгҖҒгӮёгғҘгғӘгӮўгғјгғүпјіпјұгҖҒгғҷгғ«гғӘгғіпјҲгӮ№гӮәгӮұпјүпјіпјұгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢжҙ»иәҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒјгҒҸгӮӮгӮўгғ«гғҗгғігғҷгғ«гӮҜпјіпјұгӮ„гӮ№гғЎгӮҝгғҠпјіпјұгӮ’еҘҪгӮ“гҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒӢгӮүд»ҠгӮӮз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжң¬гҒ®гғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ·гғ§гғғгғ—гғ»гғ–гғғгӮҜгӮӘгғ•гӮ’иҰӢгҒҰгҒҫгӮҸгӮӢгҒ®гҒҢгҒјгҒҸгҒ®жҘҪгҒ—гҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиұҠз”°гҒ«ж–°гҒ—гҒҸеә—гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§еҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹжҷӮгҒ«гҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫпјЈпјӨгӮігғјгғҠгғјгҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹ3жһҡгҒҢгғҗгғӘгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®4з•ӘгҖҒ5з•ӘгҖҒ6з•ӘгҒЁ10з•ӘгҖҒ12з•ӘгҒҠгӮҲгҒі13з•ӘгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ гҒЈгҒҹгҖӮе®үгҒ•гҒ«гҒӨгӮүгӮҢгҒҰгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’иІ·гҒ„еҸ–гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®жҷӮгҒ«гҒҜгғҗгғӘгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶеӣЈдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒжӯЈзӣҙгҒ«иЁҖгҒЈгҒҰгҒјгҒҸгҒҜзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰй©ҡгҒ„гҒҹгҖӮд»ҠгҒҫгҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ©гҒ®жј”еҘҸгҒЁгӮӮйӣ°еӣІж°—гҒҢйҒ•гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҜгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®еҲқжңҹгҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜд»ҠгҒҫгҒ§иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠиҒһгҒ„гҒҰгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгғҗгғӘгғӘгҒ®жј”еҘҸгҒ§иҒһгҒҸ4з•ӘгҖҒ5з•ӘгҖҒ6з•ӘгҒҜгҖҒгҒҳгҒӨгҒ«гҒ—гҒӘгӮ„гҒӢгҒ§жҹ”гӮүгҒӢгҒҸгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҷгғігҒ®еҲқжңҹгҒ®иӢҘгҖ…гҒ—гҒ„ж„ҹиҰҡгӮ’гҒҹгҒ„гҒёгӮ“иҰӢдәӢгҒ«иЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮжҖқгҒҶгҒ«йҹіжҘҪгҒ®иЎЁзҸҫгҒҜгҖҒжҠҖиЎ“зҡ„гҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ«жј”еҘҸгҒҷгӮӢдәәгҒ®еҝғгҒ®жҸәгӮүгҒҺгҒҢдјқгӮҸгҒЈгҒҰгҒ“гҒқгҖҒдәәгҒ«ж„ҹеӢ•гӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮгғҗгғӘгғӘгҒ®жј”еҘҸгҒҜжұәгҒ—гҒҰзҗҶеұҲгҒЈгҒҪгҒҸгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘ然дҪ“гҒ§йҹіжҘҪгҒ®е–ңгҒігҒ«гҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮүиЁҖгҒ„йҒҺгҒҺгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгҒҢд»–гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒзү№гҒ«12з•ӘгҒ®з¬¬2жҘҪз« гҒ®гӮўгғҖгғјгӮёгғ§гҖҒ13з•ӘгҒ®гҖҢеҳҶгҒҚгҒ®гӮ«гғҙгӮЎгғҶгӮЈгғјгғҠгҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢ第5жҘҪз« гҒ®жј”еҘҸгҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒ®гҒҠж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дёҖгҒӨж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜпјЈпјӨгҒ®йҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгӮЁгӮ№гғҲгғҹгғігӮ№гӮҝгғјгҒ®йҹіжәҗгӮҲгӮҠгғ“гӮҜгӮҝгғјгҒҢ20bit SUPER CODING гҒЁгҒ„гҒҶж–№ејҸгҒ§CDеҢ–гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҹігҒ®ијӘйғӯгҒҜгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒйҹҝгҒҚгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгӮӢгҖӮгғҜгғ«гӮҝгғјпҪҘгғҗгғӘгғӘгҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігҒҢгӮ„гӮ„зЎ¬гҒҸиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҡгҒЈгҒЁгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе…ҲжңҲдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдёӯеҸӨгғ¬гӮігғјгғүгҒӮгҒ•гӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҒӘгӮ“гҒЁгғҗгғӘгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ®LPгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ1968е№ҙгҒ«гӮӯгғігӮ°гғ¬гӮігғјгғүгӮҲгӮҠзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒгғҗгғӘгғӘеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ®иҠёиЎ“гғ»гғҷгғјгғҲгғјгғҷгғіејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІе…ЁйӣҶ第1е·»гҒ§1з•ӘгҒЁ2з•ӘгҒ®жј”еҘҸгҒҢйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮжңҹеҫ…гҒ«иғёгӮ’иҶЁгӮүгҒҫгҒӣгҒӘгҒҢгӮүгғ¬гӮігғјгғүгҒ«йҮқгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҹзһ¬й–“гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӢгӮүжөҒгӮҢгҒҰгҒҸгӮӢйҹіжҘҪгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®йҹігҒ гҒЁгҒјгҒҸгҒҜжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгӮҰгӮЈгғјгғігғ•гӮЈгғ«гӮ’йҖЈжғігҒ•гҒӣгӮӢгҖҒгҒ—гҒӘгӮ„гҒӢгҒ§жҹ”гӮүгҒӢгҒҸйҹҝгҒҚгҒ®иүҜгҒ„йҹіжҘҪгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒјгҒҸгҒҜе®үеҝғгҒҷгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҒҫгҒҹдёҖгҒӨгӮ„гӮӢгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҢеў—гҒҲгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢгҖӮ

жҳ”гҖ…гҒјгҒҸгҒҢгҒҫгҒ дјҡзӨҫгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҰж•°е№ҙзӣ®гҒ гҒЈгҒҹй ғгҖҒиҮӘеӢ•и»ҠгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢж–°гҒ—гҒ„жЁ№и„ӮйғЁе“ҒгҒ®и©ҰйЁ“и©•дҫЎгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮй–ӢзҷәгҒ—гҒҹж–°и»ҠгӮ’йҮҸз”ЈгҒ§дҪңгӮҠеҮәгҒ—гҒҰж•°ж—ҘгҒҢзөҢгҒЈгҒҹй ғгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§з¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹиүҜгҒ„еӨ©ж°—гҒҢеҙ©гӮҢгҒҰгҖҒзҢӣзғҲгҒӘйӣЁгҒҢйҷҚгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ«е®ҢжҲҗи»ҠзҪ®гҒҚе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒӮгҒЈгҒҹж–°и»ҠгҒ®гғӘгғӨгғ»гӮігғігғ“гғҚгғјгӮ·гғ§гғігғ»гғ©гғігғ—гӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгӮўгӮҜгғӘгғ«гӮұгғјгӮ№гҒ«гҒІгҒігҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒӘгҒңд№…гҒ«гғӘгғӨгӮігғігғ“гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҢжҖҘгҒ«еүІгӮҢгҒ гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢеҺҹеӣ иҝҪжұӮгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
зҙҚе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹйғЁе“ҒгҒ®иҰіеҜҹгҖҒйғЁе“ҒгҒҢгғңгғҮгғјгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒӢгӮүи»ҠгҒ®е®ҢжҲҗгҒҫгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғігҒ«гҒҜгӮҠд»ҳгҒ„гҒҰгҒ®иҰіеҜҹгҒӘгҒ©гӮ’гҒ—гҒҰеҺҹеӣ иҝҪжұӮгӮ’гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзӯ”гҒҲгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒҡжүӢи©°гҒҫгӮҠзҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҜҫзӯ–дјҡиӯ°гҒ®дёӯгҒ§иӘ°гҒӢгҒҢгҖҒдёҚе…·еҗҲзҷәз”ҹгҒ®дёҚиүҜгҒ®жҺЁз§»гӮ’и§ЈжһҗгҒ—гҒҹгӮүгҖҒйӣЁгҒҢйҷҚгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒӢгӮүжҖҘгҒ«дёҚе…·еҗҲгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮўгӮҜгғӘгғ«жЁ№и„ӮгҒҜж°ҙеҲҶгҒЁгҒӢж№ҝеәҰгҒ«ејұгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒқгҒ®еӣ жһңй–ўдҝӮгӮ’е®ҹйЁ“гҒӣгӮҲгҒЁиЁҖгҒ„еҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҜзҗҶеұҲгҒ«еҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ§гҒҜгҒ»гҒӢгҒ«гҒ©гӮ“гҒӘеҺҹеӣ гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӯ°и«–гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзөҗеұҖе®ҹйЁ“гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҒ„гҒҸгӮүгӮ„гҒЈгҒҰгӮӮеүІгӮҢгҒҜеҶҚзҸҫгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
ж°—гӮ’еҸ–гӮҠзӣҙгҒ—гҒҰгҖҒгӮӮгҒҶдёҖеәҰи»ҠгҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒе®ҢжҲҗи»ҠгғӨгғјгғүгҒ«еҮәгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®е·ҘзЁӢгӮ’иҰіеҜҹгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮ¬гӮҪгғӘгғігӮ’и»ҠгҒ«иЈңзөҰгҒҷгӮӢе·ҘзЁӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜгғӘгғӨгҒ®гғҠгғігғҗгғјгғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®иЈҸгҒ«гӮ¬гӮҪгғӘгғігҒ®иЈңзөҰеҸЈгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ§дҪңжҘӯиҖ…гҒҢгӮ¬гӮҪгғӘгғігӮ’е…ҘгӮҢгҒҹеҫҢгҒ§гҖҒгғҺгӮәгғ«гӮ’гҒҜгҒҡгҒҷжҷӮгҒ«гӮ¬гӮҪгғӘгғігҒҢ1ж»ҙгҒҹгӮҢгҒҰгӮўгӮҜгғӘгғ«гӮ«гғҗгғјгҒ«жөҒгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдҪңжҘӯиҖ…гҒ«гҒ“гҒ®гӮ„гӮҠж–№гҒҜгҒ„гҒӨгҒӢгӮүгҒӢгҒЁе°ӢгҒӯгӮӢгҒЁгҖҒиҮӘеҲҶгҒҜжңҖиҝ‘гҒ“гҒ®дҪңжҘӯгҒ«д»ҳгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеүҚд»»иҖ…гҒ«гӮ„гӮҠж–№гӮ’иЁҠгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒиҮӘеҲҶгҒҜгӮ¬гӮҪгғӘгғігҒҢгҒҹгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гӮҰгӮЁгӮ№гӮ’гғҺгӮәгғ«гҒ«еҪ“гҒҰгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮдәӨд»ЈгҒ—гҒҹжҷӮжңҹгӮӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©йӣЁгҒҢйҷҚгӮҠеҮәгҒ—гҒҹжҷӮжңҹгҒЁйҮҚгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒӘгӮүгҒ°еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҖҒгҒ•гҒЈгҒқгҒҸеҶҚзҸҫе®ҹйЁ“гӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеҗҢгҒҳжүҖгҒҢе®ҹйЁ“е®ӨгҒ§гӮӮеүІгӮҢгӮ’зҷәз”ҹгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢеҺҹеӣ гҒЁзү№е®ҡгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®зөҢйЁ“гҒ§гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘж•ҷиЁ“гӮ’еӯҰгӮ“гҒ гҒҢгҖҒгҒӘгҒӢгҒ§гӮӮгҖҒдәәй–“гҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®зөҢйЁ“гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиүІгҖ…гҒЁи§ЈйҮҲгҒ—зҗҶи§ЈгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒ“гҒЁиҮӘиә«гҒҜеӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ®еҲқжңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒқгҒ®зҗҶи§ЈгҒҢиӘӨгҒЈгҒҹзҗҶи§ЈгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«гҒҷгӮӢгҒ«гҒҜдҪ•гҒҢеӨ§еҲҮгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’еј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҡзҗҶеұҲпјҲгҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶзҗҶеұҲгҒЁгҒҜгҖҒдҪ“зі»еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹзҗҶи«–гҒЁгҒӢгҖҒеӯҰе•ҸгҒ®ж„Ҹе‘іпјүгҒ«еҗҲгӮҸгҒӘгҒ„дәӢгҒҜиө·гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҮӘеҲҶгҒҢжҖқгҒ„гҒӨгҒҚгҒ§иүІгҖ…гҒІгӮүгӮҒгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҢзҗҶеұҲгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’еҶ·йқҷгҒ«жӨңиЁјгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж…ӢеәҰгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲи©ұгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҶұеҠӣеӯҰгҒЁгҒ„гҒҶеӯҰе•ҸгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгӮЁгғігӮёгғігҒҜзҷәжҳҺгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒзҶұеҠӣеӯҰгҒҢзҷәйҒ”гҒ—гҒҹгҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҖҒгӮЁгғігӮёгғігҒ®жҖ§иғҪгҒҢи‘—гҒ—гҒҸеҗ‘дёҠгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮжҠҖиЎ“иҖ…гҒҜеҹәзӨҺзҹҘиӯҳгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁиә«гҒ«гҒӨгҒ‘гҖҒзҗҶеұҲгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮж¬ЎгҒ«зү©гҒҜжӯЈзӣҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖӮзҸҫең°гҒ§зҸҫзү©гӮ’гҒ—гҒӨгҒ“гҒ„гҒҸгӮүгҒ„гҒ«иҰіеҜҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж…ӢеәҰгҒҢйҮҚиҰҒгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“д»ҠгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢиө·гҒҚгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®еүІгӮҢгҒ®з ҙйқўгӮ’иҰіеҜҹгҒҷгӮҢгҒ°гҒ“гӮҢгҒҢеҝңеҠӣгҒ«гӮҲгӮӢеүІгӮҢгҒӢгҖҒз–ІеҠҙгҒ«гӮҲгӮӢеүІгӮҢгҒӢгҖҒгҒ“гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҪгғ«гғҷгғігғҲгҒ«гӮҲгӮӢеүІгӮҢгҒӢгҒҜеҲӨеҲҘгҒ§гҒҚгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«йҖІжӯ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ—гҖҒжҠҖиЎ“иҖ…гҒ®йӯӮгӮӮе…Ҳиј©гҒӢгӮүеҫҢиј©гҒёгҒЁеҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҢгӮҢгҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҒјгҒҸгҒ®и¶Је‘ігҒ§гҒӮгӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®дё–з•ҢгӮ’иҰ—гҒ„гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеӢқжүӢгҒҢйҒ•гҒ„гҒЁгҒҫгҒ©гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘйӣ‘иӘҢгӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҖҒзү©гӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®жҠҖиЎ“зҡ„гҒӘжң¬йҹіпјҲиӢҰеҠҙи©ұпјүгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҒ—гҖҒйӣ‘иӘҢгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮ第3иҖ…гҒҢжӨңиЁјгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ гҒӢгӮүеӯҰе•ҸгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮиҮӘеҲҶгҒ§зӣҙжҺҘдҪ“йЁ“гҒҷгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢдҝЎз”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ’гғғгғҒгӮігғғгӮҜгҒ®д»ЈиЎЁдҪңгӮөгӮӨгӮігҒЁгҒӢгҖҒйіҘгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҳ з”»гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒйқһеёёгҒ«з·»еҜҶгҒ«иЁҲз®—гҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гғҲгғјгғӘгғјгҒҢеұ•й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҪ•ж°—гҒӘгҒ„е ҙйқўгҒҢеҫҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«зҷ»е ҙдәәзү©гҒ®жҖ§ж јжҸҸеҶҷгҒҢй®®гӮ„гҒӢгҒ§гҖҒзҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮеҚ°иұЎзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹдҪңе“ҒгҒЁдёҰгҒ®дҪң家гҒҢжӣёгҒ„гҒҹе®үзү©гғүгғ©гғһгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜдҪ•гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҖӮиүҜгҒҸеҲӨгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒ“гҒ«зҷ»е ҙгҒҷгӮӢдәәзү©гҒҢгҖҒеӯҳеңЁгҒҷгӮӢдәәгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒдәәж јгҒ«зҹӣзӣҫгҒҜз„ЎгҒ„гҒӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮз·»еҜҶгҒӘиЁҲз”»гҒ§ж®әдәәгӮ’зҠҜгҒ—гҒҹиҖ…гҒҢгҖҒж¬ЎгҒ«гҒҜгҖҒйҖҡгӮҠйӯ”зҡ„ж®әдәәгӮ’зҠҜгҒҷгҒ®гҒ§гҒҜгҖҒеҗҢдёҖзҠҜгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иЎҢеӢ•гҒ«зҹӣзӣҫгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°дҪң家гҒҜгҖҒзҷ»е ҙдәәзү©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒқгҒ“гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„йғЁеҲҶгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘи¶Је‘ігҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘйЈҹгҒ№зү©гҒҜдҪ•гҒӢгҖҒдј‘гҒҝгҒҜдҪ•гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢзӯүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮжғіеғҸгӮ’гӮҒгҒҗгӮүгҒӣгҒҰгӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’дҪңгӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гҒјгҒҸгҒҜдҪң家гҒ®гғӯгғҗгғјгғҲгғ»гғ‘гғјгӮ«гғјгҒҢжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢз§Ғз«ӢжҺўеҒөгӮ№гғҡгғігӮөгғјгғ»гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®ж„ӣиӘӯиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1дҪңзӣ®гҒ®гҖҢгӮҙгғғгғүгӮҰгғ«гғ•гҒ®иЎҢж–№гҖҚгҒӢгӮү27дҪңзӣ®гҒ®гҖҢгғҸгӮ¬гғјгғһгӮ¬гғјгӮ’е®ҲгӮҢгҖҚгҒҫгҒ§гҒҜиӘӯз ҙгҒ—гҒҹгҖӮжңҖж–°дҪңгҒҜ34дҪңзӣ®гҒ®гҖҢгғүгғӘгғјгғ гӮ¬гғјгғ«гҖҚгҒҫгҒ§ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҷгҒ§гҒ«зҝ»иЁігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«гҒҜгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еүҜиӘӯжң¬гҒҫгҒ§гҒҢеҮәжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢгӮ№гғҡгғігӮөгғјгӮ’иҰӢгӮӢдәӢе…ёгҖҚзҷ»е ҙдәәзү©гҒ®гғҗгӮӨгӮӘгӮ°гғ©гғ•гӮЈгғјгҒӢгӮүгғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғігҖҒдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢ家гӮ„иЎ—гҒ®зҙ№д»ӢгҒӘгҒ©гҖҒиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§еҪјгӮүгғ»еҪјеҘігӮүгҒҢе®ҹеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйҢҜиҰҡгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҖҢгӮ№гғҡгғігӮөгғјгҒ®ж–ҷзҗҶгҖҚгҒ“гӮҢгҒҜгӮ№гғҡгғігӮөгғјгғ»гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ§гҒ®йЈҹдәӢгӮ’гҒҷгӮӢе ҙйқўгӮ’жҠңжӣёгҒҚгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®ж–ҷзҗҶгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒи§ЈиӘ¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒ•гӮүгҒ«гғ¬гӮ·гғ”гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҠгҒҫгҒ‘гҒ«гғңгӮ№гғҲгғігӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹе®ҹеңЁгҒҷгӮӢгғ¬гӮ№гғҲгғ©гғігҒ®зҙ№д»ӢгҒҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зҹҘиӯҳгӮ’гӮӨгғігғ—гғғгғҲгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®е°ҸиӘ¬гӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҖҒгғңгӮ№гғҲгғігҒ®иЎ—гҒ®гҒ©гҒ“гҒ«д»ҠеҪјгӮүгҒҢгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гҒ“гҒ«иЎҢгҒ“гҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒҢгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§иҮӘеҲҶгҒҢгҒқгҒ®иЎ—гҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮҲгҒҸеҲҶгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘з¶ҝеҜҶгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮе•ҸйЎҢгҒҜгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®гӮ·гғӘгғјгӮәгҒҢз¶ҡгҒҸгҒЁгҖҒжӯЈзӣҙиЁҖгҒЈгҒҰе°‘гҖ…йЈҪгҒҚгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ гҖӮдҪңдёӯгҒ®дәәзү©гӮӮж®өгҖ…гҒЁе№ҙгӮ’еҸ–гӮҠгҖҒжҲҗй•·гӮӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еӨүеҢ–гҒҢгҒҫгҒ©гӮҚгҒЈгҒ“гҒ—гҒҸжҖқгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮзү©дәӢгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ«гҒҜгҖҒж°ҙжҲёй»„й–ҖгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҒүеӨ§гҒӘгӮӢгғһгғігғҚгғӘеҢ–гӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёҖж–№гҒ§гҒҜеӨүеҢ–гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁйҖҖеұҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒд»–дәәгҒ®гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҶ·йқҷгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ§гҒҜиҮӘеҲҶгҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒҜгҒӘгҒҜгҒ еҝғгӮӮгҒЁгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮж—ҘеёёгӮ’е®үе®ҡзҡ„гҒ«з”ҹжҙ»гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒж—ҘгҖ…жҲҗй•·гҒҷгӮӢгҖҒдҪ•гҒӢж–°гҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гғҒгғЈгғ¬гғігӮёгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгҒ©гҒҶжҠҳгӮҠеҗҲгҒ„гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖӮгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶеҝғгҒ®жҢҒгҒЎгӮҲгҒҶгҒ§гҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«еҗ‘гҒҚеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒІгҒЁгҒӨгҒ®гғ’гғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдјҡзӨҫгҒ§д»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеёёгҒ«дҪ•гҒӢй«ҳгҒ„зӣ®жЁҷгӮ’жҺІгҒ’гҒҰгҒқгӮҢгӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҠӘеҠӣгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ«дҪ•гҒҢеҮәжқҘгҒҰгҖҒдҪ•гҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒиүҜгҒҸиҖғгҒҲгҒҰиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҖӮеҲӨж–ӯгӮ’д»–дәәгҒ«е§”гҒӯгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒй јгҒҫгӮҢд»•дәӢгӮ’гҒҷгӮӢгҒӘгҖҒиҮӘеҲҶгҒ§еҲӨж–ӯгҒӣгӮҲгҖҒдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгҒҜиҮӘгӮүеҸ–гӮҢгҖҒгҒӘгҒ©гҒЁжҖқиҖғгҒ®иЁ“з·ҙгӮ’гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮжҖқгҒҶгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘з·»еҜҶгҒ«иҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е°‘гҖ…з–ІгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®дёүйҮҚеҘҸжӣІеӨүгғӣй•·иӘҝK498гӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҢгӮүй ӯгӮ’дј‘гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
пјҲгғӯгғҷгғјгғ«гғ»гғҙгӮ§гӮӨгғӯгғі(p)гҖҒгӮёгғЈгғғгӮҜгғ»гғ©гғігӮ№гғӯ(cl)гҖҒгӮігғ¬гғғгғҲгғ»гғ«гӮӯгӮўгғі(va)гҖҒгӮЁгғ©гғјгғҲпјү


жӣёеә—гӮ’иҰ—гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒж–°жӣёжң¬гҒ®д»Ҡе№ҙгҒ®гғҷгӮ№гғҲгӮ»гғ©гғјдёҖиҰ§иЎЁгҒҢеЈҒгҒ«иІјгҒЈгҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдҪ•гҒҢеЈІгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁзңәгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒдҪ•дҪҚгҒӢзӣ®гҒ«зҰҸеІЎдјёдёҖи‘—гҖҢз”ҹзү©гҒЁз„Ўз”ҹзү©гҒ®гҒӮгҒ„гҒ гҖҚи¬ӣи«ҮзӨҫзҸҫд»Јж–°жӣёгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒҢијүгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒјгҒҸгҒ®иҲҲе‘ігӮ’еј•гҒ„гҒҹгҖӮеә—й ӯгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гӮӮеЈІгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҰӢгҒҲгҒҰе№із©ҚгҒҝгҒ—гҒҰзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжүӢгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгғ—гғӯгғӯгғјгӮ°гҒЁгӮЁгғ”гғӯгғјгӮ°гӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҖҒгғ—гғӯгғӯгғјгӮ°гҒ§гҒҜгҒ“гҒ®жң¬гҒ®дё»йЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ'з”ҹзү©гҒЁгҒҜдҪ•гҒӢ'гҒЁгҒ„гҒҶгғҶгғјгғһгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ«иҮігҒЈгҒҹи‘—иҖ…гҒ®еӢ•ж©ҹгӮ’иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮЁгғ”гғӯгғјгӮ°гҒ§гҒҜгҖҒз”ҹзү©еӯҰиҖ…гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹи‘—иҖ…гҒ®е°‘е№ҙжҷӮд»ЈгҒ®дҪ“йЁ“гҒҢиӘһгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж–Үз« гҒҢжіЈгҒӢгҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№гҒ«гӮўгӮӘгӮ№гӮёгӮўгӮІгғҸиқ¶гҒ®и©ұгҒҜгҖҒиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢгҖӮгҒ•гҒЈгҒқгҒҸгҒ“гҒ®жң¬гӮ’иІ·гҒ„жұӮгӮҒгҒҹгҖӮ
и‘—иҖ…гҒ®зҰҸеІЎдјёдёҖгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒ1пјҷ59е№ҙжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҒ§гҖҒдә¬йғҪеӨ§еӯҰеҚ’гҖҒгғҸгғјгғҗгғјгғүеӨ§еӯҰеҢ»еӯҰйғЁз ”究員гҖҒдә¬йғҪеӨ§еӯҰеҠ©ж•ҷжҺҲгҒӘгҒ©гӮ’зөҢгҒҰгҖҒзҸҫеңЁгҖҒйқ’еұұеӯҰйҷўеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҖҒе°Ӯж”»гҒҜеҲҶеӯҗз”ҹзү©еӯҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгғ»з”ҹе‘ҪгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢпјҒгҒқгӮҢгҒҜиҮӘе·ұиӨҮиЈҪгӮ’иЎҢгҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢ
гҖҖгҖҖгҖҖгғ»DNAгҒ“гҒқгҒҢйҒәдјқеӯҗгҒ®жң¬дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгғ»гғ»гғ»гӮЁгӮӨгғ–гғӘгғјгҒ®жҘӯзёҫ
гҖҖгҖҖгҖҖгғ»PCRгҒ®зўәз«ӢпјҲDNAгҒ®дәәе·Ҙзҡ„иӨҮиЈҪжі•пјүгғ»гғ»гғ»гғһгғӘгӮ№гҒ®жҘӯзёҫ
гҖҖгҖҖгҖҖгғ»DNAж§ӢйҖ пјҲдәҢйҮҚгғ©гӮ»гғіпјүгҒ®зҷәиҰӢгғ»гғ»гғ»гғҜгғҲгӮҪгғігҒЁгӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ®жҘӯзёҫгғӯгӮөгғӘгғігғүгҒ®еҪ№еүІ
гҖҖгғ»з”ҹе‘ҪгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢпјҒгҒқгӮҢгҒҜеӢ•зҡ„гҒӘе№іиЎЎзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢжөҒгӮҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҖгҖҖгғ»з”ҹе‘ҪгҒҜеӢ•зҡ„е№іиЎЎзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢгғ»гғ»гғ»гӮ·гӮ§гғјгғігғҸгӮӨгғһгғјгҒ®жҘӯзёҫ
гҖҖгҖҖгҖҖгғ»еӢ•зҡ„е№іиЎЎзҠ¶ж…ӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи‘—иҖ…гҒ®иҖғеҜҹ
гҖҖгҖҖгҖҖгғ»гғҺгғғгӮҜгӮўгӮҰгғҲгғ»гғһгӮҰгӮ№гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹи‘—иҖ…гҒ®д»•дәӢ
жң¬гҒ®еҶ…е®№гӮ’еӢқжүӢгҒ«еҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҒЁд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жң¬гҒҜгҖҒд»Ҡж—ҘгӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒҢжүӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢзҹҘиӯҳгҒ®еҚҳгҒӘгӮӢзҫ…еҲ—гӮ„и§ЈиӘ¬гҒЁгҒ„гҒҶжӣёгҒҚж–№гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®жҘӯзёҫгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰжҲҗгҒ—гҒҲгҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®з ”究иҖ…гҒ®иӢҰеҠҙи©ұгҒҢе®ҹгҒ«з”ҹгҒҚз”ҹгҒҚгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁжҖқгӮҸгҒҡеј•гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ
з”ҹе‘ҪгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸгҒ„гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒи‘—иҖ…гҒҜ'иҮӘе·ұиӨҮиЈҪгӮ’иЎҢгҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢ'гҒЁгҒ„гҒҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜ'еӢ•зҡ„гҒӘе№іиЎЎзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢжөҒгӮҢгҒ§гҒӮгӮӢ'гҒЁгҒ„гҒҶз«Ӣе ҙгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дҝЎеҝөгҒҜгҖҒи‘—иҖ…гҒ®дҪ“йЁ“гҒ«еҹәгҒҘгҒҸдҝЎеҝөгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз”ҹзү©гҒ®дёҚжҖқиӯ°гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢз•Ҹ敬гҒ®еҝөгҒҢгҒ“гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеј•гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҰиӘӯгҒҝзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®еҲҶеӯҗз”ҹзү©еӯҰгҒ®жңҖе…Ҳз«ҜгӮ’еһЈй–“иҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®дҪ“гҒҜгҖҒйЈҹзү©гӮ’гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҚҳгҒ«гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҝгҒ§гҒӘгҒҸгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®дҪ“гӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҲҶеӯҗгҒҢгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒ«зҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгӮЁгғігғҲгғӯгғ”гғјеў—еӨ§гҒ®жі•еүҮгҒӢгӮүгҖҒжҲ‘гҖ…гӮ’ж•‘гҒ„гҖҒзӣҙгҒЎгҒ«иЁӘгӮҢгӮӢжӯ»гӮ’е…ҚгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒзӯүгҖ…гҖҒгҒӘгҒңз”ҹзү©гҒҢ'еӢ•зҡ„гҒӘе№іиЎЎзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢжөҒгӮҢ'гҒӘгҒ®гҒӢиҲҲе‘ігҒҜе°ҪгҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ«иҝ°гҒ№гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒз ”з©¶гҒ®ж–№жі•гҖҒжҖқиҖғгҒ®ж–№жі•гҒӘгҒ©гӮӮеӨ§еӨүз§ҖйҖёгҒ§гҖҒзү№гҒ«иӢҘгҒ„жҠҖиЎ“еұӢгҒ®зҡҶгҒ•гӮ“гҒ«гҒҜдёҖиӘӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жҲ‘гҖ…гҒ®дҪ“гҒҜеҺҹеӯҗгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰгҖҒгҒӘгҒңгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢпјҹгӮ·гғҘгғ¬гғјгғҮгӮЈгғігӮ¬гғјгҒ®е•ҸгҒ„гҖӮгғ»гғ»гғ»зӯ”гҒҲгҒҜжң¬жӣёгҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒЎгҒҫгҒҹгҒ«йӣЁгҒҢгҒөгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»пјҲгғҙгӮ§гғ«гғ¬гғјгғҢпјү
гҒЎгҒҫгҒҹгҒ«йӣЁгҒҢгҒөгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«
гҒјгҒҸгҒ®еҝғгҒ«гҒӘгҒҝгҒ гҒөгӮӢ
гҒӘгӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҖҖгҒ“гҒ®гӮӮгҒ®гҒҶгҒ•гҒҜ
гҒ—гҒЁгҒ—гҒЁгҒЁеҝғгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«гҒ—гҒ®гҒіе…ҘгӮӢ
гҒҠгҒҠгҖҖйӣЁгҒ®йҹігҖҖең°дёҠгҒ«гӮӮ
гҒҹгҒЎгҒӘгӮүгҒ¶еұӢж №гҒ®дёҠгҒ«гӮӮ
гҒ“гҒ®еҖҰжҖ гҒ®еҝғгҒ«гҒҜ
йӣЁгҒ®жӯҢгҖҖгҒҠгҒҠгҖҖгҒ—гҒҡгҒӢгҒӘгҒІгҒігҒҚ
гҒ„гӮҸгӮҢгҒӘгҒҸгҖҖгҒӘгҒҝгҒ гҒөгӮҠ
гҒ„гӮҸгӮҢгҒӘгҒҸгҖҖгҒ—гӮҒгҒӨгҒ‘гӮӢгҖҖгҒјгҒҸгҒ®еҝғгӮҲ
гҒӘгӮ“гҒЁиЁҖгҒҶпјҹгҖҖиЈҸеҲҮгӮҠгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гҒ гҒӯ
гҒ„гӮҸгӮҢгҒӘгҒҸгҖҖе–ӘгҒ«гҒ—гҒҡгӮҖгҖҖгҒјгҒҸгҒ®еҝғгӮҲ
гҒ„гҒЎгҒ°гӮ“гӮҸгӮӢгҒ„гҒҸгӮӢгҒ—гҒҝгҒҜ
гҒ„гӮҸгӮҢгӮӮгҒ—гӮҢгҒ¬иә«гҒ®гҒ„гҒҹгҒҝ
жҒӢгӮӮгҒӘгҒҸгҖҖгҒ«гҒҸгҒ—гҒҝгӮӮгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ«
гҒјгҒҸгҒ®еҝғгҒҜгҖҖгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮӮгҒҸгӮӢгҒ—гҒҝгҒ«гҒҝгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢ
пјҲж©Ӣжң¬дёҖжҳҺиЁіпјү
гҒ“гӮҢгҒҜж©Ӣжң¬дёҖжҳҺиЁігҒ®гғҙгӮ§гғ«гғ¬гғјгғҢгҒ®и©©гҒ®дёҖзҜҖгҒ§гҒӮгӮӢеғ•гҒҜдәҢеҚҒжӯід»ЈгҒ«гҒ“гҒ®и©©гҒ«еҮәдјҡгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’гҖӮиӘӯгӮҖгҒЁиғёгҒҢз· гӮҒгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢжҖқгҒ„гҒҢгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮиҮӘеҲҶгҒ§гҒҜеүҚеҗ‘гҒҚгҒ«гҖҒжҳҺгӮӢгҒҸгҖҒдёҖз”ҹжҮёе‘ҪгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒгҒӮгӮӢж—ҘгҒ„гӮҸгӮҢгӮӮгҒӘгҒҸжӮІгҒ—гҒҝгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒҶгҖҒиӢҰгҒ—гҒҝгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒжӮІгҒ—гҒҝгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒҚгҒ«гҒ“гҒ®и©©гӮ’йқҷгҒӢгҒ«иӘӯгӮҖгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§еғ•гҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’д»ЈејҒгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®гӮ»гғігғҒгғЎгғігӮҝгғ«гӮ’еҜҶгҒӢгҒ«жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮ“гҒӘзІҫзҘһзҠ¶ж…ӢгӮ’е®ўиҰізҡ„гҒ«иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜй¬ұзҠ¶ж…ӢгҒЁгҒ—гҒӢиЁҖгҒ„ж§ҳгҒ®гҒӘгҒ„зү©гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒҜгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒӢгӮүгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’иІ°гҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒјгҒҸгҒ®йғЁеұӢгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®и©©гҒҢйЎҚгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҖҒгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮиҰӢгҒҹгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ

зҹҘз«ӢгҒ«гҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢгӮ°гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгғҲгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒй•·е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢеҸҺйӣҶгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮёгғЈгӮәгҒ®LPгҒҢ1дёҮ5еҚғжһҡд»ҘдёҠгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгӮӮеҸҜиғҪгҒӘйҷҗгӮҠгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒ§гҒқгӮҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүLPгҒ®йҹіжәҗгҒҢгҒӮгӮӢгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҒ§гӮӮCDгӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒјгҒҸгӮӮгҒ“гҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгҖҒжҷӮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒCDгӮ„еӣҪеҶ…зӣӨгҒ®LPгҒЁгҒ®гҒӮгҒҫгӮҠгҒ®йҹігҒ®йҒ•гҒ„гҒ«е”–然гҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгӮ’гҒӘгҒңйҮҚиҰ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲдёҠгҒ§гҖҢгғ¬гӮігғјгғүгҒЁгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®йғЁеұӢгҖҚ(гҖҢгғ¬гӮігғјгғүгҒЁгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®йғЁеұӢгҖҚгҒҜй–үйҺ–иҮҙгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ)гҒЁгҒ„гҒҶгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгғўгӮўгҒ•гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶж–№гҒҢж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ
гӮёгғЈгӮәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹеӣҪгҒ®еҲқзүҲгғ—гғ¬гӮ№гӮ’иЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гҒҜгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ§гҒҜдҪ•ж•…гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгӮ’йҮҚиҰҒиҰ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢпјҹзҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜдёӢиЁҳгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
пј‘пјҺ
пј’пјҺ
пј“пјҺ
пј”пјҺ
пј•пјҺ
пј–пјҺ
гғўгӮўгҒ•гӮ“гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹпј‘гҒЁпј“гҒ®й …зӣ®гҒЁгҒ®й–ўйҖЈгҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҢж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгҒӮгҒҲгҒҰзӢ¬ж–ӯгҒЁеҒҸиҰӢгҒ§иҝ°гҒ№гӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ®ең§еҖ’зҡ„гҒӘе……е®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣҪеҶ…зӣӨгӮ’иҒһгҒҸгҒЁдҪҺеҹҹгҒӢгӮүй«ҳеҹҹгҒҫгҒ§жәҖйҒҚгҒӘгҒҸйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒ«гҒҜгғҸгӮӨгғ•гӮЎгӮӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҹіжҘҪгҒЁгҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҹе ҙеҗҲгҖҒйҹігҒҢе№іжқҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒиӮқеҝғгҒӘгғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгғ©гӮӨгғігҒ®дёӯйҹіеҹҹгҒҢеүҚгҒ«еҮәгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҹіжҘҪгҒҢгғҙгӮЈгғҙгӮЈгғғгғҲгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®ж¬ЎгҒ®зү№еҫҙгҒҜйҢІйҹігғ¬гғҷгғ«гҒҢйқһеёёгҒ«й«ҳгҒҸгҖҒзҙ°гҒӢгҒ„йҹігҒҫгҒ§иҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҢгӮӯгғЈгғҺгғігғңгғјгғ«гғ»гӮўгғҖгғ¬гӮӨгғ»гӮӨгғігғ»гӮ·гӮ«гӮҙгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒҜгҖҒеҪјгҒ®еҗ№гҒҸгӮўгғ«гғҲгғ»гӮөгғғгӮҜгӮ№гҒ®гғӘгғјгғүгҒ®йңҮгҒҲгҒҫгҒ§иҒһгҒҚеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүеӣҪеҶ…зүҲгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶиҒһгҒ“гҒҲж–№гҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮдҪҶгҒ—гҖҒйҢІйҹігғ¬гғҷгғ«гҒЁй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғ—гғҒгғ—гғҒгҒЁгҒ„гҒҶгғҺгӮӨгӮәгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮеӣҪеҶ…зӣӨгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢSNжҜ”гҒҜиүҜгҒ„гҖӮгҒ§гӮӮиүҜгҒ„йҹіжҘҪгҒҢиҒһгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒеӨҡе°‘гҒ®гғҺгӮӨгӮәгҒҜж°—гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹдәӢгҒҜгҖҒдҪ•гӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдҫЎеҖӨиҰігҒҢй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҖӮдәӣзҙ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒ“гҒ гӮҸгӮүгҒҡгҖҒгғҙгӮЈгғҙгӮЈгғғгғҲгҒ«йҹіжҘҪгҒҢиҒһгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢеӨ§еҲҮгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ гҒҢгҖӮйҹігҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒЁеӣҪеҶ…зӣӨгҒ®йҒ•гҒ„гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиүІгҖ…гҒӘгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮй«ҳдҫЎгҒӘгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒ«жүӢгӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„йҹігҒ®и©°гҒҫгҒЈгҒҹLPгӮ’е…ҘжүӢгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғўгӮўгҒ•гӮ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒҜгҒҹгҒ„гҒёгӮ“еҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ