|
гғҲгғҹгғјгғ»гғ•гғ©гғҠгӮ¬гғігғ»гғҲгғӘгӮӘгҒ®д»ЈиЎЁдҪңгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҢгӮӘгғјгғҗгғјгӮ·гғјгӮәгҖҚгҖҢгӮЁгӮҜгғӘгғ—гӮҪгҖҚгҖҢгӮёгғЈгӮӨгӮўгғігғҲгғ»гӮ№гғҶгғғгғ—гӮ№гҖҚгҒӘгҒ©гҒ®еҗҚеүҚгҒҢжҢҷгҒҢгӮӢгҒҢгҖҒдёҚжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҖҢгӮёгғЈгӮәгғ»гғқгӮЁгғғгғҲгҖҚгҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеҮәгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҖӮеҫҢи—ӨиӘ ж°ҸгҒҢ1993е№ҙгҒ«гғҲгғҹгғјпҪҘгғ•гғ©гғҠгӮ¬гғігҒ«гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ—гҒҹжҷӮгҒ«гҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®еҲқгғӘгғјгғҖгғјдҪңпјҲгӮӘгғјгғҗгғјгӮ·гғјгӮәпјүгҒҜгҖҒд»ҠгӮӮгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®д»ЈиЎЁдҪңгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҗҚгҒ§гҒҷгҖҒгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгӮүгҖҒе°‘гҒ—дёҚжәҖгҒқгҒҶгҒ«гҖҒиҮӘеҲҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҢгӮёгғЈгӮәгғ»гғқгӮЁгғғгғҲгҖҚгҒ®ж–№гҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ—гҖҒеҶ…е®№гӮӮдёҠгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖҒгҒЁзӯ”гҒҲгҒҹгҒЁгҖҒжң¬гҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒјгҒҸгӮӮгҒқгҒҶжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒдҪ•ж•…жіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢдёҚжҖқиӯ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
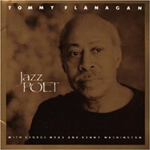
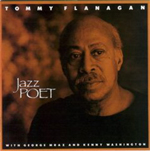
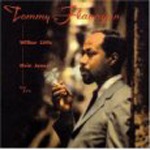
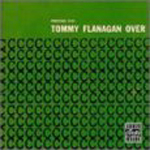
Jazz Poet / Tommy Flanagan (Timeless [H] SJP 301)
Tommy Flanagan (p) George Mraz (b) Kenny Washington (d) пјӣ NYC, January 17 & 19, 1989.
- 1.
- Raincheck
- 2.
- Lament
- 3.
- Willow Weep For Me
- 4.
- Caravan
- 5.
- That Tired Routine Called Love
- 6.
- Glad To Be Unhappy
- 7.
- St. Louis Blues
- 8.
- Mean Streets
- 9.
- I'm Old Fashioned
- 10.
- Voce Abuso
гҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҖҒдҪңе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҮәжқҘгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹгғҗгғігӮІгғ«гғҖгғјйҢІйҹігҒ§еӨ§еӨүйҹігӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зҷәеЈІгҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ§жіЁзӣ®гҒҢдҪҺгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®CDгҒ®зҷәеЈІгҒҜжңҖеҲқгӮўгғ«гғ•гӮЎгғ¬гӮігғјгғүгҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒӮгҒЁMпјҶIгҒӢгӮүгҒ®зҷәеЈІгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹдёҚжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҗҢгҒҳпјҲиүІгҒ®жҝғж·ЎгҖҒж–Үеӯ—гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒҢе°‘гҒ—з•°гҒӘгӮӢпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжӣІгҒ®й ҶеәҸгҖҒгғ©гӮӨгғҠгғјгғҺгғјгғ„гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғһгӮ№гӮҝгғӘгғігӮ°гҒ®йҒ•гҒ„гҒ§гҖҒйҹігҒ®еӮҫеҗ‘гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸйҒ•гҒҶгҖӮ
гҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘжӣІгҒҜгҖҒ1жӣІзӣ®гҒ®RaincheckгҖҒгҒқгҒ—гҒҰ8жӣІзӣ®гҒ®Mean StreetsгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жӣІгҒҜгҖҢгӮӘгғјгғҗгғјгӮ·гғјгӮәгҖҚгҒ®дёӯгҒ§гҒҜVerdandiгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҖҒгӮЁгғ«гғ“гғіпҪҘгӮёгғ§гғјгғігӮәгҒ®гғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒӘгғүгғ©гғ гҒҢйҡӣз«ӢгҒЈгҒҹжӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгӮұгғӢгғјгғ»гғҜгӮ·гғігғҲгғігҒ®гҒ“гӮҢгҒҫгҒҹзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жҠҖгҒҢиҒһгҒ‘гҖҒеҪјгҒ«ж•¬ж„ҸгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҖҒеҪјгҒ®йҖҡгӮҠеҗҚгҒ§гҒӮгӮӢMean StreetsгҒЁж”№йЎҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒӨгҒ„гҒ§гҒ«гҖҢгӮӘгғјгғҗгғјгӮ·гғјгӮәгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§зҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒҜгҖҒгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒҢгғҲгғҹгғ•гғ©гҒ®жЁӘйЎ”гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«зӣӨгҒҜгӮ°гғӘгғјгғігҒ«CгҒ®ж–Үеӯ—гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒ“гҒЎгӮүгҒ®ж–№гҒҢжңүеҗҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬зӣӨгҒ®CDгҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹйҢІйҹігғ¬гғҷгғ«гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮ

гғҲгғҹгғјпҪҘгғ•гғ©гғҠгӮ¬гғігҒҢеҲқгғӘгғјгғҖгғјдҪңгҖҢгӮӘгғјгғҗгғјгӮ·гғјгӮәгҖҚгӮ’гғЎгғҲгғӯгғҺгғјгғ гҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1957е№ҙ8жңҲ15ж—ҘгҖҒгӮ№гғҲгғғгӮҜгғӣгғ«гғ гҒ§гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғЎгғігғҗгғјгҒҜгғҲгғҹгғјгғ»гғ•гғ©гғҠгӮ¬гғі(p)гҖҒгӮҰгӮЈгғ«гғҗгғјгғ»гғӘгғҲгғ«(b)гҖҒгӮЁгғ«гғ“гғігғ»гӮёгғ§гғјгғігӮә(d)гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜJ.J.гӮёгғ§гғігӮҪгғігҒ®гғЁгғјгғӯгғғгғ‘жј”еҘҸгғ„гӮўгғјгҒ®гғӘгӮәгғ гӮ»гӮҜгӮ·гғ§гғігҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгғӘгғјгғҖгғјдҪңгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгғ¬гӮ®гғҘгғ©гғјгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҒгӮЁгғ«гғ“гғігҒ®гғӣгғғгғҲгҒӘгғүгғ©гғ гҒ«и§ҰзҷәгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгҒ„гҒӨгҒ«гҒӘгҒҸгғҲгғҹгғјгӮӮгғӣгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒӢгӮүгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӮ‘дҪңгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ§гҒҜгҖҒгғҲгғҹгғјпҪҘгғ•гғ©гғҠгӮ¬гғігҒҜе„ӘгӮҢгҒҹдјҙеҘҸгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰеәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒиӘ°гӮӮеҪјгҒ®гғӘгғјгғҖгғјдҪңгӮ’иЈҪдҪңгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҜжҖқгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢгӮӘгғјгғҗгғјгӮ·гғјгӮәгҖҚгӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒгӮҪгғӢгғјгғ»гғӯгғӘгғігӮәгҒЁгҖҢгӮөгӮӯгӮҪгғ•гӮ©гғігғ»гӮігғӯгғғгӮөгӮ№гҖҚгҒЁгҒӢгӮұгғӢгғјгғ»гғҗгғ¬гғ«гҖҒJ.J.гӮёгғ§гғігӮҪгғігҖҒгғҹгғ«гғҲгғ»гӮёгғЈгӮҜгӮҪгғігҒӘгҒ©гҒЁеӨҡгҒҸгҒ®йҢІйҹігӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҲқгғӘгғјгғҖгғјдҪңгҒҢеҢ—欧гҒ®гғЎгғҲгғӯгғҺгғјгғ гҒЁгҒ„гҒҶгғһгӮӨгғҠгғјгғ¬гғјгғҷгғ«гҒӢгӮүеҮәгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҪ“еҲқж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜе…ҘжүӢгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҖҒе№»гҒ®еҗҚзӣӨгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгӮӨгғҲгғ«гӮӮ" Tommy Flanagan Trio Overseas "д»ҘеӨ–гҒ«" Tommy Flanagan Trio in Stockholm 1957 "гҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨгғҲгғ«гӮӮеҶ…е®№гҒҜеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгӮӮе®ҹгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒқгҒ®дёҖйғЁгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮ
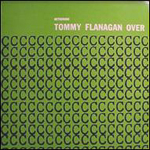
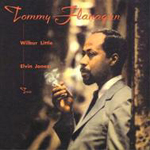
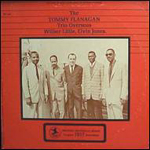
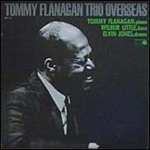
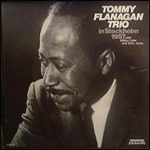
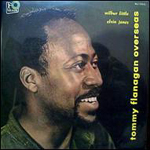
гҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒгғҮгӮ№гӮҜгғҰгғӢгӮӘгғігҒӢгӮүзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ«гҒҜгҖҒз•°гҒӘгҒЈгҒҹгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒҢдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҖЈж—ҘгҖҒ35еәҰгӮ’и¶…гҒҲгӮӢзҢӣжҡ‘ж—ҘгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜжңқгҒӢгӮүйӣ·гҒЁйӣЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒж°—жё©гӮӮ26еәҰд»ҘдёӢгҒ«дёӢгҒҢгӮҠж¶јгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®10ж—Ҙй–“гҒҜгҖҒиүІгҖ…гҒӘдәӢгҒҢгҒӮгӮҠйӣ‘иЁҳеёігӮӮдј‘гҒҝгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜжңқгҒӢгӮүеҘҪгҒҚгҒӘгӮ№гӮҝгғігғ»гӮІгғғгғ„гҒ®гӮёгғЈгӮәгӮ’гҒҡгҒЈгҒЁиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гӮ№гӮҝгғіпҪҘгӮІгғғгғ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ"иҖігӮ’жҫ„гҒҫгҒӣгҒ°дәәз”ҹгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгӮҲ"гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜзўәгҒӢеҜәеі¶йқ–еӣҪгҒ•гӮ“гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒјгҒҸгҒҜгҖҒгӮІгғғгғ„гҒҜгғЎгғӯгғҮгӮЈгҒ®еӨ©жүҚгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰеҜәеі¶гҒ•гӮ“гҒ®иЁҖгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮІгғғгғ„гҒҜжҷӮд»ЈжҷӮд»ЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж„ҹжғ…иЎЁзҸҫгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮІгғғгғ„гҒ®дәәз”ҹгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҖҒз°ЎеҚҳгҒ«ж•ҙзҗҶгҒҷгӮӢгҖӮ
гӮ№гӮҝгғіпҪҘгӮІгғғгғ„гҒҜ1927е№ҙ2жңҲ2ж—ҘгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«еҗҲиЎҶеӣҪгғ•гӮЈгғ©гғҮгғ«гғ•гӮЈгӮўгҒ®гғҸгғјгғ¬гғ гҒ§иІ§гҒ—гҒ„гғҰгғҖгғӨзі»гғүгӮӨгғ„дәә移民гҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮ16жӯігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«гғ—гғӯгҒ®гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒгғҗгғігғүгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҖҒгӮёгғЈгғғгӮҜгғ»гғҶгӮЈгӮ¬гғјгғҮгғігҖҒгӮ№гӮҝгғігғ»гӮұгғігғҲгғігҖҒгғҷгғӢгғјгғ»гӮ°гғғгғүгғһгғігҒ®еҗ„жҘҪеӣЈгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹгҖӮ1947е№ҙгҒ«гӮҰгғҮгӮЈпҪҘгғҸгғјгғһгғігҒ®гғҳгӮ«гғігғүгғ»гғҸгғјгғүгҒ«еңЁзұҚгҒ—гҖҒгғӘгғјгғүпҪҘгӮ»гӮҜгӮ·гғ§гғі"гғ•гӮ©гғјгғ»гғ–гғ©гӮ¶гғјгӮә"гҒ®дёҖе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰеҗҚгӮ’дёҠгҒ’гҖҒгӮўгғјгғӘгғјпҪҘгӮӘгғјгӮҝгғ гҒӘгҒ©гҒ®жӯҙеҸІзҡ„еҗҚжј”гӮ’ж®ӢгҒ—гҖҒгӮҜгғјгғ«гғ»гӮёгғЈгӮәгӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢгғҶгғҠгғјгғ»гӮөгғғгӮҜгӮ№гҒЁгҒ—гҒҰе®ҡи©•гӮ’еҫ—гӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒӮгҒЁиҮӘе·ұгҒ®гӮ°гғ«гғјгғ—гӮ’зөҗжҲҗгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒдёҖж–№гҒ§йә»и–¬гҒ«гӮӮжүӢгӮ’жҹ“гӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒ1954е№ҙгҒ«гҒҜйә»и–¬гӮ’иІ·гҒҶйҮ‘гҒ»гҒ—гҒ•гҒ«гӮігғігғ“гғӢеј·зӣ—гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ
жңҚеҪ№гӮ’зөӮгҒҲгҒҹеҫҢгҒҜгҖҒгғҺгғјгғһгғігғ»гӮ°гғ©гғігғ„гҒ®дё»еӮ¬гҒҷгӮӢJATPгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҖҒеҢ—欧гҒёгҒЁж—…иЎҢгӮ’гҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒ61е№ҙгҒҫгҒ§гӮігғҡгғігғҸгғјгӮІгғігӮ’жӢ зӮ№гҒ«гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§жҙ»еӢ•гҖӮ
1961е№ҙгҒ«гӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ«её°еӣҪгҒ—гҖҒеҪ“жҷӮжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгғ–гғ©гӮёгғ«йҹіжҘҪгҒ®гғңгӮөгғҺгғҙгӮЎгӮ’жҺЎгӮҠе…ҘгӮҢгҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҖҢгӮёгғЈгӮәгғ»гӮөгғігғҗгҖҚгӮ’йҢІйҹігҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮёгғЈгӮәз•ҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғңгӮөгғҺгғҙгӮЎеҘҸиҖ…гҒ®з¬¬дёҖдәәиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®и©•дҫЎгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮ1963е№ҙгҒ«гҒҜгӮёгғ§гӮўгғігғ»гӮёгғ«гғҷгғ«гғҲгҖҒгӮўгғігғҲгғӢгӮӘгғ»гӮ«гғ«гғӯгӮ№гғ»гӮёгғ§гғ“гғігҒЁе…ұгҒ«гҖҢгӮІгғғгғ„пјҸгӮёгғ«гғҷгғ«гғҲгҖҚгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒгӮ°гғ©гғҹгғјиіһ4йғЁй–ҖгӮ’зӢ¬еҚ гҒҷгӮӢеӨ§гғ’гғғгғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«йҹіжҘҪз•ҢгӮ№гғјгғ‘гғјгӮ№гӮҝгғјгҒ®еә§гӮ’зҚІеҫ—гҖӮ
д»ҘйҷҚиҮӘе·ұгҒ®гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§1969е№ҙгҒҫгҒ§жҙ»еӢ•гҖӮгҒқгҒ®еҫҢ72е№ҙгҒҫгҒ§еҚҠгҒ°еј•йҖҖеҗҢж§ҳгҒ®жҷӮжңҹгӮ’йҒҺгҒ”гҒҷгҖӮ1980е№ҙд»ЈгҒ«еҶҚгҒігӮігғігӮігғјгғүгҒЁеҘ‘зҙ„гҒ—гҖҒгӮІгғғгғ„гҒ®еҶҶзҶҹжңҹгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҖӮ87е№ҙгҒ«иӮқиҮ“гӮ¬гғігӮ’е®Је‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰд»ҘжқҘгҖҒжј”еҘҸжҙ»еӢ•гҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰй—ҳз—…гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒ1991е№ҙ6жңҲ6ж—Ҙжӯ»еҺ»гҖӮ
д»ҘдёҠгӮ№гӮҝгғіпҪҘгӮІгғғгғ„гҒҜйә»и–¬гҖҒгҒқгӮҢгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢйҖ®жҚ•гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гӮўгғ«гӮігғјгғ«дҫқеӯҳз—ҮгҖҒйӣўе©ҡгҒ«дјҙгҒҶиҺ«еӨ§гҒӘж…°и¬қж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҖҒгӮ¬гғігҒ«гӮҲгӮӢй—ҳз—…гҒЁеӨҡгҒҸгҒ®еӣ°йӣЈгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҪјгҒҜжј”еҘҸгҒ«гӮҲгӮӢиҮӘе·ұиЎЁзҸҫгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜеӨ©жүҚгҒ®йҹіжҘҪгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
й•·гҖ…гҒЁжӣёгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгҒ«гӮҲгӮҠеӨ©жүҚгҒ¶гӮҠгҒ®зҷәжҸ®гҒ«д»•ж–№гҒҢе°‘гҒ—гҒҡгҒӨз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®жј”еҘҸгҒӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒеҪјгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгӮҲгӮҠзҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮд»Ҡж—ҘгҒјгҒҸгҒҢиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢй Ҷз•ӘгҒ«гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮ
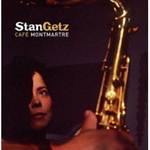
гғ»STAN GETZ/CAFE MONTMARTRE
Kenny Barron ( Piano ) , Stan Getz ( Sax (Tenor) )
Victor Lewis ( Drums ) , Rufus Reid ( Double Bass )
1 People Time (6:11) , 2 I Thought About You (8:12) , 3 Soul Eyes (7:20) , 4 I Can't Get Started (11:13) , 5 I'm Okay (5:22) , 6 Falling in Love (9:01) , 7 I Remember Clifford (8:49) , 8 Blood Count (3:54) , 9 First Song (For Ruth) (9:53)
гӮ№гӮҝгғіпҪҘгӮІгғғгғ„гҒҢ1987е№ҙ7жңҲ6ж—ҘгҒ«гҖҒгӮігғҡгғігғҸгғјгӮІгғігҒ®гӮ«гғ•гӮ§пҪҘгғўгғігғһгғ«гғҲгғ«гҒ§гҖҒгӮұгғӢгғјгғ»гғҗгғӯгғігҖҒгғ“гӮҜгӮҝгғјгғ»гғ«гӮӨгӮ№гҖҒгғ«гғјгғ•гӮЎгӮ№гғ»гғӘгғјгғүгҒЁиЎҢгҒЈгҒҹзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гғ©гӮӨгғ–жј”еҘҸгҒ®иЁҳйҢІгҒҢ2жһҡгҒ®CDгҒЁгҒ—гҒҰзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгҖҒANNIVERSARYгҒЁSERENITYгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жј”еҘҸдјҡгҒ§гғҗгғ©гғјгғүгӮ’дёҖжӣІгғ”гӮўгғҺгҒЁгҒ®гғҮгғҘгӮӘгҒ§жј”еҘҸгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒҫгҒҹеӨ§еӨүзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒӨгҒӢгғҮгғҘгӮӘгҒ§гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’дҪңгӮҚгҒҶгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢ1991е№ҙпј“жңҲпј“пҪһ6ж—ҘгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®гҖҒеҗҢгҒҳгӮігғҡгғігғҸгғјгӮІгғігҒ®гӮ«гғ•гӮ§пҪҘгғўгғігғһгғ«гғҲгғ«гҒ§гҖҒгӮұгғӢгғјпҪҘгғҗгғӯгғігҒЁгҒ®PEOPLE TIMEгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғіпҪҘгӮІгғғгғ„гҒ®жӯ»гҒ®пј“гғ¶жңҲеүҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢеҪјгҒ®жңҖеҫҢгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®STAN GETZ/CAFE MONTMARTREгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҖҒ1987е№ҙгҒЁ1991е№ҙгҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮ’з·ЁйӣҶгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1гҖҒ3гҖҒ5гҖҒ7гҖҒ9жӣІгҒҢгӮұгғӢгғјгғ»гғҗгғӯгғігҒЁгҒ®гғҮгғҘгӮӘгҖҒ2гҖҒ4гҖҒ6гҖҒ8жӣІгҒҢгӮ«гғ«гғҶгғғгғҲгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҷ©е№ҙгҒ®гӮІгғғгғ„гҒ®жј”еҘҸгҒҢгҒ“гҒ“гҒ«еҮқзё®гҒ—гҖҒзү№гҒ«гғҮгғҘгӮӘгҒ§гҒ®I Remember CliffordгҖҒFirst SongгҒӘгҒ©гҒҜж„ҹеӢ•гҒ®ж¶ҷгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜиҒһгҒ‘гҒӘгҒ„гҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒ«иҒһгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„1жһҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰж„ҹеӢ•гҒ—гҒҹгӮүдёҠиЁҳгҒ®3жһҡгӮ’жүӢгҒ«еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
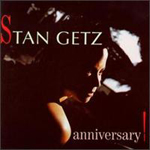
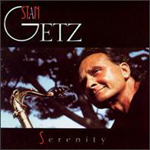
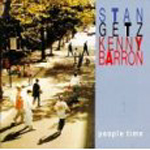
жҷ©е№ҙгҒ®гӮ№гӮҝгғіпҪҘгӮІгғғгғ„гҒ®зҙ№д»ӢгҒ«еҠӣгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҲқжңҹгҒ®жј”еҘҸгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҖӮ
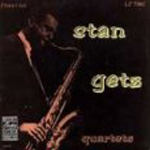
гғ»STAN GETZ QUARTETS
гҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜ1949е№ҙгҒӢгӮү50е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®гҖҒгғҜгғігғ»гғӣгғјгғіз·ЁжҲҗгҒ«гӮҲгӮӢеҲқжңҹеҗҚжј”йӣҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮІгғғгғ„гҒ®з‘һгҖ…гҒ—гҒ„жј”еҘҸгҒҜгҒ©гҒ®жӣІдёҖгҒӨеҸ–гҒЈгҒҰгӮӮеӨ§еӨүйӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№гҒ«гҒјгҒҸгҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгҒ®гҒҜWhat's NewгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
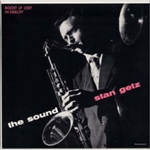
гғ»THE SOUND
гӮ№гӮҝгғігғ»гӮІгғғгғ„гҒҢгӮ№гӮЁгғјгғҮгғігҒ®гғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒЁгҖҒ1951е№ҙгҒ«еҪ“ең°гҒ§еҲқгӮҒгҒҰе…ұжј”гҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҖӮеҪјгҒ®зҙ№д»ӢгҒ§еәғгҒҸзҹҘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹDEAR OLD STOCKHOLMгҒҢеҲқгӮҒгҒҰзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒЈгҒҹгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘иҒһгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮгҖҒеӨ§жәҖи¶ігҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҪјгҒ®йӯ…еҠӣгҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ е°ҪгҒҚгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҒ“гӮҢгҒ§гҒҠзөӮгҒ„гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ








