|
гҖҖе№ҙгҒҢжҳҺгҒ‘гҒҰе№ҙе§ӢгҒ®жҢЁжӢ¶гӮ„гҖҒе…„ејҹгғ»еӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒЁгҒ®йЎ”еҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҖҒж…ҢгҒҹгҒ гҒ—гҒҸйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«жқҘгҒҰе°‘гҒ—иҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®пј¬пј°гҒ§гӮӮиҰӢгҒ«иЎҢгҒ“гҒҶгҒЁеҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүпј–жһҡгҒ®пј¬пј°гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖвҳ…1жһҡзӣ®гҒҜгғҸгӮӨгғүгғігҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҖҢеҶ—и«ҮгҖҚгҖҢгӮ»гғ¬гғҠгғјгғҮгҖҚгҖҢ5еәҰгҖҚгҒ®йҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹпј¬пј°гҒ§гҖҒжј”еҘҸгҒҜгғӨгғҠгғјгғҒгӮ§гӮҜејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒDECCA 1964е№ҙзҷәеЈІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгғҸгӮӨгғүгғігҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҒҜгҖҒиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒЁгҒҰгӮӮжё…жё…гҒ—гҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҹгҒ„гҒҰгҒ„гҒ®гӮӮгҒ®гҒҜжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгғӨгғҠгғјгғҒгӮ§гӮҜејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒҜгҖҒгӮ№гғЎгӮҝгғҠејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒЁгҒӘгӮүгӮ“гҒ§гғҒгӮ§гӮігӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ§гҖҒж јиӘҝй«ҳгҒҸгҖҒжҡ–гҒӢгҒҸгҖҒйҹіиүІгӮӮзҫҺйә—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
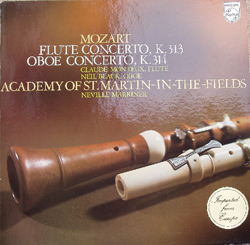
гҖҖвҳ…2жһҡзӣ®гҒҜгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ•гғ«гғјгғҲеҚ”еҘҸжӣІпјҲK313пјүгҒЁгӮӘгғјгғңгӮЁеҚ”еҘҸжӣІпјҲK314пјүгҒ§гҒҷгҖӮжј”еҘҸгҒҜгӮҜгғӯгғјгғүгғ»гғўгғігғҲгӮҘ(fl)гҖҒеҪјгҒҜжҢҮжҸ®иҖ…гғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғўгғігғҲгӮҘгҒ®жҒҜеӯҗгҖӮгғҚгӮӨгғ«гғ»гғ–гғ©гғғгӮҜпјҲOboeпјүгҖҒгғҚгғҙгӮЈгғ«гғ»гғһгғӘгғҠгғјжҢҮжҸ®гҒ®гӮўгӮ«гғҮгғҹгғјпҪҘгӮӘгғ–пҪҘпјіпҪ”пҪҘгғһгғјгғҒгғігғ»гӮӨгғігғ»гӮ¶гғ»гғ•гӮЈгғјгғ«гӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®йҹіжҘҪгҒҜгҒ©гӮҢгӮӮжүӢе…ғгҒ«зҪ®гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгғҮгӮЈгғҙгӮ§гғ«гғҶгӮЈгғЎгғігғҲгӮ„гӮ»гғ¬гғҠгғјгғүгҖҒз®ЎжҘҪеҷЁгҒ®еҚ”еҘҸжӣІгҒӘгҒ©гҒҜиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҘҪгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ
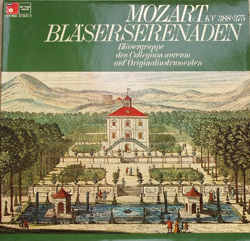
гҖҖвҳ…3жһҡзӣ®гӮӮгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гӮ»гғ¬гғҠгғјгғү第11з•Ә(K375)гҒЁз¬¬12з•ӘпјҲK388пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжј”еҘҸгҒҜеҸӨжҘҪеҷЁгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгӮігғ¬гӮ®гӮҰгғ гғ»гӮўгӮҰгғ¬гӮҰгғ еҗҲеҘҸеӣЈпјҲгғҸгғ«гғўгғӢгӮўгғ»гғ гғігғҮгӮЈпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гӮ»гғ¬гғҠгғјгғүгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒ7з•ӘпјҲгғҸгғ•гғҠгғјпјүгҖҒ9з•ӘпјҲгғқгӮ№гғҲгғ»гғӣгғ«гғіпјүгҖҒ10з•ӘпјҲеҚҒдёүз®ЎжҘҪеҷЁгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮ»гғ¬гғҠгғјгғүпјүгҒқгҒ—гҒҰжңүеҗҚгҒӘ13з•ӘпјҲгӮўгӮӨгғҚгғ»гӮҜгғ©гӮӨгғҚгғ»гғҠгғҸгғҲгғ гӮёгғјгӮҜпјүгӮ’гӮҲгҒҸиҒһгҒҸгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮігғ¬гӮ®гӮҰгғ гғ»гӮўгӮҰгғ¬гӮҰгғ еҗҲеҘҸеӣЈгҒ®еҸӨжҘҪеҷЁгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹжёӢгҒ„йҹіиүІгӮӮгҖҒзҫҺгҒ—гҒ„гҖӮ
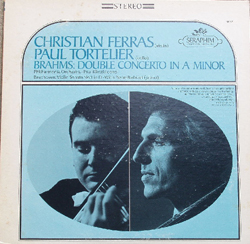
гҖҖвҳ…4жһҡзӣ®гҒҜгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ®гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒЁгғҒгӮ§гғӯгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҚ”еҘҸжӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжј”еҘҸгҒҜгӮҜгғӘгӮ№гғҒгғЈгғігғ»гғ•гӮ§гғ©гӮ№пјҲViolinпјүгҖҒгғқгғјгғ«гғ»гғҲгғ«гғҲгӮҘгғӘгӮЁпјҲCellпјүгҖҒгғ‘гӮҰгғ«гғ»гӮҜгғ¬гғ„гӮӯгӮӨжҢҮжҸ®гҒ®гғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгӮўдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒ§гҒҷгҖӮгӮ«гғғгғ—гғӘгғігӮ°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғӘгғігӮҪгғҠгӮҝ第1з•ӘгҒ§гҒҷгҖӮгғ•гӮ§гғ©гӮ№гҒ®гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҖҒгғ”гӮўгғҺгҒҜгғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғҗгғ«гғ“гӮјгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ®з¬¬5дәӨйҹҝжӣІгҒЁгҒ—гҒҰзқҖжғігҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒ®жӣІгӮ’иҒҙгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢз„ЎгҒҸгҖҒжҖқгӮҸгҒҡиІ·гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгғ•гӮ§гғ©гӮ№гҒ®гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒҢгҒ©гҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдёҚе®үгҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ«гғ©гғӨгғігҒЁеҮәдјҡгҒҶеүҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§(1963е№ҙзҷәеЈІ)гҖҒгҒ®гҒігҒ®гҒігҒЁжј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ
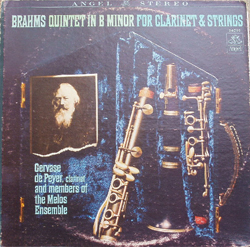
гҖҖвҳ…5жһҡзӣ®гӮӮгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ§гҖҒгӮҜгғ©гғӘгғҚгғғгғҲдә”йҮҚеҘҸжӣІгҒ§гҒҷгҖӮжј”еҘҸгҒҜгӮёгӮ§гғ«гғҙгӮЎгғјгӮ№гғ»гғүгӮҘгғ»гғҡгӮӨгӮЁ(cl)гҒЁгғЎгғӯгӮ№гғ»гӮўгғігӮөгғігғ–гғ«гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ§гҒҜгӮҜгғ©гғӘгғҚгғғгғҲеҚ”еҘҸжӣІгҖҒгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ§гҒҜгӮҜгғ©гғӘгғҚгғғгғҲдә”йҮҚеҘҸжӣІгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒгҒӨгҒ„жүӢгҒҢеҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
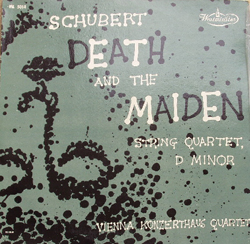
гҖҖвҳ…жңҖеҫҢгҒ®6жһҡзӣ®гҒҜгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІпҪўжӯ»гҒЁд№ҷеҘіпҪЈгҒ§гҒҷгҖӮжј”еҘҸгҒҜгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮігғігғҒгӮ§гғ«гғҲгғҸгӮҰгӮ№ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈпјҲгӮҰгӮЁгӮ№гғҲгғҹгғігӮ№гӮҝгғјпјүгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶLPгҒЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒжүӢгӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮҰгӮЁгӮ№гғҲгғҹгғігӮ№гӮҝгғјгҒ®е®ӨеҶ…жҘҪгҒҜCDгҒ§гӮӮзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒLPгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢж–ӯ然гҖҒејҰгҒ®йҹігҒҢиү¶гӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ第2жҘҪз« гҒ®жӯҢгҒ„ж–№гҒҢгӮігғігғҒгӮ§гғ«гғҲгғҸгӮҰгӮ№гҒҜгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
гҖҖд»ҘдёҠгҖҒд»Ҡж—Ҙиіје…ҘгҒ—гҒҹLPгӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒж–Үз« гӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒҹеӨңдёӯгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢпј‘гҖҚгҒҜдәҲжғід»ҘдёҠгҒ«иүҜгҒ„гҖҒгҖҢпј’гҖҚгҒЁгҖҢпј“гҖҚгҒҜдәҲжғійҖҡгӮҠиүҜгҒ„гҖҒгҖҢпј”гҖҚгҒҜгҒҫгҒӮгҒҫгҒӮгҖҒгҖҢпј•гҖҚгҖҢпј–гҖҚгҒҜдәҲжғід»ҘдёҠгҒ«иүҜгҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢ第1еҚ°иұЎгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүиҒһгҒҚиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖе№ҙжң«гҒ«гӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгҒ®дјқиЁҳгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒжј”еҘҸгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ—гҒҰйҒҺгҒ”гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдәӢгҒ®гҒӨгҒ„гҒ§гҒ«гғ“гғ«пҪҘгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒ®гғ”гӮўгғҺпҪҘгғҲгғӘгӮӘгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒ—гҒҹжј”еҘҸгӮ’ж”№гӮҒгҒҰиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гғҷгғјгӮ·гӮ№гғҲгҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘжј”еҘҸгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’гғ”гғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ
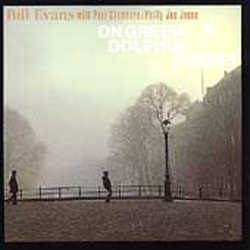
гҖҖгғ»1959.1.19 NYCгҖҖOn Green Dolphin Street (Milestone)гҖҖPaul Chambers(b)гҖҒPhilly Joe Jones(ds)
гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгӮ№гӮігғғгғҲпҪҘгғ©гғ•гӮЎгғӯгҒҢеҸӮеҠ гҒҷгӮӢзӣҙеүҚгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҖҒгғҒгӮ§гғғгғҲпҪҘгғҷгӮӨгӮ«гғјгҒ®гҖҢгғҒгӮ§гғғгғҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹжҷӮгҒ®гғӘгӮәгғ гӮ»гӮҜгӮ·гғ§гғігҒ§гҖҒеҗҢгҒҳж—ҘгҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гӮӮгғқгғјгғ«пҪҘгғҒгӮ§гғігғҗгғјгӮ№гҒ®гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғҷгғјгӮ№гҒ«д№—гҒЈгҒҰгӮҲгҒҸгӮ№гӮӨгғігӮ°гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
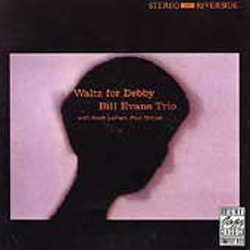
гҖҖпҪҘ1961.6.25 NYCгҖҖWaltz For Debby пјҲRiversideпјүгҖҖScott LaFaro(b)гҖҒPaul Motian(ds)
гҖҖгӮ№гӮігғғгғҲпҪҘгғ©гғ•гӮЎгғӯгҒ®еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгғӘгғҗгғјгӮөгӮӨгғү4йғЁдҪңгҒҜгҒ©гӮҢгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒдҪ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®гғһгӮӨгғ»гғ•гғјгғӘгғғгӮ·гғҘгғ»гғҸгғјгғҲгҒӢгӮүгғҜгғ«гғ„гғ»гғ•гӮ©гғјгғ»гғҮгғ“гғјгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®жј”еҘҸгҒҜдҪ•еәҰиҒҙгҒ„гҒҰгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
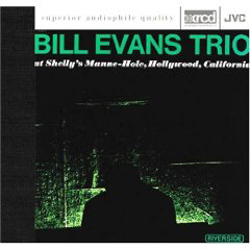
гҖҖпҪҘ1963.5.30 LAгҖҖBill Evans At Shelly's Manne Hole пјҲRiversideпјүгҖҖChuck Israels(b)гҖҒLarry Bunker(ds)
гҖҖгғҒгғЈгғғгӮҜпҪҘгӮӨгӮ№гғ©гӮЁгғ«гҒ®еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒҜгҖҒгғ гғјгғігғ»гғ“гғјгғ гӮ№гҒ®гғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгӮӮиҰӢдәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜеӨ§еӨүгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҹе‘ігӮҸгҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғҒгғЈгғғгӮҜпҪҘгӮӨгӮ№гғ©гӮЁгғ«гҒ®гғҷгғјгӮ№гҒ®йҹігҒҢдҪ•гҒЁгӮӮиү¶гӮ„гҒӢгҒ§зҫҺгҒ—гҒ„гҖӮеҪјзӢ¬зү№гҒ®йҹіиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
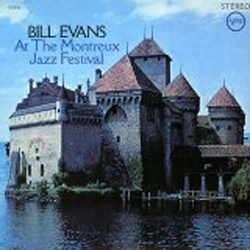
гҖҖпҪҘ1968.6.15 MontreuxгҖҖBill Evans At The Montreux Jazz FestivalпјҲVerveпјүгҖҖEddie Gomez(b)гҖҒJack DeJohnette(ds)
гҖҖгғ“гғ«пҪҘгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№пҪҘгғҲгғӘгӮӘгҒ®гғҷгғјгӮ·гӮ№гғҲгҒ§гӮ№гӮігғғгғҲпҪҘгғ©гғ•гӮЎгғӯгҒҜ2е№ҙгҖҒгғҒгғЈгғғгӮҜпҪҘгӮӨгӮ№гғ©гӮЁгғ«гӮӮ2е№ҙгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮЁгғҮгӮЈгӮӨпҪҘгӮҙгғЎгӮ№гҒҜ11е№ҙй–“еңЁзұҚгҒ—гҖҒжңҖгӮӮй•·гҒ„й–“гғЎгғігғҗгғјгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮҙгғЎгӮ№гҒ®й«ҳйҹігӮ’й§ҶдҪҝгҒ—гҒҹгӮҲгҒҸжӯҢгҒҶгғҷгғјгӮ№гҒҜгҖҒгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒ®гӮҪгғӯгҒЁеҘҪдёҖеҜҫгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒҜгғҮгӮЈгӮёгғ§гғҚгғғгғҲгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҖҒгӮўгӮ°гғ¬гғғгӮ·гғ–гҒӘжј”еҘҸгӮ’иҒһгҒӢгҒӣгӮӢгҖӮ
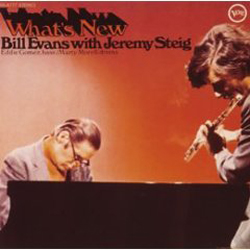
гҖҖгғ»1969.1.30пҪһ5.3 NYCгҖҖWhat's NewпјҲVerveпјүгҖҖJeremy Steig(fl)гҖҒEddie Gomez(b)гҖҒMarty Morell(ds)
гҖҖгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгғ”гӮўгғҺпҪҘгғҲгғӘгӮӘгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғҸгғјгғүгҒӘгғ—гғ¬гӮӨгӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢгӮёгӮ§гғ¬гғҹгғјгғ»гӮ№гӮҝгӮӨгӮ°гҒЁгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒҢгҖҒгҒҢгҒЈгҒ·гӮҠеӣӣгҒӨгҒ«зө„гӮ“гҒ йқһеёёгҒ«гӮўгӮ°гғ¬гғғгӮ·гғ–гҒӘжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
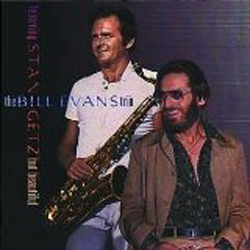
гҖҖпҪҘ1974.8.9пҪһ8.16 HollandгҖҒBelgiumгҖҖBut BeautifulпјҲMilestoneпјүгҖҖStan Getz(ts)гҖҒEddie Gomez(b)гҖҒMarty Morell(ds)
гҖҖгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮӮеҖӢжҖ§жҙҫгҒ®гӮ№гӮҝгғігғ»гӮІгғғгғ„гӮ’гӮІгӮ№гғҲгҒ®иҝҺгҒҲгҒҰгҒ®гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒЁгғҷгғ«гӮ®гғјгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮ’еҸҺйҢІгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒиүІгҖ…гҒЁгӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгҒ®еӨҡгҒ„гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дёӯгҒ®гғ”гғјгӮігғғгӮҜгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ§гҒ®гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒЁгӮІгғғгғ„гҒ®гғҮгғҘгӮӘжј”еҘҸгҒҜгҖҒй¬јж°—иҝ«гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
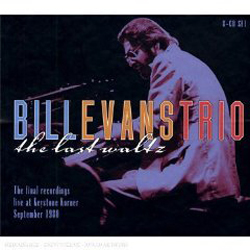
гҖҖпҪҘ1980.8.31пҪһ9.8 San FranciscoгҖҖThe Last WaltzпјҲMilestoneпјүгҖҖMarc Johnson(b)гҖҒJoe LaBarbera(ds)
гҖҖгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒ®жңҖжҷ©е№ҙгҒ®гғҷгғјгӮ·гӮ№гғҲгҒҜгғһгғјгӮҜпҪҘгӮёгғ§гғігӮҪгғігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒҢз„ЎгҒҸгҒӘгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®е№ҙй–“еңЁзұҚгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒҢз„ЎгҒҸгҒӘгӮӢ(80е№ҙ9жңҲ15ж—Ҙ)зӣҙеүҚгҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮ’жҚүгҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғһгғјгӮҜгғ»гӮёгғ§гғігӮҪгғігҒЁгҒ®гӮігғігғ“гҒҜгҖҒгғ•гӮігғғгғҲгғ»гғ©гғ•гӮЎгғӯгҒЁгҒ®гӮігғігғ“гҒ®жј”еҘҸгҒ«жңҖгӮӮиҝ‘гҒ„жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгғ“гғ«пҪҘгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жј”еҘҸгҒҜжІўеұұгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®жҷӮд»ЈжҷӮд»ЈгҒ§гҒ®еҘҪгҒҚгҒӘд»ЈиЎЁзҡ„гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еј•гҒЈејөгӮҠеҮәгҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгӮ’иҒҙгҒҚзөӮгҒҲгҒҹгҒӮгҒЁгҖҒгӮөгғігӮҪгғігғ»гғ•гғ©гғігӮҪгғҜгҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгғ©гғҷгғ«пҪҘгғ”гӮўгғҺжӣІе…ЁйӣҶгҒӢгӮүгҖҒйҒ©еҪ“гҒ«гғ©гғҷгғ«гҒ®гғ”гӮўгғҺжӣІгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжӣІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгғ“гғ«гғ»гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒҢжј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҚ°иұЎгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮеҪјгҒҢгғ©гғҷгғ«гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еј·гҒҸж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖ2е№ҙй–“гҒ®иұҠз”°еёӮиҫІгғ©гӮӨгғ•еүөз”ҹгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®з ”дҝ®гӮӮгҖҒгҒқгӮҚгҒқгӮҚзөӮгӮҸгӮҠгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе®ҹи·өж Ҫеҹ№з•‘гӮӮгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«зүҮд»ҳгҒ‘гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜеҶ¬йҮҺиҸңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒзҷҪиҸңгҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҖҒгӮ«гғӘгғ•гғ©гғҜгғјгҖҒгҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҖҒеӨ§ж №гҖҒгҒӘгҒ©гӮ’дҪңгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҶ¬йҮҺиҸңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҰӮдҪ•гҒ«жӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘жҷӮжңҹгҒҢеӨ§еҲҮгҒӢгӮ’е®ҹж„ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§ж•ҙзҗҶгҒҷгӮӢгҖӮ
8жңҲ30ж—Ҙ
гҒҫгҒ ж®Ӣжҡ‘гҒҢеҺігҒ—гҒ„гҒЁгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҷҪиҸңгҖҒгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒгӮ«гғӘгғ•гғ©гғҜгғјгҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еңҹеЈҢж”№иүҜпјҲе ҶиӮҘгҖҒиӢҰеңҹзҹізҒ°пјүгӮ’е®ҹж–ҪгҖӮ
9жңҲ2ж—Ҙ
зҷҪиҸңгҖҒгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒгӮ«гғӘгғ•гғ©гғҜгғјгҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®е…ғиӮҘгҒЁз•қгҒҹгҒҰгҖӮ
9жңҲ3ж—Ҙ
зҷҪиҸңгҖҒгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒгӮ«гғӘгғ•гғ©гғҜгғјгҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®жӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘гҒЁйҳІиҷ«гғҚгғғгғҲжҺӣгҒ‘гҖӮ
зҷҪиҸңгҒҜж’ӯзЁ®еҫҢ2йҖұй–“гҒҹгҒЈгҒҹиӢ—гӮ’жӨҚгҒҲгҒӨгҒ‘гҒҲгӮӢгҖӮпјҲж №гҒҢејұгҒ„гҒ®гҒ§гҒӘгӮӢгҒ№гҒҸж—©гҒҸжӨҚгҒҲгӮӢпјүгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒгӮ«гғӘгғ•гғ©гғҜгғјгҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒҜжң¬и‘үгҒҢпј”пҪһ5жһҡгҒ«жҲҗгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жӨҚгҒҲгҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒҜиқ¶гӮ„иӣҫгҒ®жҙ»еӢ•гҒҢзӣӣгӮ“гҒӘгҒ®гҒ§йҳІиҷ«гғҚгғғгғҲгҒҜеҝ…й ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁйқ’иҷ«гҒ®йӨҢе ҙгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
9жңҲ11ж—Ҙ
зҷҪиҸңпјҲиҝҪеҠ пјүгӮ’зӣҙжҺҘж’ӯзЁ®гҒҷгӮӢгҖӮ
9жңҲ17ж—Ҙ
еӨ§ж №гҒ®зӣҙжҺҘж’ӯзЁ®пјҲеӨ§ж №гҒҜеҝ…гҒҡзӣҙж’ӯгҒҷгӮӢпјү
10жңҲ12ж—Ҙ
гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒ®зӣҙжҺҘж’ӯзЁ®пјҲгҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгӮӮеҝ…гҒҡзӣҙж’ӯгҒҷгӮӢпјү
10жңҲ7ж—ҘгҒӢгӮү8ж—Ҙ
еҸ°йўЁгҒҢгӮ„гҒЈгҒҰжқҘгҒҰгҖҒеӨ§ж №гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©е…Ёж»…
10жңҲ13ж—Ҙ
еҸ°йўЁгҒ§еӨ§ж №гҒҢгғҖгғЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҖҒ2еӣһзӣ®гҒ®ж’ӯзЁ®гӮ’е®ҹж–ҪгҖӮ
10жңҲ27ж—Ҙ
гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚү(иҝҪеҠ )гҒ®зӣҙжҺҘж’ӯзЁ®
гҖҖд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪңжҘӯзҠ¶жіҒгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒ
пј‘пјүзҷҪиҸңгҒ®зӣҙж’ӯпјҲ9жңҲ11ж—ҘпјүгҒҜ1йҖұй–“йҒ…гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮзҷҪиҸңгҒЁгҒӢгӮӯгғЈгғҷгғ„гҒҜж—ҘгҒҢзҹӯгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҜ’гҒ•гҒҢгӮ„гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁи‘үгҒҢзҗғзөҗгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒҫгҒ§гҒ«20жһҡд»ҘдёҠгҒ®и‘үгҒҢеҮәжқҘгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁдёҠжүӢгҒҸиЎҢгҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ9жңҲ11ж—ҘгҒ§гҒҜиҗҪгҒЎгҒ“гҒјгӮҢгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ
пј’пјүеӨ§ж №гӮ’10жңҲгҒ«и’”гҒҚзӣҙгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠ9жңҲдёӯж—¬гҒҫгҒ§гҒ«и’”гҒӢгҒӘгҒ„гҒЁз„ЎзҗҶгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
пј“пјүгҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгӮ’1еӣһзӣ®гҒЁ2еӣһзӣ®гҒ®й–“йҡ”гӮ’2йҖұй–“зҪ®гҒ„гҒҰи’”гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒй–“йҡ”гҒҜ1йҖұй–“гҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒҜ9жңҲгҒ®еҲқгӮҒгҒ«и’”гҒ‘гҒ°1гғ¶жңҲгҒ§еҸҺз©«гҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒ10жңҲеҲқгӮҒгҒ§1.5гғ¶жңҲгҖҒ11жңҲеҲқгӮҒгҒ§3гғ¶жңҲгҖҒ12жңҲеҲқгӮҒгҒ§5гғ¶жңҲеҸҺз©«гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҶ¬йҮҺиҸңгҒҜгҖҒеҜ’гҒҸгҒӘгӮӢгҒЁз”ҹй•·гҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’й–“йҒ•гҒҲгӮӢгҒЁгҖҒеҜ’гҒ•гҒ®жә–еӮҷгҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒҫгҒЁгӮӮгҒ«еҸҺз©«гҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮжӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘жҷӮжңҹгҒ®еӨ§еҲҮгҒ•гӮ’е®ҹж„ҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ







