|
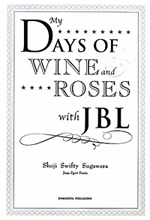

гҖҖжҷӮгҖ…йЎ”гӮ’еҮәгҒҷжң¬еұӢгӮ’иҰҳгҒ„гҒҹгӮүгҖҒдёҖй–ўеёӮгҒ«гҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢгғҷгӮӨгӮ·гғјгҖҚгҒ®еә—дё»гҖҒиҸ…еҺҹжӯЈдәҢгҒ•гӮ“гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹжң¬гҖҢгҒјгҒҸгҒЁгӮёгғ гғ©гғігҒ®й…’гҒЁгғҗгғ©гҒ®ж—ҘгҖ…гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҙ’иҗҪгҒҹиЈ…дёҒгҒ®жң¬гҒҢзӣ®гҒ«з•ҷгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮиҸ…еҺҹгҒ•гӮ“гҒҢгҒҫгҒҹжң¬гӮ’еҮәгҒ—гҒҹгӮ“гҒ гҖҒиІ·гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҖҒгҒЁжҖқгҒЈгҒҰиіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢгғҷгӮӨгӮ·гғјгҖҚгҒҜгӮёгғЈгӮәеҘҪгҒҚгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеҗҚеүҚгҒҸгӮүгҒ„гҒҜиӘ°гҒ§гӮӮзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгӮёгғЈгӮәгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ§гҒҜжңүеҗҚгҒӘеә—гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹз”ҹеүҚгҒ®гӮ«гӮҰгғігғҲпҪҘгғҷгӮӨгӮ·гғјгҒЁж·ұгҒ„иҰӘдәӨгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғҷгӮӨгӮ·гғјгҒҢдҪ•еӣһгҒӢгҒ“гҒ®гҒҠеә—гӮ’иЁӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖ家гҒ«её°гҒЈгҒҰгҖҒжң¬гӮ’иӘӯгҒҝе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮдёҖй–ўгҒ«гҖҢгғҷгӮӨгӮ·гғјгҖҚгҒ®йҹігҒӮгӮҠгҒЁж—Ҙжң¬дёӯгҒ«йіҙгӮҠйҹҝгҒҚгҖҒжқұдә¬гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸж—Ҙжң¬дёӯгҒ®гҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгҒӢгӮүгҒқгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒҚгҒ«жқҘгӮӢгҒҠе®ўгҒ•гӮ“гҒҢгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒҶжҲҗгӮӢгҒ«гҒҜгҒЁгӮ“гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„еҠӘеҠӣгӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢиҸ…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®гҖҒгӮёгғЈгӮәеҶҚз”ҹгҒ«гҒӢгҒ‘гӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒёгҒ®жғ…зҶұгҒҢдёҖжқҜи©°гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжң¬гҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӢгҒӘгӮҠиӘӯгӮ“гҒ§гҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢеҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒд»ҘеүҚгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§иҒһгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰиҸ…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®гҒӢгҒӢгӮҢгҒҹгҖҢгҒӮгҒЁгҒҢгҒҚгҖҚгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жң¬гҒҜд»ҘеүҚгҖҢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢгғҷгӮӨгӮ·гғјгҖҚгҒ®йҒёжҠһгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ§и¬ӣи«ҮзӨҫгӮҲгӮҠеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹжң¬гҒҢзө¶зүҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒй§’иҚүеҮәзүҲгӮҲгӮҠж–°гҒҹгҒ«еҶҚеҮәзүҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгҒјгҒҸгӮӮ18е№ҙеүҚгҒ«иӘӯгӮ“гҒ гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒЈгҒӢгӮҠеҝҳгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖеҝҳгӮҢгҒҹдәӢгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§гҖҒгӮӮгҒҶдёҖеәҰиҸ…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®жӣёгҒӢгӮҢгҒҹжң¬гӮ’иӘӯгҒҝзӣҙгҒ—гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҒҫгҒҹеӨ§гҒ„гҒ«еҲәжҝҖгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®и…•еүҚгҒҜиҸ…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®и¶іе…ғгҒ«гӮӮеҸҠгҒ°гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгӮӮгҒҶдёҖеәҰиҮӘеҲҶгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жң¬гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгӮёгғЈгӮәгғ»гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ
гғ»Basie in London / Count BasieгҖҒVerve
гҖҖиҸ…еҺҹгҒ•гӮ“гҒҢгғҷгӮӨгӮ·гғјгҒЁгҒ®жңҖеҲқгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҖҒж„ҹеӢ•гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҖӮ
гғ»Kelly Blue / Wynton KellyгҖҒRiverside
гҖҖиӢҘгҒ„й ғгҒ«иіје…ҘгҒ—д»ҠгҒ§гӮӮжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғ«гғҗгғ гҖӮ
гғ»The Great Paris Concert / Duke EllingtonгҖҒAtlantic
гҖҖгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ«гӮҲгҒҸдҪҝгҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҖӮ
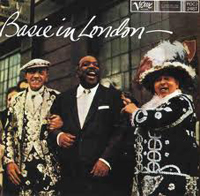

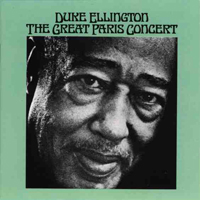
гғ»Mercy, Mercy / Buddy RichгҖҒPacific Jazz
гғҗгғҮгӮЈгғ»гғӘгғғгғҒгҒ®гғүгғ©гғ гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҖӮ
гғ»Waltz for Debby / Bill EvansгҖҒRiverside
гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒ®еӮ‘дҪң
гғ»Crescent / John ColtraneгҖҒimpulse
гҒ“гӮҢгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгӮігғ«гғҲгғ¬гғјгғігҒ®е§ҝгҒҢиҰӢгҒҲгҒҹгҖӮ
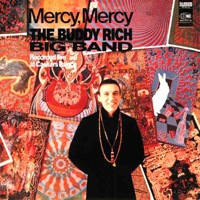
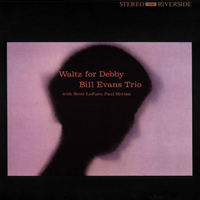

гғ»The Great Jazz Trio at The Village vanguardгҖҒEW
гғҲгғӢгғјпҪҘгӮҰгӮЈгғӘгӮўгғ гҒ®гғүгғ©гғ гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҖӮ
гғ»King Size / Andre PrevinгҖҒContemporary
гӮігғігғҶгғігғқгғ©гғӘгӮӨгҒ®еҘҪйҢІйҹізӣӨгҖӮ
гғ»Out Of The Afternoon / Roy HaynesгҖҒimpulse
гғүгғ©гғ гҒ®йҢІйҹігҒҜгӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№гҒҢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶ1жһҡгҖӮ
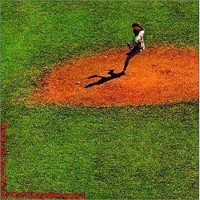
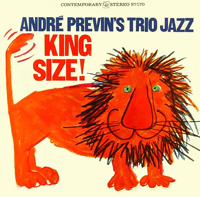
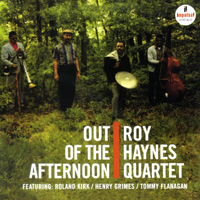
гҒҫгҒ гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгӮӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиЈ…зҪ®гҒ§гҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮ«гӮҰгғ©еҸҺе®№жүҖи„ұиө°дәӢ件гӮ’NHKгҒҢз•Әзө„гҒ§жҺЎгӮҠгҒӮгҒ’гҒҹгҖӮгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ®гӮ«гӮҰгғ©еёӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«з¬¬2ж¬ЎеӨ§жҲҰжҷӮгҒ«жҚ•иҷңеҸҺе®№жүҖгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ж—Ҙжң¬е…өгӮ„гӮӨгӮҝгғӘгӮўе…өгҒҢеҸҺе®№гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҳӯе’Ңпј‘пјҷе№ҙпјҳжңҲпј‘пј‘пјҗпј”еҗҚгҒ®ж—Ҙжң¬е…өгҒҢгӮ«гӮҰгғ©еҸҺе®№жүҖгҒӢгӮүгҒ®йӣҶеӣЈи„ұиө°гӮ’иЁҲз”»гҒ—гҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰпј’пј“пј‘еҗҚгҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҶ…пј“пј‘еҗҚгҒҢиҮӘжұәгҒ—гҒҹгҖӮеҫҢгҒҜе…Ёе“ЎжҚүгҒҲгӮүгӮҢгҖҒйҖғгҒ’гҒҹгӮӮгҒ®гҒҜдёҖдәәгӮӮгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўеҒҙгӮӮиӯҰеӮҷгҒ®еёӮж°‘е…өпј”дәәгҒҢж®әгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еӢ•ж©ҹгҒҜдҪ•гҒӢгҖӮеҸҺе®№жүҖгҒ§иҷҗеҫ…гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒеҫ…йҒҮгҒ«дёҚжәҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҖҢз”ҹгҒҚгҒҰиҷңеӣҡгҒ®иҫұгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҡгҖҒжӯ»гҒ—гҒҰзҪӘзҰҚгҒ®жұҡеҗҚгӮ’ж®ӢгҒҷгҒ“гҒЁеӢҝгӮҢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҲҰйҷЈиЁ“гҒ®ж•ҷгҒҲгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒеј·зЎ¬гҒ«и„ұиө°гӮ’иЁҲз”»гҒ—гҖҒеҗҚиӘүгҒ®жҲҰжӯ»гӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢдәәйҒ”гҒ«еӨҡж•°гҒҢеҫ“гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢж—Ҙжң¬и»ҚгҒ«гҒҜжҚ•иҷңгҒ«гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒ“гҒ®еүҚжҸҗгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒжҚ•иҷңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®еҜҫеҮҰгҒ®д»•ж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®ж•ҷиӮІгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮёгғҘгғҚгғјгғ–еҚ”е®ҡгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹеҜҫеҮҰгҒ§иЁҖгҒҲгҒ°гҖҒе°Ӣе•ҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжӢ’еҗҰжЁ©гӮӮиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е®ҹйҡӣгҒ«жҚ•иҷңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹж—Ҙжң¬дәәгҒҜгҖҒе°Ӣе•ҸгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©зҙ зӣҙгҒ«гҒ—гӮғгҒ№гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮе”ҜдёҖгҒ—гӮғгҒ№гӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢиҮӘеҲҶгҒ®йҡҺзҙҡгҒЁеҗҚеүҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҗҚеүҚгҒҜеҒҪеҗҚгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒҜжҚ•иҷңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹдәӢгҒҢзҹҘгӮҢгӮӢгҒЁе®¶ж—ҸгҒҫгҒ§йқһеӣҪж°‘гҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гӮ’жҒҗгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖеҗҢгҒҳжҚ•иҷңгҒ§гӮӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўе…өгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡиҮӘеҲҶгҒ®еҗҚеүҚгҒЁйҡҺзҙҡгӮ’е ӮгҖ…гҒЁеҗҚд№—гӮӢгҖӮжҚ•иҷңгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӣҪгӮ’д»ЈиЎЁгҒ—гҒҰеүҚз·ҡгҒ§жҲҰгҒЈгҒҹиЁјгҒ§гҒӮгӮҠеҗҚиӘүгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҚд№—гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠ家ж—ҸгҒ«иҮӘеҲҶгҒҢз„ЎдәӢгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰи»ҚдәӢзҡ„гҒ«ж©ҹеҜҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰгҒ—гӮғгҒ№гӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®дҫЎеҖӨиҰігҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬и»ҚгҒ®жҚ•иҷңгҒ®жүұгҒ„гҒ«гӮӮзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҚ•иҷңгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮ„гҒӨгҒҜжҒҘгҒҡгҒ№гҒҚеҘҙгҒ§гҒӮгӮҠдәәйҒ“зҡ„гҒ«жүұгҒҶеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж—Ҙжң¬е…өгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖи©ұгҒҜе…ЁгҒҸеӨүгӮҸгӮӢгҒҢгҖҒзҰҸ島第1еҺҹеӯҗеҠӣзҷәйӣ»жүҖгҒ®дәӢж•…еҮҰзҗҶгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеҺҹеӯҗзӮүгӮ’еҶ·еҚҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еӨ§йҮҸгҒ®жұҡжҹ“ж°ҙгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®жұҡжҹ“ж°ҙгӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮўгғЎгғӘгӮ«гҒЁгғ•гғ©гғігӮ№гҒӢгӮүжҠҖиЎ“гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰеҮҰзҗҶгғ—гғ©гғігғҲгӮ’е»әиЁӯзЁјеӢ•гҒҷгӮӢиЁҳдәӢгҒҢж–°иҒһгҒ«ијүгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜеҺҹеӯҗеҠӣгҒҜе®үе…ЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘдәӢж•…гҒҜзҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®еүҚжҸҗгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒжғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢжҠҖиЎ“гҒ®й–ӢзҷәгӮӮеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзҷәжғігҒ§еӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеӣҪгҒҢдё»еӮ¬гҒҷгӮӢе…¬иҒҙдјҡгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе ҙгҒ§гӮӮгҖҒиіӣжҲҗгҒ®дё–и«–еҪўжҲҗгҒ®гӮ„гӮүгҒӣгҒҢгҖҒйӣ»еҠӣдјҡзӨҫгҒҢеӣҪгҒ®ж„Ҹеҗ‘гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зөҗжһңгҒҜзҸҫзҠ¶гӮ’зӣҙиҰ–гҒҷгӮҢгҒ°жҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгӮӮгҒЈгҒЁиә«иҝ‘гҒӘи©ұгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгӮӢең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®зү©е“Ғиіје…ҘжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒёгҖҒжҠҖиЎ“иҖ…гҒҢй§ҶгҒ‘иҫјгӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҖҢз·ҠжҖҘгҒ«зү©е“ҒгӮ’иіје…ҘгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮж•°еҚғеҶҶзЁӢеәҰгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпј‘жҷӮй–“гҒ§жүӢй…ҚгҒ—гҒҰж¬ІгҒ—гҒ„пјҒгҖҚ件гҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒ„гӮҸгҒҸгҖҢ競дәүе…ҘжңӯгҒ§иіје…ҘгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„пјҒгҖҚгҖҢгҒқгӮҢгҒ§гҒҜй–“гҒ«еҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гӮҲпјҒгҖҚгҖҢй–“гҒ«еҗҲгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«иЁҲз”»зҡ„гҒ«иіје…ҘгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„пјҒгҖҚзөҗеұҖгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»
гҖҖзү©е“Ғиіје…ҘжӢ…еҪ“иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒзү©гӮ’иІ·гҒҶгҒ®гҒҜ競дәүе…ҘжңӯгҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒҜжғіе®ҡеӨ–гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдҪ•гҒӢиө·гҒҚгҒҹжҷӮгҒ«гҖҒгҖҢгҒқгӮҢгҒҜжғіе®ҡеӨ–гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒзөҗжһңгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҺҹеӣ иҝҪ究гӮӮгҒӮгҒ„гҒҫгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶдәӢгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮиІ¬д»»иҝҪеҸҠгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁиүІгҖ…гҒЁйӣЈгҒ—гҒ„йқўгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҶ·йқҷгҒ«ж…ҺйҮҚгҒ«иЎҢгҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҶҚзҷәйҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҺҹеӣ иҝҪ究гҒҜеҫ№еә•зҡ„гҒ«е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮпјҲеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҺҹеӣ иҝҪ究гӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгӮ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒӮгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҒқгҒ®зөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢдәӢгҒҢеӨҡгҒ„пјү
гҖҖиҮӘеҲҶгҒ®иә«гҒ®еӣһгӮҠгҒ«гӮӮгҖҢжғіе®ҡеӨ–гҒ®гҒ“гҒЁгҖҚгӮ’гҒҝгҒҡгҒӢгӮүдҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгҖҒеҶ·йқҷгҒ«иҰӢзӣҙгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ第д№қгҒ®IгҒ•гӮ“гҒҢзҸҫеңЁгҒ®гҖҢ第д№қгҒ®IгҒ®monthlyгғ•гғӯгӮӨгғҮгҖҚгӮ’жӣёгҒҚе§ӢгӮҒгӮӢеүҚгҒ«гӮӮгғ–гғӯгӮ°гӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҒҢгҒ”еӯҳзҹҘгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜеӨ§еӨүиІҙйҮҚгҒӘжғ…е ұжәҗгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢи¶…еҗҚжӣІ150жӣІ--дё–з•ҢгҒҢйҒёгӮ“гҒ гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒҜгҒ“гӮҢгҒ пјҒпјҒгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҠӣдҪңгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒјгҒҸгҒҢдёҖйғЁгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖӮ
гҖҖ
гҖҖеҗ„жӣІгҒ®в‘ пҪһв‘ҰгҒ®ж•°еӯ—гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®еҗҚзӣӨгӮ¬гӮӨгғүгғ–гғғгӮҜгҒ®з•ӘеҸ·гӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢгҒҳз•ӘеҸ·гҒҢиӨҮж•°гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ–гғғгӮҜгҒ§гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒҢиӨҮж•°жҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгҒҫгҒҹз•ӘеҸ·гҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жӣІгҒ®гғҷгӮ№гғҲзӣӨгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖв‘ ж—Ҙжң¬гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ21дё–зҙҖгҒ®еҗҚжӣІеҗҚзӣӨ(йҹіжҘҪд№ӢеҸӢзӨҫ)гҖҖ
гҖҖв‘ЎгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҖҖгҖҖTHE PENGUIN GUIDE TO COMPACT DISCS & DVDs 2005/6 EDITION
гҖҖв‘ўгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҖҖгҖҖGRAMOPHONE THE CLASSICAL GOOD CD & DVD GUIDE 2006
гҖҖв‘Јгғ•гғ©гғігӮ№GUIDE DES CD RECOMPENSES PAR LA PRESSE ET LES GRANDS PRIX(2005-6edition)
гҖҖв‘Өгғ•гғ©гғігӮ№гҖҖгҖҖLE PAVE DANS LA MARE
гҖҖв‘ҘгғүгӮӨгғ„гҖҖгҖҖ CDпјҚFUHLERгҖҖKLASSIK(2003)
гҖҖв‘ҰгӮўгғЎгғӘгӮ«гҖҖгҖҖALLгҖҖMUSICгҖҖGUIDEгҖҖTOгҖҖCLASSICALгҖҖMUSIC(2005)
гҖҖгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гҖҖ*еҚ°пјҡгҖҖгҖҢ第д№қгҒ®IгҖҚгҒ®гҒІгҒЁгҒҸгҒЎгӮігғЎгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ
гҖҖе…Ҳж—ҘгҒјгҒҸгҒҢгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰиҒһгҒ„гҒҹгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гҖҢгӮ¶гғ»гӮ°гғ¬гӮӨгғҲгҖҚгҒ®й …гҒ§гҒҜгҖҒ
гҖҖ93.гӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҖҖдәӨйҹҝжӣІз¬¬8(9)з•ӘгҖҢгӮ¶гғ»гӮ°гғ¬гӮӨгғҲгҖҚ
гҖҖв‘ гғ•гғ«гғҲгғҙгӮ§гғігӮ°гғ©гғјжҢҮжҸ®гғҷгғ«гғӘгғігғ•гӮЈгғ«<1951>(DG POCG3790)
гҖҖв‘ЎгғҙгӮЎгғігғҲжҢҮжҸ®гғҷгғ«гғӘгғігғ•гӮЈгғ«<1995>(RCA BVCC37225)
гҖҖв‘ўгӮ·гғ§гғ«гғҶгӮЈжҢҮжҸ®гӮҰгӮЈгғігғ•гӮЈгғ«<1981>(гғҮгғғгӮ« UCCD5007)
гҖҖв‘ЈгғҙгӮЎгғігғҲжҢҮжҸ®еҢ—гғүгӮӨгғ„ж”ҫйҖҒйҹҝ<1991>(RCA BVCC37089)
гҖҖв‘ӨгӮұгғігғҡжҢҮжҸ®гғҹгғҘгғігғҳгғігғ•гӮЈгғ«<1968>(гӮҪгғӢгғјгҖҖSICC57)
гҖҖв‘ҘгғҙгӮЎгғігғҲжҢҮжҸ®гӮұгғ«гғіж”ҫйҖҒйҹҝ<1977>(RCA BVCC38184пҪһ5)
гҖҖв‘ҰгӮ»гғ«жҢҮжҸ®гӮҜгғӘгғјгғҙгғ©гғігғү<1957>(гӮҪгғӢгғј SRCR2544)
гҖҖ*гғҮгғўгғјгғӢгғғгӮ·гғҘгҒӘгғ•гғ«гғҙгӮ§гғігҖҒгғҙгӮЎгғігғҲгҒ®3зЁ®гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ§жұәе®ҡзҡ„и©•дҫЎгҒ®гӮ·гғ§гғ«гғҶгӮЈгҖҒжҡ–гҒӢгҒ„гӮұгғігғҡгҖҒзІҫз·»гҒӘгӮ»гғ«гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮзҙҚеҫ—гҖӮ
гҖҖ
гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶеҶ…е®№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ¬гӮӨгғүгғ–гғғгӮҜгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ“гӮҢгӮ’з·ЁйӣҶгҒ•гӮҢгҒҹеҠҙеҠӣгӮӮеӨ§еӨүгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒIгҒ•гӮ“гҒ®гҒІгҒЁгҒҸгҒЎгӮігғЎгғігғҲгӮ’иӘӯгҒҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®жј”еҘҸгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйҖ и©ЈгӮӮж·ұгҒҸеӨ§еӨүеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҒһгҒҸгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®гҖҢи¶…еҗҚжӣІ150жӣІгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиҮӘеҲҶгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮ’иҰӢзӣҙгҒ—гҒҹж–№гӮӮгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒјгҒҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иІҙйҮҚгҒӘгғҮгғјгӮҝгҒҢгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫеҹӢгӮӮгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒҜеӨ§еӨүж®ӢеҝөгҒ§д»•ж–№гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒңгҒІгҒЁгӮӮIгҒ•гӮ“гҒҢгҒ“гҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’еҶҚеәҰгғ–гғӯгӮ°гҒ«гӮўгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгӮ’йЎҳгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«й …зӣ®гҒ®иҝҪеҠ гӮ„гҒІгҒЁгҒҸгҒЎгғЎгғўгҒ®ж”№иЁӮгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮҢгҒ°жңӣеӨ–гҒ®е–ңгҒігҒ§гҒҷгҖӮ








