|
гҖҖгғўгғігӮөгғігғҲгҖҒгғҮгғҘгғқгғігҖҒгғҖгӮҰгӮұгғҹгӮ«гғ«гҒЁгҒ„гҒҶдјҒжҘӯеҗҚгҒҜдё–з•ҢгҒ®еӨ§жүӢеҢ–еӯҰдјҡзӨҫгҒЁгҒ—гҒҰеӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ§гҒҜгҖҒгӮ·гғігӮёгӮ§гғігӮҝзӨҫгҒЁгҒ„гҒҶдјҒжҘӯгӮ’еҗҚгҒҜгҒ©гҒҶгҒӢгҖӮе®ҹгҒҜгҒ“гҒ®4зӨҫгҒҜиҫІжҘӯеҲҶйҮҺгҒ§гҒҜдё–з•ҢгҒ®жңҖеӨ§жүӢгҒ§гҖҒдё–з•ҢгҒ®жңүз”ЁгҒӘзЁ®гҒҜгҒ“гҒ®4зӨҫгҒ«зӢ¬еҚ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгӮҝгӮӯгӮӨзЁ®иӢ—пјҲж ӘпјүгҒЁгҒӢпјҲж ӘпјүгӮөгӮ«гӮҝгҒ®гӮҝгғҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹеӣҪз”ЈдјҡзӨҫгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҠйҡЈгҒ®еӣҪйҹ“еӣҪгҒ§гҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еӨ§жүӢзЁ®иӢ—дјҡзӨҫгҒҢдёҠиЁҳ4зӨҫгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®еӯҗдјҡзӨҫгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ·гғігӮёгӮ§гғігӮҝзӨҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®гғҒгғҗгӮ¬гӮӨгӮ®гғјгҖҒиӢұеӣҪгҒ®ICIгҖҒгӮ№гӮЁгғјгғҮгғігҒ®гӮўгӮ№гғҲгғ©гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹеӨ§жүӢдјҒжҘӯгҒ®иҫІжҘӯйғЁй–ҖгҒҢеҗҲдҪөгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ«жң¬йғЁгӮ’зҪ®гҒҸеӨҡеӣҪзұҚдјҒжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгӮёгғҘгғӘгғңгғ•гғӯгӮўгғ–гғ«гҒЁгҒ„гҒҶе•Ҷе“ҒгҒҜгҖҒгӮ·гғігӮёгӮ§гғігӮҝзӨҫгҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҹж–°еһӢгҒ®ж®әиҷ«еүӨгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ2010е№ҙ1жңҲгҒ«иҫІи–¬зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҖҒ3жңҲгҒӢгӮүиІ©еЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒд»ҠжңҲгҒ§зҷәеЈІгҒӢгӮү2.5е№ҙгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮ·гғігӮёгӮ§гғігӮҝзӨҫгҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҹиҫІи–¬гҒ«гҒҜгҖҒж®әиҷ«еүӨгҒЁгҒ—гҒҰгӮўгӮҜгӮҝгғ©гҖҒгӮўгғ•гӮЎгғјгғ гҖҒгғҲгғӘгӮ¬гғјгғүгҖҒгғһгғғгғҒгҒӘгҒ©гҒҢгҖҒж®әиҸҢеүӨгҒЁгҒ—гҒҰгӮўгғҹгӮ№гӮҝгғј20гҖҒгғӘгғүгғҹгғ«MZгҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮзү№гҒ«гӮўгӮҜгӮҝгғ©гҒҜгғҚгӮӘгғӢгӮігғҒгғҺгӮӨгғүзі»гҒ®гғҒгӮўгғЎгғҲгӮӯгӮөгғ гҒЁгҒ„гҒҶеҢ–еӯҰжҲҗеҲҶгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹж–°гҒ—гҒ„ж®әиҷ«еүӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®гӮёгғҘгғӘгғңгғ•гғӯгӮўгғ–гғ«гҒЁгӮҲгҒҸдјјгҒҹе•Ҷе“ҒгҒ«гҖҒгғҮгғҘгғқгғігҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҰ2009е№ҙгҒ«иҫІи–¬зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹгғ—гғ¬гғҗгӮҪгғігғ•гғӯгӮўгғ–гғ«5гҒЁгҒ„гҒҶе•Ҷе“ҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮўгғігғҲгғ©гғӢгғ«гӮёгӮўгғҹгғүзі»гҒ®гӮҜгғӯгғ©гғігғҲгғ©гғӢгғӘгғ—гғӯгғјгғ«гҒЁгҒ„гҒҶеҢ–еӯҰжҲҗеҲҶгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹи–¬еүӨгҒ§гҖҒжҳҶиҷ«гҒ«зӯӢиӮүејӣз·©еүӨгҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒ—гҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰжҳҶиҷ«гӮ’йӨ“жӯ»гҒ•гҒӣгӮӢгҖӮеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢжҳҶиҷ«гҒҜгғҒгғ§гӮҰзӣ®гҒҠгӮҲгҒігғҸгӮЁзӣ®е®іиҷ«гҒ«й«ҳгҒ„еҠ№жһңгӮ’зҷәжҸ®гҒҷгӮӢгҖӮдҪҝз”Ёжі•гҒҜеҫ“жқҘгҒ®ж•Јеёғжі•гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒгғқгғғгғҲиӢ—гҒ®зҒҢжіЁеҮҰзҗҶгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеҚ“еҠ№гӮ’зӨәгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮёгғҘгғӘгғңгғ•гғӯгӮўгғ–гғ«гҒҜгӮўгӮҜгӮҝгғ©гҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгғҒгӮўгғЎгғҲгӮӯгӮөгғ гҒ«гғҮгғҘгғқгғігҒ®й–ӢзҷәгҒ—гҒҹгӮҜгғӯгғ©гғігғҲгғ©гғӢгғӘгғ—гғӯгғјгғ«гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰиӨҮеҗҲеҢ–гҒ—гҒҹиҫІи–¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҒгӮўгғЎгғҲгӮӯгӮөгғ гҒ«гҒҜжҳҶиҷ«гҒ®зҘһзөҢдјқйҒ”зі»гҒ®еӣһи·ҜгӮ’йҳ»е®ігҒҷгӮӢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒЁгӮҜгғӯгғ©гғігғҲгғ©гғӢгғӘгғ—гғӯгғјгғ«гҒ«гӮҲгӮӢжҳҶиҷ«гҒ®зӯӢиӮүејӣз·©еүӨеҠ№жһңгҒҢиӨҮеҗҲгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢжҳҶиҷ«гҒҜгғҒгғ§гӮҰзӣ®гҒҠгӮҲгҒігғҸгӮЁзӣ®е®іиҷ«гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒгғ—гғ¬гғҗгӮҪгғігғ•гғӯгӮўгғ–гғ«5гҒ§гҒҜеҠ№жһңгҒ®гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғҚгӮ®гӮўгӮ¶гғҹгӮҰгғһгӮ„гӮўгғ–гғ©гғ гӮ·гҒ«гӮӮеҠ№жһңгӮ’зҷәжҸ®гҒҷгӮӢгҖӮдҪҝз”Ёжі•гҒҜгғқгғғгғҲиӢ—гҒ®зҒҢжіЁеҮҰзҗҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҒҢжіЁгҒ«гӮҲгӮҠж №гҒӢгӮүеҗёеҸҺгҒ•гӮҢгҒҹжҲҗеҲҶгҒҢзҙ„1гҒӢжңҲгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеҠ№жһңгӮ’жҢҒз¶ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒгғҸгӮҜгӮөгӮӨгҖҒгғ¬гӮҝгӮ№гҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®е®ҡжӨҚжҷӮгҒ®йҳІиҷ«еҜҫзӯ–гҒ«еӨ§еӨүжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
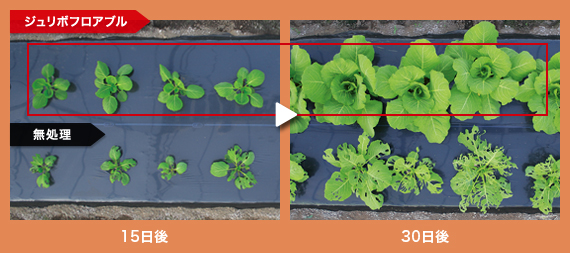
гҖҖд»Ҡе№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӯгғЈгғҷгғ„гҖҒгғҸгӮҜгӮөгӮӨгҖҒгғ¬гӮҝгӮ№гҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®е®ҡжӨҚгҒ«гӮёгғҘгғӘгғңгғ•гғӯгӮўгғ–гғ«гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒҢгҖҒгӮ·гғігӮёгӮ§гғігӮҝгӮёгғЈгғ‘гғігҒҢе…¬й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҠ№жһңгҒ®еҶҷзңҹгҒЁе…ЁгҒҸеҗҢгҒҳзөҗжһңгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠйҳІиҷ«гғҚгғғгғҲгҒӘгҒ©гҒ®жүӢй–“гҒҢеӨ§е№…гҒ«зңҒгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒҜеӨ§гҒ„гҒ«жҷ®еҸҠгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖиҫІжҘӯгӮӮж–°гҒ—гҒ„жҠҖиЎ“гҒҢзўәе®ҹгҒ«жҷ®еҸҠгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеәғгҒҸжҷ®еҸҠгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒдҫЎж јгҒҢиӘІйЎҢпјү

гҖҖдёҖжҳЁж—ҘгҖҒиҝ‘гҒҸгҒ®еҸӢдәәгҒҢ3дәәгҖҒжҲ‘гҒҢ家гҒ«йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҚгҒ«йҒҠгҒігҒ«жқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜзҡҶгҒ§гӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢдёҖдәәгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜеғ•гҒҜгӮ№гғҲгғ©гғҙгӮЈгғігӮ№гӮӯгғјгҒ®жҳҘгҒ®зҘӯе…ёгҒҢеӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғ–гғјгғ¬гғјгӮәгҒҢгӮҜгғӘгғјгғ–гғ©гғігғүдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒЁ1991е№ҙ3жңҲгҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹCDпјҲDGпјүгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰиҒһгҒҚе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒӘгӮүгҒ°гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ§гҖҒжүӢжҢҒгҒЎгҒ®LPгӮ’гҒ”гҒқгҒ”гҒқеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰдёӢгҒ®дёҖиҰ§иЎЁгҒ«гҒӮгӮӢгғҸгғ«гӮөгӮӨгҒ®гҒ•гӮҸгӮҠгҒ®йғЁеҲҶгӮ’иҒһгҒҚе§ӢгӮҒгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁжј”еҘҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж„ҸиҰӢдәӨжҸӣгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
| гӮ№гғҲгғ©гғҙгӮЈгғігӮ№гӮӯгғјгҖҖгҖҢжҳҘгҒ®зҘӯе…ёгҖҚ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | жҢҮжҸ®иҖ… | гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ© | гғ¬гғјгғҷгғ« | з•ӘеҸ· | е№ҙ | жңҲ | гӮігғЎгғігғҲгҖҖ*1 |
| пј‘ | гғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғўгғігғҲгӮҘгғј | гғ‘гғӘйҹіжҘҪйҷўз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | LONDON | GT 2013-4 | 1956 | 11 | еҲқжј”иҖ…гҒ«гӮҲгӮӢжј”еҘҸ |
| пј’ | гғ¬гғҠгғјгғүгғ»гғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғі | гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гғ•гӮЈгғ« | CBS-SONY | 13AC 21 | 1958 | 7 | зҶұж°—гҒӮгҒөгӮҢгҒҹжј”еҘҸпјҲпј“гҒҜпј’гҒЁеҗҢгҒҳжј”еҘҸгӮ’гғҹгғігғҲгҒҢеҲ¶дҪң йҹігҒҢж јж®өгҒ«иүҜгҒ„пјү |
| пј“ | гғ¬гғҠгғјгғүгғ»гғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғі | гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гғ•гӮЈгғ« | FRANKLIN MINT | 83 | 1958 | 7 | |
| пј” | гӮӨгғјгӮҙгғӘгғ»гғһгғ«гӮұгғҙгӮЈгғғгғҒ | гғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгӮўз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | EMI | AA/5039 | 1959 | 2 | гғӯгӮ·гӮўзҡ„йҮҺз”ҹе‘і |
| пј• | гғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғ–гғјгғ¬гғјгӮә | гғ•гғ©гғігӮ№еӣҪз«Ӣж”ҫйҖҒз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | COLUMBIA | OC-7260-PK | 1963 | 6 | |
| пј– | гғҳгғ«гғҷгғ«гғҲгғ»гғ•гӮ©гғігғ»гӮ«гғ©гғӨгғі | гғҷгғ«гғӘгғігғ»гғ•гӮЈгғ« | DG | SLGM-1260 | 1963 | 10 | ж©ҹиғҪзҫҺгҒ®жҘөиҮҙ |
| пј— | гғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғ–гғјгғ¬гғјгӮә | гӮҜгғӘгғјгғ–гғ©гғігғүгғ»гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ© | CBS-SONY | пј’пјҗAC 1546 | 1969 | 7 | зІҫеҰҷзІҫз·» гӮҜгғјгғ«гҒ«еҶҙгҒҲгӮҸгҒҹгӮӢ |
| пјҳ | гғ¬гғҠгғјгғүгғ»гғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғі | гғӯгғігғүгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | CBS-SONY | FCCA 535 | 1972 | 4 | |
| пјҷ | гӮІгӮӘгғ«гӮ°гғ»гӮ·гғ§гғ«гғҶгӮЈ | гӮ·гӮ«гӮҙгғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғј | LONDON | K18C-9233 | 1974 | 5 | иҰӢйҖҡгҒ—гҒ®иүҜгҒ•гҒЁйҹіжҘҪгҒ®зҶұгҒ• |
| 10 | гӮҜгғ©гӮҰгғҮгӮЈгӮӘгғ»гӮўгғҗгғү | гғӯгғігғүгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | DG | MG 1012 | 1975 | 2 | зҙ°йғЁгҒ®жҠҪеҮәгҒҢиЎқж’ғзҡ„ |
| 11 | гғҳгғ«гғҷгғ«гғҲгғ»гғ•гӮ©гғігғ»гӮ«гғ©гғӨгғі | гғҷгғ«гғӘгғігғ»гғ•гӮЈгғ« | DG | MG 1088 | 1975 | 12 | ж©ҹиғҪзҫҺгҒ®жҘөиҮҙ |
| 12 | гӮігғӘгғігғ»гғҮгӮЈгғҙгӮЈгӮ№ | гӮўгғ гӮ№гғҶгғ«гғҖгғ гғ»гӮігғігӮ»гғ«гғҲгғҳгғңгӮҰ | PHILIPS | X-7783 | 1976 | 11 | е…ЁдҪ“гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ®иүҜгҒ•гҒЁйҹіжҘҪгҒ®иіӘгҒ®й«ҳгҒ• |
| 13 | гӮәгғјгғ“гғігғ»гғЎгғјгӮҝ | гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гғ•гӮЈгғ« | CBS-SONY | пј’пј“AC501 | 1977 | 9 | |
| 14 | е°ҸжІўеҫҒзҲҫ | гғңгӮ№гғҲгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | PHILIPS | пј’пј•PC-101 | 1979 | 12 | |
| 15 | гӮўгғігӮҝгғ«гғ»гғүгғ©гғҶгӮЈ | гғҮгғҲгғӯгӮӨгғҲгғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғј | LONDON | L28C-1110 | 1981 | 5 | гғҗгғ¬гӮЁйҹіжҘҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҳҘзҘӯ |
| 16 | гғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғ–гғјгғ¬гғјгӮә | гӮҜгғӘгғјгғ–гғ©гғігғүгғ»гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ© | DG | 435 769-2 *2 | 1991 | 3 | гӮІгғ«гӮ®гӮЁгғ•гҒЁеҸҚеҜҫгҒ®жҘөиҮҙ |
| 17 | гғҜгғ¬гғӘгғјгғ»гӮІгғ«гӮ®гӮЁгғ• | гӮӯгғјгғӯгғ•жӯҢеҠҮе ҙз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | PHILIPS | UCCP-1035 | 1999 | 7 | еҺҹе§Ӣзҡ„гҒӘйҹігҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғј |
| *1гҖҢзҸҫд»ЈеҗҚзӣӨй‘‘е®ҡеӣЈгҖҚе°Ҹжһ—еҲ©д№ӢгҖҒжө…йҮҢе…¬дёүз·Ёи‘—гӮҲгӮҠгҒ®дёҖеҸЈгӮігғЎгғігғҲгҒ®еј•з”Ё *2 жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҒҹCD |
|||||||
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгғҸгғ«гӮөгӮӨгҒ«гҒҜй©ҡгҒҸгҒ»гҒ©иЎЁзҸҫгҒ«е№…гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҷгҒЈгҒӢгӮҠжҷӮгҒ®гҒҹгҒӨгҒ®гӮӮеҝҳгӮҢгҒҰжҘҪгҒ—гҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒјгҒҸзҡ„гҒ«гҒҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒ«жңҖгӮӮиҝ«еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢгӮігғӘгғігғ»гғҮгӮӨгғҙгӮЈгӮ№жҢҮжҸ®гҖҒгӮўгғ гӮ№гғҶгғ«гғҖгғ гӮігғігӮ»гғ«гғҲгғҳгғңгӮҰгҒ®жј”еҘҸгҒҢж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгӮӨгғјгӮҙгғӘгғ»гғһгғ«гӮұгғҙгӮЈгғғгғҒжҢҮжҸ®гҖҒгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгӮўз®ЎејҰжҘҪеӣЈгҒ®гғҶгғігғқгҒ®йҖҹгҒ„йҮҺжҖ§зҡ„гҒӘжј”еҘҸгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒЁгҖҒиЁҖгҒ„еҮәгҒҷгҒЁгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҝгӮ“гҒӘгҒ§гҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁжҘҪгҒ—гҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖиӢұиӘһгҒ§resurgenceгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҶҚиө·гҒЁгҒӢеҫ©жҙ»гҖҒеҶҚзҮғгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒ®еҗҚи©һгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒЁгҒ—гҒҰгғӘгӮөгғјгӮёгӮ§гғігӮ№гҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒЁж„Ҹе‘ігҒҢйҒ•гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮиҫІж–ҮеҚ”гҒ®гғ«гғјгғ©гғ«йӣ»еӯҗеӣіжӣёйӨЁгҒ®зҸҫд»ЈиҫІжҘӯз”ЁиӘһйӣҶгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғӘгӮөгғјгӮёгӮ§гғігӮ№гҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢгғҸгғҖгғӢгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§иҫІи–¬гӮ’ж•ЈеёғгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰгғҸгғҖгғӢгҒҢгҒөгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе®іиҷ«йҳІйҷӨгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иҫІи–¬гӮ’ж•ЈеёғгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе®іиҷ«гҒҢж•ЈеёғеүҚгӮҲгӮҠгӮӮгҒөгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒиҫІи–¬гӮ’ж•ЈеёғгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰеӨҡгҒҸгҒӘгӮӢзҸҫиұЎгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ®иҰҒеӣ гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒпјҲ1пјүеӨ©ж•өгҒ®жёӣе°‘гҖҒпјҲ2пјү競дәүзЁ®гҒ®йҷӨеҺ»гҖҒпјҲ3пјүиҫІи–¬гҒҢеҜ„дё»жӨҚзү©гҒ®з”ҹзҗҶгӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢй–“жҺҘзҡ„гҒӘе®іиҷ«гҒ®еў—ж®–зҺҮгҒ®дёҠжҳҮгҖҒпјҲ4пјүиҫІи–¬гҒ®зӣҙжҺҘеҲәжҝҖгҒ«гӮҲгӮӢеҮәз”ҹзҺҮгҒ®еў—еҠ гҖҒпјҲ5пјүж®әиҷ«еүӨжҠөжҠ—жҖ§е®іиҷ«гҒ®еҮәзҸҫгҖҒгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгғ гғҖгҒӘиҫІи–¬ж•ЈеёғгҒҜгғ гғҖгҒӘгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒҷгҒҫгҒӘгҒ„гҖӮеӨ©ж•өгӮ’ж®әгҒ—гҖҒгҒҹгҒ гҒ®иҷ«гӮ’ж®әгҒ—гҖҒз”°гҒ®дёӯгҒ®иҷ«гҒ®дё–з•ҢгӮ’дёҚе®үе®ҡгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гғӘгӮөгғјгӮёгӮ§гғігӮ№гҒёгҒ®зқҖзӣ®гҒҜгҒқгҒ®еҫҢгҖҒз”°гӮ“гҒјгҒ”гҒЁгҒ«йҒ•гҒҶе®іиҷ«гҒ®зҷәз”ҹзҠ¶жіҒгӮ’иҷ«иҰӢжқҝгҒ§иҫІе®¶иҮӘгӮүзўәгҒӢгӮҒгӮӢжёӣиҫІи–¬гҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ«зҷәеұ•гҒ—гҖҒеӨ©ж•өгӮ’з”ҹгҒӢгҒҷйҳІйҷӨгҒёгҒ®йҒ“гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸеәғгҒ’гҒҹгҖӮгҖҚ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶзҸҫиұЎгҒҜзҹҘиӯҳгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒе®ҹж„ҹгҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгӮҸгҒӢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»Ҡе№ҙгҒ®еӨҸгҒ«гҒ©гҒҶгӮӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮ’дҪ“йЁ“гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҜгғҠгӮ№гӮ’е°‘гҒ—гҒ°гҒӢгӮҠж Ҫеҹ№гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжҳҘгҒӢгӮүеӨҸгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгӮўгғ–гғ©гғ гӮ·гӮ„гӮігғҠгӮёгғ©гғҹгҒЁгҒ„гҒҶе®іиҷ«гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°жӮ©гҒҫгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжіЁж„ҸгҒ—гҒҰйҳІйҷӨгҒ«еҠӘгӮҒгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»Ҡе№ҙгҒ®еӨҸгҒ«гӮўгғ–гғ©гғ гӮ·гӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠйҖҖжІ»гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҖҒгӮўгғ–гғ©гғ гӮ·гҒ«еҚ“еҠ№гҒ®гҒӮгӮӢеҗҲжҲҗгғ”гғ¬гӮ№гғӯгӮӨгғүзі»гҒ®и–¬еүӨгғҲгғ¬гғңгғіпјҲгӮЁгғүгғ•гӮ§гғігғ—гғӯгғғгӮҜгӮ№еүӨпјүгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®з”Іж–җгҒӮгҒЈгҒҰгӮўгғ–гғ©гғ гӮ·гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еұ…гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒ—гҒҰз•‘гӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгғҠгӮ№гҒ®з•‘дёҖйқўгҒ«гғҸгғҖгғӢгҒҢеӨ§зҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜ8жңҲгҒЁгҒ„гҒҶгғҸгғҖгғӢгҒ®зҷәз”ҹгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„жҷӮжңҹгҒ«гғҲгғ¬гғңгғігӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғҶгғігғҲгӮҰгғ гӮ·гҒЁгҒӢгғҸгғҖгғӢгӮўгӮ¶гғҹгӮҰгғһгҖҒгӮ«гғЎгғ гӮ·гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҸгғҖгғӢгҒ®еӨ©ж•өгӮ’жёӣе°‘гҒ•гҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒгҒҫгҒҹ競дәүзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢгӮўгғ–гғ©гғ гӮ·гҒҢжёӣгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҲгғ¬гғңгғігҒҢгғҸгғҖгғӢгҒ«гҒҜз„ЎжҜ’гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгғҸгғҖгғӢгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеў—ж®–гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’йҳІгҒҗгҒ«гҒҜгҖҒгғҸгғҖгғӢгҒ®зҷәз”ҹгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„жҷӮжңҹгҒ®гӮўгғ–гғ©гғ гӮ·йҖҖжІ»гҒ«гҒҜгҖҒгғҸгғҖгғӢгҒ«гӮӮеҠ№жһңгҒ®гҒӮгӮӢи–¬еүӨгӮ’йҒёе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гғҲгғ¬гғңгғігҒ«ж®әгғҖгғӢеүӨгӮ’дҪөз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҒҜгғҖгғӢгҒ«гӮӮеҠ№жһңгҒ®гҒӮгӮӢеҗҲжҲҗгғ”гғ¬гӮ№гғӯгӮӨгғүзі»гҒ®и–¬еүӨгғһгғ–гғӘгғғгӮҜпјҲгғ•гғ«гғҗгғӘгғҚгғјгғҲеүӨпјүгҒӘгҒ©гӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«еӨ§дәӢгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз•‘гҒ®еӣһгӮҠгҒ«гӮҪгғ«гӮ¬гғ гҒӘгҒ©гӮ’жӨҚгҒҲгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е®іиҷ«гҒ®еӨ©ж•өгӮ’е‘јгҒіеҜ„гҒӣгҒҰгҖҒе®іиҷ«гҒҢз•°еёёз№Ғж®–гҒ—гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠзҘһзөҢиіӘгҒ«гҒӘгӮүгҒҡгҒ«гҖҒжёӣиҫІи–¬гӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜиҫІжҘӯгҒ®и©ұгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдәәй–“гҒ®дё–з•ҢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжҠ—з”ҹзү©иіӘгӮ’еӨҡз”ЁгҒҷгӮӢз—…йҷўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иҖҗжҖ§иҸҢгҒҢеҮәзҸҫгҒ—гҒҰгҖҒеӨҡж•°гҒ®йҷўеҶ…ж„ҹжҹ“гҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҖҒгғӘгӮөгғјгӮёгӮ§гғігӮ№зҸҫиұЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ
гҖҖдҫҝеҲ©гҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢи–¬еүӨгӮӮгҖҒйҒҺгҒҺгҒҹгӮӢгҒҜеҸҠгҒ°гҒ–гӮӢгҒҢгҒ”гҒЁгҒ—гҒ§гҖҒеӨҡз”ЁгҒҷгӮӢгҒЁжҖқгӮҸгҒ¬иҗҪгҒЁгҒ—з©ҙгҒ«гҒҜгҒҫгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮ’гҖҒиә«гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰдҪ“йЁ“гҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒјгҒҸгҒ®и¶Је‘ігҒ§гҒӮгӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒд»ҘеүҚгҒҜгӮұгғјгғ–гғ«1жң¬еӨүгҒҲгҒҹгӮүгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҹігҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒӢиҖігӮ’йҮқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з ”гҒҺжҫ„гҒҫгҒ—гҒҰгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҒқгӮҢгҒ§гӮҲгҒ„зөҢйЁ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжӯЈзӣҙйҹіжҘҪгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ«гҒҜдҪҷиЈ•гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒ“гҒ гӮҸгӮүгҒҡгҒ«йҹіжҘҪгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒӮгҒҫгӮҠзҘһзөҢиіӘгҒ«гҒӘгӮүгҒҡгҒ«гҖҒдҪ•дәӢгӮӮгҖҒгҒ„гҒ„еҠ жёӣпјҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжҳЁе№ҙгҒ®10жңҲд»ҘйҷҚгҖҒж°—еҲҶгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгҒҫгӮҠйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еј•гҒҚгҒҡгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒе№ҙжң«е№ҙе§ӢгҒҜгӮӮгҒЈгҒұгӮүиӘӯжӣёгӮ’гҒ—гҒҰйҒҺгҒ”гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёӯгҒ§гӮӮеҒ¶з„¶жүӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖҢзҷҪе·қйқҷгғ»жјўеӯ—гҒ®дё–з•ҢиҰігҖҚжқҫеІЎжӯЈеүӣи‘—гҖҒе№іеҮЎзӨҫж–°жӣёгӮ’иӘӯгҒҝе§ӢгӮҒгҖҒзҷҪе·қйқҷгҒ•гӮ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҹгҒ„гҒқгҒҶиҲҲе‘ігҒҢ湧гҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жң¬гҒҜзҷҪе·қйқҷгҒ®дё–з•ҢгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е…Ҙй–ҖжӣёгҒЁгҒ—гҒҰи‘—иҖ…гҒҢжӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҶ…е®№гӮ’зӣ®ж¬ЎгҒ§зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ
пј‘пјҺж–Үеӯ—гҒҢдё–з•ҢгӮ’жҶ¶гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢ
пј’пјҺе‘ӘиғҪгӮ’гӮӮгҒӨжјўеӯ—
пј“пјҺеҸӨд»ЈдёӯеӣҪгӮ’е‘јеҗёгҒҷгӮӢ
пј”пјҺеҸӨд»ЈжӯҢи¬ЎгҒЁиҲҲгҒ®ж–№жі•
пј•пјҺе·«зҘқзҺӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж°‘дҝ—еӯҰ
пј–пјҺзӢӮеӯ—гҒӢгӮүйҒҠеӯ—гҒ«гҒҠгӮҲгҒ¶
пј—пјҺжјўеӯ—гҒЁгҒ„гҒҶеӣҪиӘһ
гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶз« з«ӢгҒҰгҒ§и©ігҒ—гҒҸзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӘгҒӢгҒ§гӮӮз”ІйӘЁж–ҮгҖҒйҮ‘ж–ҮгҒ®з ”究гҒ®еҹәгҒҡгҒҸжјўеӯ—гҒ®зҙ№д»ӢгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«зӣ®гҒӢгӮүйұ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж–Үеӯ—гҒҜиЁҖи‘үгҒ®еҸҚжҳ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЁҖи‘үгҒҜжҖқжғігҒ®еҸҚжҳ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶз«Ӣе ҙгҒ§з”ІйӘЁж–ҮгӮ’иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸгҒЁгҖҒеҪ“жҷӮпјҲж®·гҒ®жҷӮд»ЈпјүгҒ®еҸӨд»ЈдәәгҒ®иҖғгҒҲж–№гҒҫгҒ§гҒҜиҰӢгҒҲгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒзҷҪе·қгғҜгғјгғ«гғүгҒ«еј•гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ
гҖҖзҷҪе·қгҒ•гӮ“гҒ®ж–Үеӯ—еӯҰгҒ®йӣҶеӨ§жҲҗгҒҢгҖҢеӯ—зөұгҖҚгҖҢеӯ—иЁ“гҖҚгҖҢеӯ—йҖҡгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ3гҒӨгҒ®еӯ—жӣёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖж–°иЁӮгҖҢеӯ—зөұгҖҚе№іеҮЎзӨҫгғ»жҷ®еҸҠзүҲгҖҒ1107гғҡгғјгӮёгҖҒ6300еҶҶгҖҒжјўеӯ—гҒ®жҲҗгӮҠз«ӢгҒЎгӮ’зҹҘгӮӢеӯ—жәҗиҫһе…ё
гҖҖж–°иЁӮгҖҢеӯ—иЁ“гҖҚе№іеҮЎзӨҫгғ»жҷ®еҸҠзүҲгҖҒ944гғҡгғјгӮёгҖҒ6300еҶҶгҖҒж—Ҙжң¬иӘһгҒЁжјўеӯ—гҒ®еҮәдјҡгҒ„гӮ’жҺўгӮӢеҸӨиӘһиҫһе…ё
гҖҖгҖҢеӯ—йҖҡгҖҚе№іеҮЎзӨҫгғ»еӨ§еһӢжң¬гҖҒ2094гғҡгғјгӮёгҖҒ23000еҶҶгҖҒеӯ—жӣёдёүйғЁдҪңгҒ®жҺүе°ҫгӮ’йЈҫгӮӢжјўе’Ңиҫһе…ё
гҖҖгҒ“гӮҢгӮ’зҷҪе·қгҒ•гӮ“гҒҜ13е№ҙгҒ®жӯіжңҲгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰдёҖдәәгҒ§е®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮгҒјгҒҸгҒҜдёӯиә«гӮ’жң¬еұӢгҒ§е°‘гҒ—иӘӯгӮ“гҒ гҒҢгҒҫгҒ жүӢе…ғгҒ«гҒҜжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—иҝ‘гҒ„е°ҶжқҘжүӢе…ғгҒ«зҪ®гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖзҷҪе·қгҒ•гӮ“иҮӘиә«гҒ®жң¬гӮ’иӘӯгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁгҒҠгӮӮгҒ„гҖҒгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡиҝ‘гҒҸгҒ®жң¬еұӢгҒ«еҮәеҗ‘гҒҚж¬ЎгҒ®4еҶҠгҒ®жң¬гӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢжјўеӯ—гҖҚзҷҪе·қйқҷи‘—гҖҒеІ©жіўж–°жӣё
гҖҖгҖҢеӯ”еӯҗдјқгҖҚзҷҪе·қйқҷи‘—гҖҒдёӯе…¬ж–Үеә«
гҖҖгҖҢе‘ӘгҒ®жҖқжғігҖҚзҷҪе·қйқҷгҖҒжў…еҺҹзҢӣеҜҫи«ҮйӣҶгҖҒе№іеҮЎзӨҫгғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘгғј
гҖҖгҖҢеӣһжғі90е№ҙгҖҚзҷҪе·қйқҷи‘—гҖҒе№іеҮЎзӨҫгғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘгғј
гҖҖгҖҢжјўеӯ—гҒҜгҖҚ1970е№ҙгҖҒзҷҪе·қйқҷ60жүҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҲқгӮҒгҒҰдёҖиҲ¬еҗ‘гҒ‘иӘӯиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жӣёгҒҚдёӢгӮҚгҒ—гҒҹжң¬гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй–ўеҝғгҒӮгӮӢиӘӯиҖ…гҒ«иЎқж’ғгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҢжқҫеІЎжӯЈеүӣгҒ•гӮ“гҒҢзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢеӣһжғі90е№ҙгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒ®дёӯгҒ§е®®еҹҺи°·жҳҢе…үгҒ•гӮ“гҒЁеҜҫи«ҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢз« гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе®®еҹҺи°·гҒ•гӮ“гҒҜзҷҪе·қгҒ•гӮ“гҒ®и‘—дҪңгӮ’еӢүеј·гҒ—гҒҰе°ҸиӘ¬гӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҜҫи«ҮгҒ®з®ҮжүҖгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖе®®еҹҺи°·гҖҢгғ»гғ»гғ»е°ҸиӘ¬гӮ’жӣёгҒҸгҒЁгҒҚгҒ«еҸҚеҜҫгҒ«иӢҰгҒ—гӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҸӨд»ЈгҒ®дәәгҒҢдҪҸгӮҖ家гӮ’гҖҒгҒ„гҒҫгҒ®гҖҢ家гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӯ—гҒ§жӣёгҒҸгҒЁгҖҒжҰӮеҝөзҡ„гҒ«йҒ•гҒҶгҖӮгҖҢе®®гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӯ—гӮ’жӣёгҒ‘гҒ°гҒ„гҒ„гӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҒ‘гҒ©гӮӮгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҜе®®ж®ҝгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒӘ家еұӢгӮ’жҖқгҒ„жө®гҒӢгҒ№гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғ»гғ»гғ»гҖҚ
гҖҖзҷҪе·қгҖҢгҖҢ家гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӯ—гҒҜгҒӯгҖҒз”ІйӘЁж–ҮгҒ§гҒҜгҖҢеӨ§д№ҷгҒ®е®¶гҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶзҘ–е…ҲгҒ®зҺӢж§ҳгҒ®еҗҚеүҚгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰжӣёгҒӢгӮҢгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзҘҖгӮӢе ҙжүҖгӮ’иЁҖгҒҶгҖӮгҒҹгҒ„гҒҰгҒ„гҒ®иҫһжӣёгҒҜгҖҢиұҡгҒЁдёҖз·’гҒ«дҪҸгӮҖгҖҚгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮиұҡгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒ“гӮҢгҒҜзҠ¬гҖӮе»әзү©гӮ’е»әгҒҰгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«дёӢгҒ«еҹӢгӮҒгӮӢзҠ зүІгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢеЎҡгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӯ—гӮӮеҗҢж§ҳгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶзҠ зүІгӮ’еҹӢгӮҒгҒҰгҖҒеў“жүҖгҒЁгҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҖӮгғ»гғ»гғ»гҖҚ
гҖҖе®®еҹҺи°·гҒ•гӮ“гҒҜгҖҒзҷҪе·қйқҷгҒ®з ”究жҲҗжһңгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҰгҖҒдёӯеӣҪгҒ®еҸӨд»ЈгӮ’е ҙйқўгҒЁгҒ—гҒҹгҖҢеӨ©з©әгҒ®иҲҹгҖҚгҖҢдҫ йӘЁиЁҳгҖҚгҖҢзҺӢ家гҒ®йўЁж—ҘгҖҚгҖҢеӨҸ姫жҳҘз§ӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе°ҸиӘ¬гӮ’еӨҡгҒҸжӣёгҒ„гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҒҜеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҖ…гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮгҒ®гӮ’иҖғгҒҲгҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢжјўеӯ—гҒҜдҪ•гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҒӢгҒӘгҒ©гҒ«гӮӮзҘһзөҢгӮ’иЎҢгҒҚеұҠгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҢиӘӯгӮ“гҒ гҖҢзҺӢ家гҒ®йўЁж—ҘгҖҚгҒҜж®·зҺӢжңқжң«жңҹгҒ®гҖҒиҘҝе‘ЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж»…дәЎгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®гғүгғ©гғһгҒҢеұ•й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶе°ҸиӘ¬гҒҜзҷҪе·қйқҷгҒ®ж–Үеӯ—гғҜгғјгғ«гғүгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁдёҖж®өгҒЁйқўзҷҪгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҜгҒҫгҒ еҲқеҝғиҖ…гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҪ“еҲҶиҲҲе‘ігҒҜе°ҪгҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ







