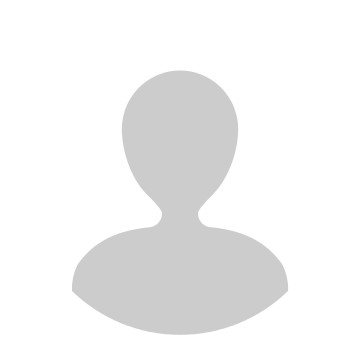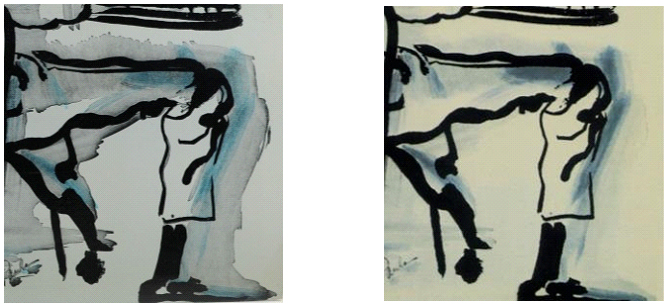|
昨年の11月に少し体調を壊し、回復するのに12月の半ばまでかかってしまった。そのためか、大橋さんのラジオ番組「ようこそオーディオルーム」の12月27日の2時間ジャズ特集を、ライブ放送で行う事となった。すべて原因がぼくにあったわけではないと思っているが、とにかくスリリングな体験をしてしまった。
長年ジャズを聞いているが、首を突っ込めば突っ込むほど奥深くて、まだまだ知らないことが多く、普段は興味がそういうところに向いているが、こういった番組に参加させてもらうと、今まで理解していたはずの演奏でも改めて聞いてみると、また新しい発見があったりしてなかなか楽しい時間を過ごさせてもらった。大橋さんには感謝である。
番組の内容は、ブルーノートのオリジナル盤を中心に選定して、ハイレゾ音源と聞き較べたりしながら、バンゲルダーサウンドをたっぷりと堪能した2時間であった。もちろんFMの電波を通すのと直接の再生音を聞くのとを較べると差が出てしまい、リスナーにどの程度伝わったかは不安もあるが。しかし、参加したぼくとしてはブルーノートのオリジナル盤の音の良さを改めて認識し直した。再発盤とか国内盤に比べて音の鮮度感がまるで違うのである。もちろん、ハイレゾ音源も音の分離とか高音の繊細感では大変優れていることも認識したが。
今ぼくはスタンゲッツのStan Getz At Largeという2枚組のLPのオリジナル盤を聞いている。ゲッツの演奏は、ブルーノートが録音した黒人を中心としたホットな演奏とはまた違った雰囲気があり、このアルバムはCDで手持ちしており、内容についてはわかっていたので、入手してからしばらく聞くこともなしに置かれていたが、オリジナル盤の音を確かめる気になった。
 ・Stan Getz At Large (Verve MGV 8393-2)
・Stan Getz At Large (Verve MGV 8393-2)
Stan Getz (tenor saxophone) Jan Johansson (piano)
Daniel Jordan (bass) William Schiopffe (drums)
"Kildevangs Church", Copenhagen, Denmark, January 14 & 15, 1960
A : Night And Day, Pammie’s Tune, Amour
B : I Like To Recongnize The Tune, When The Sun Come Out,
Just A Child, Folks Who Live On The Hill
C : Cafe Montmartre Blues, He Was Too Good For Me,
Younger Than Springtime, Good-Bye
D : Land’s End, In Your Own Sweet Way, In The Night
このアルバムは1960年、ゲッツが33歳の時に、コペンハーゲンでライブ演奏を行ったものを録音したものである。メンバーにはスエーデンのピアノの名手ヤン・ヨハンソンなどが参加している。晩年のゲッツの演奏は真剣勝負をしているかのような緊張感と凄みを感じるが、この時の演奏はむしろゆったりとしたゆとりを感じられ、聞いていてこちらもリラックス出来るのである。
まず最初に、ぼくの好きなB面のFolks Who Live On The Hillを聞いてみた。この曲については、ゲッツがポーランドで録音した演奏が、録音も良く決定盤だと思っていたが、この深々と聞こえるオリジナル盤の音には、思わず聞き入ってしまった。それでA面からすべてをじっくりと聞く気になったのである。ヨハンソンのリリカルなピアノも素晴らしく、ゲッツの天才的な歌心を楽しむには最適なアルバムである。

地域のある活動団体から、春になったら地区の交流館を使ってジャズのレコードコンサートを企画したいが協力してもらえないかと相談を受けた。依頼者が以前お世話になった方ですし、好きな事なので協力を約束した。対象は普段あまりジャズを聞いたことのない人で、オーディオとは無縁な方たちなので、分かり易いジャズをできれば初めて体験するような音で聞いてもらえたらと思っている。
オーディオ装置としては、今我が家で快調に音を出しているアルテックのA-7スピーカーを使用し、プリアンプ、メインアンプともに球のアンプで駆動し、音源はLPを使用できたらと思っている。但しそうすると少し広い会場でないと都合が悪いので、可能かどうか検討してもらっている。装置はそうとして、初心者の方にどんなジャズを紹介すればよいか、それがなかなか悩ましい。
まだ時間はあるので、色々と頭を悩ませればよいと考えているが、中でもせっかく大型スピーカーを持ち込むのであれば、ぼくの好きなカウント・ベイシー・オーケストラの演奏を紹介したいと思っている。手持ちのベイシーのアルバムをあれこれ聞きなおしているが、分かり易い演奏で、良くスイングして、しかも音の良い演奏となると、選曲に意外と悩むのである。
ベイシーの強烈なスイング感は初期のカンサス・シティ・スタイルが最高であるが、残念ながら録音が古い。後期の編曲を主体にした演奏は玄人好みである。なかなか条件に合ったイメージの曲が出てこない。もう一度ベイシーのディスコグラフを見直していると、1960年にルーレットより発売されたThe Count Basie Storyというアルバムに目が留まった。特に気にかかったのが、60年代のベイシーがLester Leaps In、Avenue C、Tickle Toes、9:20 Specialなどといったオールドベイシー時代の曲を演奏しているのである。今まで、The Count Basie Storyというタイトルと、2枚組のLPという事で、ルーレットのオムニバス盤のように思っていたが、調べてみるとカウント・ベイシー楽団の設立25周年を記念して、オールドベイシー時代の演奏曲をフランク・フォスターが現代風にアレンジして、当時の最強メンバーで再録音した企画アルバムのようである。
 グッド・ベイトのマスターに主旨を話してこのアルバムがないか探してもらった。もちろんすぐに見つかった。それもルーレットのオリジナル盤である。このアルバムの演奏を聞いてみると、素晴らしい音でオールドベイシーが再現されているのである。なかでもTicl Toes、Every Tub、Lester Leaps Inなどの見事なアンサンブルとソロを聞くと、ベイシーの凄さが良くわかる。ただこの盤はモノラル盤であり、並行してステレオ盤も発売されているようで、やはりビッグ・バンドはステレオ盤で聞きたいと思った。
そんなことを感じながら、もう一度手持ちのLPを眺めていたら、「ワン・オクロック・ジャンプ・カウント・ベイシー・スペシャル」というタイトルの国内発売のオムニバス盤にレスター・リープス・インという曲が収録されているではないか。このアルバムはオムニバス盤であり、冒頭にOne O’Clock Jumpというあまり音の良くない録音のライブ演奏が収められていたので、気に留めなかったが、よくよく確認してみると、この1曲以外の11曲はThe Count Basie Storyというアルバムからのピックアップでしかもステレオ録音である。Lester Leaps Inを聞いてみると、右からはサックス群の、左からはトランペット群のアンサンブル、中央からリズムの音が飛び出してくる。ソロはフランク・フォスターである。これがレスター・ヤングであれば完璧であるがそれは無理だ。
グッド・ベイトのマスターに主旨を話してこのアルバムがないか探してもらった。もちろんすぐに見つかった。それもルーレットのオリジナル盤である。このアルバムの演奏を聞いてみると、素晴らしい音でオールドベイシーが再現されているのである。なかでもTicl Toes、Every Tub、Lester Leaps Inなどの見事なアンサンブルとソロを聞くと、ベイシーの凄さが良くわかる。ただこの盤はモノラル盤であり、並行してステレオ盤も発売されているようで、やはりビッグ・バンドはステレオ盤で聞きたいと思った。
そんなことを感じながら、もう一度手持ちのLPを眺めていたら、「ワン・オクロック・ジャンプ・カウント・ベイシー・スペシャル」というタイトルの国内発売のオムニバス盤にレスター・リープス・インという曲が収録されているではないか。このアルバムはオムニバス盤であり、冒頭にOne O’Clock Jumpというあまり音の良くない録音のライブ演奏が収められていたので、気に留めなかったが、よくよく確認してみると、この1曲以外の11曲はThe Count Basie Storyというアルバムからのピックアップでしかもステレオ録音である。Lester Leaps Inを聞いてみると、右からはサックス群の、左からはトランペット群のアンサンブル、中央からリズムの音が飛び出してくる。ソロはフランク・フォスターである。これがレスター・ヤングであれば完璧であるがそれは無理だ。
うーん!これは音の良いモノのオリジナル盤か、ステレオの国内盤を選ぶか、悩ましい!

2009年1月15日の雑記帳に書いた、1980年代のオーディオ装置の中で、レコードプレーヤー・SONY PS-X700を手元に置いてずっと使用してきた。このプレーヤーの機能については、オーディオの足跡というブログに詳しく乗っている。
ぼくがこのプレーヤーを愛用している最大の理由は、カートリッジの音の比較に大変便利だからである。アームにカートリッジを取り付けて、ツマミで指定針圧を表示すれば、後はプレーヤーが自動でゼロバランスを取り、必要な針圧を印加してくれる。更に演奏中であってもツマミを回せば針圧を変えられる。面倒は操作をしなくても簡単にカートリッジのききくらべが出来る。最も便利なだけに、必要以上にカートリッジを聞き較べたくなるのは、困った時もあるが。
 それからアームが水平方向も、垂直方向もリニアモータに電子制御をかけた駆動となっているので、レコードのそりにもめっぽう強い。テラークの録音によるチャイコフスキーの大砲も楽々とトレースする。30センチLPとEP盤も自動検知して針をぴったと着けてくれる。(EP盤を任せるのに最初はハラハラしたが)とにかく手軽に色々なことが出来るのである。ただし針圧が1.5g以下のハイコンプライアンスタイプのカートリッジは、要注意である。モノによってはカンチレバーがたわみ過ぎる。音の特徴は、低音が少しダンピングの効きすぎたような、響きが薄くなるような気がする。と言って大きな不満になるほどではないので、愛用していたのである。
それからアームが水平方向も、垂直方向もリニアモータに電子制御をかけた駆動となっているので、レコードのそりにもめっぽう強い。テラークの録音によるチャイコフスキーの大砲も楽々とトレースする。30センチLPとEP盤も自動検知して針をぴったと着けてくれる。(EP盤を任せるのに最初はハラハラしたが)とにかく手軽に色々なことが出来るのである。ただし針圧が1.5g以下のハイコンプライアンスタイプのカートリッジは、要注意である。モノによってはカンチレバーがたわみ過ぎる。音の特徴は、低音が少しダンピングの効きすぎたような、響きが薄くなるような気がする。と言って大きな不満になるほどではないので、愛用していたのである。
このプレーヤーが、昨年アームが時々不規則な動きをするようになった。裏蓋を開けてみると、このプレーヤーは電子基板がぎっしりと詰まっており、とても素人の手におえるようなものではない。知り合いのプロの方にプレーヤーを預け、しばらく使ってもらい不具合を確認し、修理が出来るか依頼をした。そのプレーヤーが返ってきた。たぶん大丈夫だと思うので使ってみてほしいというのである。という事で再び現在使いだしたが、正常に動いている。何に手を加えたのか確認した所、接点を磨いただけという事である。この便利なプレーヤーがまだ当分使えそうなので、うれしい限りである。
ところで今評価すると、とても便利で先進的なSONYのこのプレーヤーも、これが売り出された時には今ほど素晴らしいと思わなかった。このことについて当時の雑誌にこのプレーヤーについて評価した藤岡誠さんの記事が載っていた。このプレーヤーの便利さ、素晴らしさについて述べたのちにこう書いている。「こうみてくると、何もかも良いように思える。だからここに取り上げて紹介しているわけだが、しかしマニヤによってはこのフルオートマチックがなんとも逆にやりきれないかも知れない。マニア層はまだ、ここまで先進的なプレーヤーを欲していないように思う・・・マニヤの保守的傾向を責めたい・・・」このプレーヤーの素晴らしさを体験してみなさい、と言っている。ぼくも当時はこの記事を読んでも、自分の音の探求の自由度を狭めるのは嫌だと思っていたのである。どんな素晴らしい商品も、ユーザーの要求とうまくマッチングしないと、なかなか評価されない難しさがあるのである。
オーディオを趣味にして、自分のイメージする良い音のためには、どんな苦労もいとわないという姿勢(価値観)が、現在ではほとんど通用しないような感じがする。現在は小型で、手軽で、あまり費用をかけないという制約条件の中で、音楽を楽しむというのが主流ではないか。SONYのオーディオはどうなっていくのであろうか。

山口克巳さんという方が書かれた「LPレコードに潜む謎・円盤最深部の秘密を探る」誠文堂新光社、2011年発行という本に、LPのジャケットも初期は凸版印刷が使用され、ほぼ30センチLPが発売された頃から徐々にオフセット印刷に切り替わっていった。その中でブルーノートレコードは切り替えが遅れ、1500番台と4000番台の途中まで凸版印刷だったと解説され、具体的例としてホレス・シルバーのBlowin’ The Blues Awayのジャケットが取り上げられていた。
具体的内容を紹介すると、下の一部を拡大したジャケットで左側のジャケットがオリジナルジャケット(1961年)で、右側が1970年代に発売されたユナイテッド・アーチスツ盤のもの。オリジナル盤はグレーと青と黒の3色による凸版印刷、再発は青と黒の2色によるオフセット印刷である。
実は、こんなことを思い出したのも、最近ホレス・シルバーのBlowin’ The Blues Awayのオリジナル盤を入手したからである。このLPについてはキングレコードが発売した国内盤は持っている。そのオビには“オリジナル・ジャケット、オリジナル・レーベルの完全復刻!”と書いてあり、今回入手したオリジナル盤とジャケットの表を比較すると、どちらも3色刷の図案となっていて、確かによく似ている。

 写真の左のオビ付がキングの国内盤で、右が今回入手のオリジナル盤。絵だけを見れば若干の色違いはあるが、足の部分はどちらも3色刷となっている。さすがにブルーノートの国内販売権を入手したキングはこの辺はきちっと意識してジャケットを作成している。これだけでは印刷の違いは分からない。ところが凸版印刷とオフセット印刷を見分ける方法は、活字を拡大してみると分かるようである。活字の写真の上段がオリジナル盤、下段が国内盤。上段の文字の縁がしっかりとしていて、輪郭部分のインクがムラになって白いすじが付いているのが凸版印刷。下段の輪郭はきちんとしているが凸版に比べて黒の濃度が薄いのがオフセット印刷のようである。
写真の左のオビ付がキングの国内盤で、右が今回入手のオリジナル盤。絵だけを見れば若干の色違いはあるが、足の部分はどちらも3色刷となっている。さすがにブルーノートの国内販売権を入手したキングはこの辺はきちっと意識してジャケットを作成している。これだけでは印刷の違いは分からない。ところが凸版印刷とオフセット印刷を見分ける方法は、活字を拡大してみると分かるようである。活字の写真の上段がオリジナル盤、下段が国内盤。上段の文字の縁がしっかりとしていて、輪郭部分のインクがムラになって白いすじが付いているのが凸版印刷。下段の輪郭はきちんとしているが凸版に比べて黒の濃度が薄いのがオフセット印刷のようである。
従来はLPのラベルを見て、住所とか、溝の有無とか、RVGの刻印とかを見てオリジナル盤の有無を議論していたが、ジャケットの印刷方法の違いでも年代を推定できるようである。まぁ、どうでも良いようなことであるが、マニアの話題提供には面白い。
で、肝心の音はどうか。キングの国内盤も“名ミキサー、ルディ・ヴァン・ゲルダーのオリジナルサウンドを再現!”と謳っているようになかなか良い音である。しかし比較してしまうと、音の鮮度感で少しオリジナル盤が良いと思える。