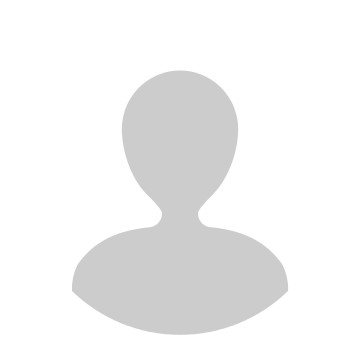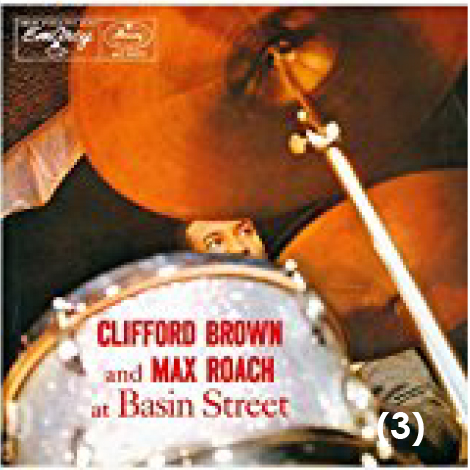|
ジャズをレーベル別に特集してシリーズとして収録してきましたが、7月3-4週放送分のテーマはEmarcy/Marcuryレーベルです。Emarcyは50年代の半ばにMarcuryのジャズ部門として、ボブ・シャッドをプロデューサーに迎えてスタートし、その全盛期にマックス・ローチ~クリフォード・ブラウン・クインテットの名演の大部分をプロデュースしたレーベルとして輝いている。またジェリー・マリガン、キャノンボール・アダレイやローランド・カークを売り出したり、ヘレン・メリルやサラ・ボーンなどのボーカルにも力を入れていた。 今回の収録音源を以下に示す。
| No | 選曲者 | 演奏リーダー | 曲名 | アルバム名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 | Helen Merrill | You'd Be So Nice To Come Home To | Helen Merrill With Clifford Brown |
| 2 | 神谷 | Clifford Brown | I'll Remember April | More Study In Brown |
| 3 | 清水 | Clifford Brown And Max Roach | What Is This Thing Called Love? | At Basin Street |
| 4 | 神谷 | Paul Bley | There'll Never Be Another You | Paul Bley |
| 5 | 清水 | Cannonball Adderley | Stars Fell On Alabama | In Chicago |
| 6 | 神谷 | Roland Kirk | We Free Kings | We Free Kings |
最初(1番目)にこれがEmarcyの代表的名盤だと大橋さんが選んだヘレン・メリルのHelen Merrill With Clifford Brownというアルバム。このアルバムタイトルにWith Clifford Brownとついているのは日本盤のみであるが、それほどにヘレン・メリルの歌とともにクリフォード・ブラウンのトランペットも素晴らしい、まさに大名盤である。取り上げられた曲は彼女の代表的名唱You'd Be So Nice To Come Home Toである。ハスキーな歌声を大いに楽しめる。エピソードとして、この曲を大橋巨泉さんが<帰ってくれたら嬉しいわ>と訳したが、のちに本人がこれは誤訳で<君の元に帰っていけたら幸せ>というのが正しい意味であると言っている。これに関連して寺井珠重さんが「これはプロポーズの言葉である」と解説されている。珠重さんの訳された詩を以下に引用させてもらいます。
=You'd be So Nice to Come Home To=
You'd be so nice to come home to,
You'd be so nice by the fire,
While the breeze, on high, sang a lullaby,
You'd be all that I could desire,
Under stars, chilled by the winter,
Under an August moon, burning above
You'd be so nice,
You'd be paradise to come home to and love.
この対訳ノートを、大橋巨泉さんに捧げます。(珠重さんの言葉)
家に帰って、君が出迎えてくれたなら、とても素敵だろうな。
暖まった暖炉のそばに君が居れば、もう最高だろうな。
心地良く吹くそよ風が子守歌を歌ってくれても、
僕の願いは君と一緒になることだけ。
凍てつく冬の星の下、
8月の燃える月の下、
いつも君と一緒なら、素敵だろうな、
最高に幸せだろうな、僕を待つ、愛する伴侶が君ならば。
少々引用が長くなりましたが、お許しください。
2番目にマスターが取り上げたのは、クリフォード・ブラウン(tp)のMore Study In Brownであり、3番目に僕が取り上げたのが、ブラウン=ローチ・クインテットのAt Basin Streetと共にクリフォード・ブラウンを取り上げた。厳密にいえば1曲目もクリフォード・ブラウンであり、彼はまさにEmarcyを代表するスターである。なかでもマスターが取り上げたMore Study In BrownというアルバムはブラウンがEmarcyに録音して未発表のオリジナル音源をもとに、日本人が企画・制作した貴重盤である。ぼくの選んだAt Basin Streetというアルバムは、ブラウンが自動車事故で無くなる数か月前の録音で、ソニー・ロリンズがテナーを担当し、ブラウンに触発されてバップのイデオムで溌剌と演奏しているのも一つの聞きどころである。
4番目にマスターが取り上げたのは、若きポール・ブレイ(p)のPaul BleyというアルバムよりThere'll Never Be Another Youという曲の演奏である。ポール・ブレイのピアノといえば、少しアヴァンギャルドなと言うか、フュージョンぽい演奏を連想する方が多いと思うが、ここではまるでバド・パウエルのようなバップのスタイルで演奏している。マスターが持ってきたのがWing Recordsのオリジナル盤で音も大変良い。
5番目に僕が提供したのが、キャノンボール・アダレイ(as)のCannonball Adderley Quintet In Chicagoというアルバムである。このアルバムで演奏しているメンバーは、マイルス・ディヴィスがKind Of Blueを発表する直前のレギュラー・メンバーよりマイスルが抜けたクインテット構成である。当時のメンバーの充実した演奏が展開されている。持ち込んだのはステレオのオリジナル盤である。このアルバムは1959年の発売であるが、これとは別にLimelightレーベルより同じ演奏がCannonball & Coltraneというタイトルで、しかもジャケットは全く別のデザインで1964年に発売された。人によってはこちらのアルバムのオリジナル盤のほうが音が良いという評価をする。
 ぼくの大好きなキャノンボールであるが、このころはマイルスのメンバーの力を借りていた演奏していた感じがする。彼が本当に自分のコンボを作って活躍しはじめたのは、8か月後にリバーサイドに移籍して、弟のナット・アダレイと共に演奏したThe Cannonball Adderley Quintet In San Franciscoというアルバム以降である。これ以降の彼のアルバムは、まさにファンキー・ブームを代表するものである。
ぼくの大好きなキャノンボールであるが、このころはマイルスのメンバーの力を借りていた演奏していた感じがする。彼が本当に自分のコンボを作って活躍しはじめたのは、8か月後にリバーサイドに移籍して、弟のナット・アダレイと共に演奏したThe Cannonball Adderley Quintet In San Franciscoというアルバム以降である。これ以降の彼のアルバムは、まさにファンキー・ブームを代表するものである。
最後(6番目)にマスターが取り上げたのがローランド・カークのWe Free Kingsというアルバムである。このアルバムは若き日のローランド・カークの2番目のリーダー作で、ローランド・カーク入門には最適のアルバムである。ジャケットの写真にあるようにマルチリードを同時に口にくわえて演奏する彼のスタイルは、はまった人にはたまらない魅力であり、熱狂的なファンもいる。
収録を終えてみると、やはりEmarcyの魅力の第1は、クリフォード・ブラウンの輝かしい演奏が印象的である。

収録の終了後の写真を撮りながら、次回はどんな企画で行きますかという話になり、もう少しレーベル別特集を続けましょうということになりました。続きをご期待ください。