|
гҖҖж”ҫйҖҒгҒ®дәӢеүҚжү“гҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒ®жҷӮгҒ«еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ®йҒёжӣІгӮ’иҰӢгҒҰгҖҒзҙ зӣҙгҒ«еҗҚзӣӨгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒ®йҒёжӣІгҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгҒ„гҒ„гҒӯпјҒгҒЁжҖқгӮҸгҒҡиЁҖгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҮӘеҲҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’зҙ зӣҙгҒ«йҒёжӣІгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒЁгҖҒеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҜзӯ”гҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠгҒҫгҒ§гҒҜе°‘гҒ—иғҢдјёгҒігӮ’гҒ—гҒҰиүІгҖ…иҖғгҒҲгҒҰйҒёжӣІгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒҜгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒ§иЎҢгҒҚгҒҫгҒҷгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒјгҒҸгҒҜгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮ°гғғгғүгғҷгӮӨгғҲгҒ§ж”ҫйҖҒгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§и©ұгҒҢгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгӮҠгҖҒYжӯҰгҒ•гӮ“гҒӘгҒ©гҒӢгӮүиүІгҖ…гҒЁж„ҸиҰӢгҒЁгҒӢгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮиүІгҖ…гҒӘзҡҶгҒ•гӮ“гҒ«й–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒҰгҒӮгӮҠгҒҢгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
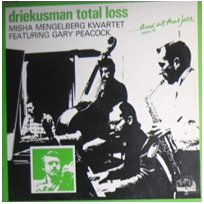
пј‘пјүзҘһи°·пјҡDriekusman Total Loss (9:53)
гғ»Misha Mengelberg Kwartet Featuring Gary Peacock вҖ“ Driekusman Total Loss
гғ»VARAJAZZ вҖ“ 210 (release 1981)
гғ»Recorded on 4 December 1964 (A1-B1) and 28 June 1966 (B2) at VARA-Studio in Hilversum
гҖҖгҖҖAlto Saxophone вҖ“ Piet Noordijk
гҖҖгҖҖBass вҖ“ Gary Peacock (tracks: A1 to B1), Rob Langereis (tracks: B2)
гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Han Bennink
гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Misha Mengelberg
гҖҖгғӘгғјгғҖгғјгҒ§гғ”гӮўгғҺгҒ®гғҹгӮ·гғЈгғ»гғЎгғігӮІгғ«гғҷгғ«гӮҜгҒЁгғүгғ©гғһгғјгҒ®гғҸгғігғ»гғҷгғӢгғігӮҜгҒҜгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®йҢІйҹігҒ®зӣҙеүҚгҒ«гӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®гғ©гӮ№гғҲгғ»гғҮгӮӨгғҲгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®йҢІйҹігҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгӮўгғ«гғҲгҒ®гғ”гғјгғҲгғ»гғҺгғ«гғҮгӮЈгӮҜгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®жј”еҘҸе…ЁдҪ“гҒҢгғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®жј”еҘҸгӮ’жғіеғҸгҒ•гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйӣ°еӣІж°—гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®йҖғгҒ•гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгғһгӮ№гӮҝгғјгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮ

пј’пјүжё…ж°ҙпјҡIntroduction,The Ballad Of Thelonious Monk 6:22
гғ»Carmen McRae вҖ“ The Great American Songbook
гғ»Atlantic вҖ“ SD 2-904 (release 1972)
гғ»Recorded live at Donte's, Los Angeles, California 1972
гҖҖгҖҖBass вҖ“ Chuck Domanico
гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Chuck Flores
гҖҖгҖҖGuitar вҖ“ Joe Pass
гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Carmen McRae (tracks: A3, D3), Jimmy Rowles
гҖҖгҖҖVocals вҖ“ Carmen McRae
гҖҖгҒјгҒҸгҒҢгӮ«гғјгғЎгғігӮ’йҒёжӣІгҒҷгӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгҖҒгҒЁиҮӘеҲҶгҒ§гӮӮй©ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгӮ«гғјгғЎгғігҒҢгӮ®гӮҝгғјгҒ®гӮёгғ§гғјгғ»гғ‘гӮ№гҖҒгғ”гӮўгғҺгҒ®гӮёгғҹгғјгғ»гғӯгӮҰгӮәгҒӘгҒ©гҒЁе…ұгҒ«гҖҒгғӯгӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгғҖгғігғҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮҜгғ©гғ–гҒ§гғ©гӮӨгғ–жј”еҘҸгӮ’гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’йҢІйҹігҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҖҒгӮҜгғ©гғ–гҒ®еӨ§еӨүжҘҪгҒ—гҒ„йӣ°еӣІж°—гҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒјгҒҸгӮӮеӨ§гҒ„гҒ«жҘҪгҒ—гӮ“гҒ гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгӮ«гғјгғЎгғігҒ®гҒҠгҒ—гӮғгҒ№гӮҠгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҰгҖҒгӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгҒ®гғҗгғ©гғјгғүгҒЁгҒ„гҒҶжӯҢгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮ«гғјгғЎгғігҒҢдҪ•гӮ’гҒҠе–ӢгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒгӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгҒ®гғҗгғ©гғјгғүгҒЁгҒ„гҒҶжӯҢгҒҢгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶйўЁгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ®жӯҢгҒӢгӮҸгҒӢгӮӢгҒЁгӮҲгӮҠдёҖеұӨжҘҪгҒ—гҒ•гҒҢеў—гҒҷгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒжІ№дә•жӯЈдёҖгҒ•гӮ“гҒҢжӣёгҒ„гҒҹгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®гғ©гӮӨгғҠгғјгғҺгғјгғ„гӮҲгӮҠгҒқгҒ®йғЁеҲҶгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ
гҖҖгҖҢгӮёгғҹгғјгғ»гғӯгӮҰгӮәгҒҢдҪңжӣІгҒ—гҒҹBehind The FaceгҒЁгҒ„гҒҶеј·зғҲгҒӘгғЎгғғгӮ»гғјгӮёжҖ§гҒ®еј·гҒ„жӯҢгӮ’гҒҶгҒҹгҒЈгҒҹеҫҢгҖҢгҒ©гҒҶгӮӮгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҖӮгӮёгғҹгғјгғ»гғӯгӮҰгӮәгҒҜеҮ„гҒҸжүҚиғҪгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж¬ЎгҒ®жӯҢгҒҜд»ҠгҒ®жӯҢгҒЁе…ЁгҒҸйҒ•гҒҶгҖӮжң¬еҪ“гҒ«еӨ©жүҚгҖӮгҒ“гҒ®жӯҢгҒҜгӮёгғҹгғјгҒҢгҖҒеҗҢгҒҳгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ§гҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ¬гғғгӮ·гғҙгғ»гғ•гӮЎгӮәгҒ®ж”№йқ©иҖ…гӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгӮ’жӯҢгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгҒ“гҒ“гҒ«гҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгӮӢж–№гҒҜгғўгғігӮҜгӮ’гҒ”еӯҳгҒҳгҒ гҒҢгҖҒгғ¬гӮігғјгғүгӮ’иІ·гҒЈгҒҰдёӢгҒ•гӮӢж•°зҷҫдёҮгҒ®ж–№гҒ«гғ»гғ»гғ»гҒқгҒ®дҪҚеЈІгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒ„гҒ‘гҒ©гғ»гғ»гғ»гӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгҒЁгҒҜгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶдәәгҒӢиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖҚпјҲдёӯз•ҘпјүгҖӮгҖҢгғўгғігӮҜгҒ®йҹіжҘҪгӮ’иҒһгҒ„гҒҹдәәгҒӘгӮүгҖҒгӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгӮ’гӮ«гғігғҲгғӘгғјпјҶгӮҰгӮЁгӮ№гӮҝгғізҡ„жӯҢгҒ«гҒҷгӮӢйӣЈгҒ—гҒ•гҒҢгҒҠгӮҸгҒӢгӮҠгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгғўгғігӮҜгҒҢ130еӣһз”ҹгҒҫгӮҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгӮӮгӮ«гӮҰгғңгғјгӮӨгҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҚгҖӮгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰ笑гӮҸгҒӣгҒҹгҒӮгҒЁпјңгӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгҒ®гғҗгғ©гғјгғүпјһгӮ’жӯҢгҒҶгҖҚгҖӮгӮ»гғӯгғӢгӮўгӮ№гғ»гғўгғігӮҜгҒ®гғҗгғ©гғјгғүгҒЁгҒ„гҒҶжӯҢгҒ®жӯҢи©һгӮӮеӨ§еӨүйқўзҷҪгҒ„гҒҢгҖҒжӣёгҒҚгҒ гҒҷгҒЁй•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§зңҒз•ҘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
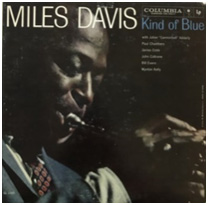
пј“пјүеӨ§ж©ӢпјҡBlue In Green (5:27)
гғ»Miles Davis вҖ“ Kind Of Blue
гғ»Columbia вҖ“ CL 1355 (release 1959)
гғ»Recorded March 2 and April 22 of 1959
гҖҖгҖҖAlto Saxophone вҖ“ Julian Adderly (tracks: A1, A2, B1, B2)
гҖҖгҖҖBass вҖ“ Paul Chambers
гҖҖгҖҖDrums вҖ“ James Cobb
гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Bill Evans (tracks: A1, A3 to B2), Wynton Kelly (tracks: A2)
гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ John Coltrane
гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Miles Davis
гҖҖгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«гғ“гғ«гғ»гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гӮ’иҝҺгҒҲгҒҰгҖҒгғһгӮӨгғ«гӮ№гҒҢгғўгғјгғүеҘҸжі•гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҰжј”еҘҸгҒ—гҒҹеҗҚзӣӨгҒЁгҒ—гҒҰгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҒёжӣІгҒҢBlue In GreenгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“еҘҪгҒҝгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
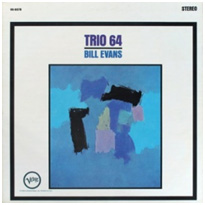
пј”пјүзҘһи°·пјҡSanta Claus Is Coming To Town (4:22)
гғ»Bill Evans вҖ“ Trio 64
гғ»Verve Records вҖ“ V6-8578 (release 1964)
гғ»Recorded in New York City, Dec. 18, 1963
гҖҖгҖҖBass вҖ“ Gary Peacock
гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Paul Motian
гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Bill Evans
гҖҖгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒҢгғҷгғјгӮ№гҒ®гӮІгғјгғӘгғјгғ»гғ”гғјгӮігғғгӮҜгҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҒ“гӮҢ1жһҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®дёӯгҒ«гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒҢеҘҪгҒҚгҒ гҒЈгҒҹSanta Claus Is Coming To TownгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’иҰӢйҖғгҒ•гҒҡгҖҒгӮҜгғӘгӮ№гғһгӮ№гҒ®жҷӮжңҹгҒ«жҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҒҜгҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гӮёгғЈгӮәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жӣІгҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгӮүгҒҡгҖҒж·ЎгҖ…гҒЁжј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгҒјгҒҸгҒ гҒ‘гҒ®ж„ҹиҰҡгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
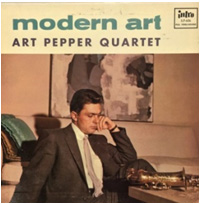
пј•пјүжё…ж°ҙпјҡBlues In (5:40)
гғ»Art Pepper Quartet вҖ“ Modern Art
гғ»Intro Records вҖ“ ILP 606 (release 1957)
гғ»Recorded at Radio Recorders, Los Angeles on December 28, 1956
гҖҖгҖҖAlto Saxophone вҖ“ Art Pepper
гҖҖгҖҖBass вҖ“ Ben Tucker
гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Chuck Flores
гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Russ Freeman
гҖҖиӢҘгҒҚгӮўгғјгғҲгғ»гғҡгғғгғ‘гғјгҒ®жј”еҘҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮӨгғігғҲгғӯгҒ®гғўгғҖгғігӮўгғјгғҲгҖҒгӮҝгғігғ‘гҒ®гӮўгғјгғҲгғ»гғҡгғғгғ‘гғјгғ»гӮ«гғ«гғҶгғғгғҲпјҲдҫӢгҒ®гҒ№гӮөгғЎгғ»гғ гғјгғҒгғ§гҒ®е…ҘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®пјүгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүгӮөгғҙгӮ©гӮӨгҒ®гӮөгғјгғ•гғ©гӮӨгғүгҖҒгҒ“гҒ®3жһҡгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’гӮҲгҒҸиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғ–гғ«гғјгӮ№гғ»гӮӨгғігҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒҜгҖҒгғҡгғғгғ‘гғјгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜзҸҚгҒ—гҒҸгғҷгғјгӮ№гҒ®гғҷгғігғ»гӮҝгғғгӮ«гғјгҒЁгғҮгғҘгӮӘгҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҲгҒ®йҹіиүІгҒ гҒ‘гӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҒҫгҒ•гҒ«гғҡгғғгғ‘гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҮгғҘгӮӘжј”еҘҸгӮ’гӮҲгҒҸгӮ„гӮӢгҒ®гҒҜгғӘгғјгғ»гӮігғӢгғғгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж”ҫйҖҒгҒ®дёӯгҒ§еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ®зҷәиЁҖгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢзӘҒгҒЈиҫјгҒҝгӮ’е…ҘгӮҢгҖҒдәҢдәәгҒ§гҒӮгӮҢгҒ“гӮҢиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгғӘгғјгғ»гӮігғӢгғғгғ„гӮӮгӮҲгҒҸиҒһгҒҸгҒЁгҖҒжҷӮгҒ«гҒҜдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгҒЁжҖқгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮжңүгӮӢгҖӮ

пј–пјүеӨ§ж©ӢпјҡTenderly (3:02)
гғ»Ben Webster вҖ“ King Of The Tenors
гғ»Verve Records вҖ“ MGV-8020 (release 1957),
гҖҖгҖҖAlto Saxophone вҖ“ Benny Carter (tracks: A1 to A4, B2)
гҖҖгҖҖBass вҖ“ Ray Brown
гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Alvin Stoller (tracks: A1 to A4, B2), J.C. Heard (tracks: B1, B3, B4)
гҖҖгҖҖGuitar вҖ“ Barney Kessel (tracks: B1, B3, B4), Herb Ellis (tracks: A1 to A4, B2)
гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Oscar Peterson
гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ Ben Webster
гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Harry Edison (tracks: A1 to A4, B2)
гҖҖгғҷгғігғ»гӮҰгӮ§гғ–гӮ№гӮҝгғјгҒ®гғҶгғҠгғјгҒҜзӢ¬зү№гҒ®гҒҶгҒӯгӮҠгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҠӣеј·гҒҸгҒҰзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢйҒёгҒ¶жӣІгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгғҷгғігҒ®гғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгҒЁгҒӢгғҶгғҠгғјгҒ®йҹіиүІгҒ«йӯ…еҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒјгҒҸгҒ«гҒҜжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮзү№гҒ«еҪјгҒ®гғҗгғ©гғјгғүгғ»гғ—гғ¬гӮӨгҒҜзӢ¬зү№гҒ®жё©гҒӢгҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҒқгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҜеҪјгҒҢгғӘгғјгғҖгғјгҒЁгҒ—гҒҰжј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғ«гғҗгғ гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгғҮгғҘгғјгӮҜгғ»гӮЁгғӘгғігғҲгғіжҘҪеӣЈгҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢйӯ…еҠӣзҡ„гҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒӘгҒңгҒ гҒӢиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ„гҒЈгҒЁе°‘гҒ—гғҡгғјгӮ№гӮ’еҸ–гӮҠжҲ»гҒ—гҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е№ҙжң«гҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰең°еҹҹгҒ®иЎҢдәӢгҒёгҒ®еҸӮеҠ гӮ„гҖҒиҫІжҘӯгҒ®и¬ӣзҫ©гҒӘгҒ©гҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁж®ӢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҫҢеҚҠгҒ®еҺҹзЁҝгҒҢйҒ…гӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж°—гӮ’еј•гҒҚз· гӮҒгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ








